Archive for the ‘(連載)たそがれ駄小説’ Category
連載 73: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (9)
七、 しらゆり⑨
黒川は自説を全く修正しなかった。よく知りもせず夫婦のことに口出しするな、親子のことへの干渉は第三者特有の無責任な建前論だと一歩も譲らない。 そればかりか激しい会話の挙句、思いもよらない難癖を付けて来た。 「思っていた通り君もやはり美枝子と同じ世代・同じ傾向の自己愛人間だ。同じ穴の狢なんだよ。持続できないことをその場の自分の気持ち最優先でやっちゃう。相手・ことの実像、関係の総体を幾重にも検討して、時には引く・・・・それを知らない、知ろうとしない」 「はあ? それ、黒川さんあんた自身の自己分析ですか? あんたにだけは言われたくない。その言葉そっくりあんたに返させてもらいます」 ![DSC_0518_2[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0518_211.jpg) 「そうじゃないか! 君は何度かひろしを海へ連れて行ったが、ひろしに喜んでもらっていい気分を味わいたいという君のエゴなんだよアレは」 「何~ぃ! 連れて行ってやってくれ、と言ったのはあんたじゃないか」 「ぼくが遅くなった日に、久茂地の居酒屋へ二度も連れて行ったのも知っているぞ。君は大阪へ帰る人間だ、無責任なんだよ! 後のことはどうにでもなれ、ぼくは知らない好きにしろ、あとは野となれ山となれって訳か。車の運転など出来ない上に炎天下は身体に障る病を抱えた老人に、バスを乗り継いで連れて行くことなど出来ないことを知ってるくせに。ひろしに、ぼくが出来ないことを次々するんじゃないよ」 「何を言うとんのや。あんたが監督可能なこと、あんたが同行可能な範囲のことしかユウくんに体験させないと言うのか? その中にユウくんの人生を閉じ込めておけと言うのか? あんたこそ自己中心主義だと思わないのか」 「食事にしたってそうだ。ぼくでも簡単に作れる範囲のメニュウとか、買ってきて電子レンジでチーンするとか、出来るだけそういうものしようと心がけない。手をかける。君が居なくなった後ぼくに出来ないことばかりしやがって」 「あれが食いたいこれを作れと言うたのはあんたやないか。食って美味い美味いと褒めて煽てて・・・。」 「褒めるのは礼儀だからだ」 「話にならん! ぼくがしたことは全部迷惑やったと言うわけやな。ちょうどええ、店もオープンに漕ぎ着けたっことだし、いよいよ帰らせてもらう。もうあんたと言い合うのは止める。時間と精神の浪費や。結論!さいなら」 「残された者に出来ないことを見せつけ見せびらかし、上から目線を保ったまま帰りゃいいさ。勝手にしなさい。沖縄に移住した父子の処へ、軽い気持ちで気分転換とばかりにやって来た己の軽薄を噛み締めるがいい。いいか、ぼくは沖縄にずっと居るんだ、君と違って」 言い返す気にもなれず、部屋を出た。階段を降り始めた裕一郎の背中に、黒川が「明日のオープンも視に来なくていいからね」と投げつける声が聞こえた。続けて「去る者が一体何を視ると言うんだ」とつぶやくのも聞こえた。 いつか黒川は「ぼくもついこのあいだ六十だった。二十年はアッという間だよ。君もすぐぼくと同じ歳になるんだ。自覚しているかね」と言っていた。黒川にこそ、その自覚を求めたい。だが、その通りなのだ、俺もきっとすぐ八十だ。さっき展開された言い合いは、しばしばニュースが伝える老老介護の果ての殺人のようだ。じゃれ合い喧嘩のように見える発情牡象の威嚇のように、時に大怪我もする。些細に見えて、人と人の諍いの縮図なのだ。事実、黒川は最後の一撃を仕掛けて来た。
「そうじゃないか! 君は何度かひろしを海へ連れて行ったが、ひろしに喜んでもらっていい気分を味わいたいという君のエゴなんだよアレは」 「何~ぃ! 連れて行ってやってくれ、と言ったのはあんたじゃないか」 「ぼくが遅くなった日に、久茂地の居酒屋へ二度も連れて行ったのも知っているぞ。君は大阪へ帰る人間だ、無責任なんだよ! 後のことはどうにでもなれ、ぼくは知らない好きにしろ、あとは野となれ山となれって訳か。車の運転など出来ない上に炎天下は身体に障る病を抱えた老人に、バスを乗り継いで連れて行くことなど出来ないことを知ってるくせに。ひろしに、ぼくが出来ないことを次々するんじゃないよ」 「何を言うとんのや。あんたが監督可能なこと、あんたが同行可能な範囲のことしかユウくんに体験させないと言うのか? その中にユウくんの人生を閉じ込めておけと言うのか? あんたこそ自己中心主義だと思わないのか」 「食事にしたってそうだ。ぼくでも簡単に作れる範囲のメニュウとか、買ってきて電子レンジでチーンするとか、出来るだけそういうものしようと心がけない。手をかける。君が居なくなった後ぼくに出来ないことばかりしやがって」 「あれが食いたいこれを作れと言うたのはあんたやないか。食って美味い美味いと褒めて煽てて・・・。」 「褒めるのは礼儀だからだ」 「話にならん! ぼくがしたことは全部迷惑やったと言うわけやな。ちょうどええ、店もオープンに漕ぎ着けたっことだし、いよいよ帰らせてもらう。もうあんたと言い合うのは止める。時間と精神の浪費や。結論!さいなら」 「残された者に出来ないことを見せつけ見せびらかし、上から目線を保ったまま帰りゃいいさ。勝手にしなさい。沖縄に移住した父子の処へ、軽い気持ちで気分転換とばかりにやって来た己の軽薄を噛み締めるがいい。いいか、ぼくは沖縄にずっと居るんだ、君と違って」 言い返す気にもなれず、部屋を出た。階段を降り始めた裕一郎の背中に、黒川が「明日のオープンも視に来なくていいからね」と投げつける声が聞こえた。続けて「去る者が一体何を視ると言うんだ」とつぶやくのも聞こえた。 いつか黒川は「ぼくもついこのあいだ六十だった。二十年はアッという間だよ。君もすぐぼくと同じ歳になるんだ。自覚しているかね」と言っていた。黒川にこそ、その自覚を求めたい。だが、その通りなのだ、俺もきっとすぐ八十だ。さっき展開された言い合いは、しばしばニュースが伝える老老介護の果ての殺人のようだ。じゃれ合い喧嘩のように見える発情牡象の威嚇のように、時に大怪我もする。些細に見えて、人と人の諍いの縮図なのだ。事実、黒川は最後の一撃を仕掛けて来た。
積んであった商品や書庫・衝立が持ち出されてガランとなった洋間の椅子に座って想った。 黒川は結局は「帰るな」と言いたいのだ、「帰ってくれるな」と。「君が居なくなればぼくはどうすればいいのだ」と。 だが黒川は、最初からの「オープンまで」との約束を百も承知し、裕一郎の今後の計画もあろうとも思ってはいる。しかも報酬を払えていない以上、帰るのは当然だと充分解かっているのだ。 その二つ、心理と道理の分裂を自覚して、裕一郎を責め立てることに感情を向け、その整理を付けているのだ。 祐一郎は、どんなに理不尽であったとしても、ことの真実をたぶん言い当てている黒川の言葉を振り返っていた。 「軽い気持ち」「気分転換」「沖縄の父子」・・・・。その通りだと思う。 黒川の最後の一撃にはただ黙って聞くしかなかった。黒川はこう言ったのだ。 上から見下して、ぼくとひろしをガードする輝ける騎士・ナイト気取りでいるんだろう? 言っちゃ悪いが、君の携帯に仕事や君の言う社会運動やそして女性から電話なんて掛かっては来ないじゃないか。することが無く、することを喪い、することに去られ、することから逃げた果てに、か弱い老人と障害ある子との危うい家庭へ、沖縄へと、潜り込んだんだ。ああ、もちろんぼくとて同類だとも。しかし君の振舞いや言動に在る、半端インテリ浪人のお助け根性などお見通しだよ。自分と老人黒川とは同じなんだという謙虚がない。 裕一郎は、たまにユウくんが海へだって行けるような方法、その端緒だけは組み立ててから帰ろうと考えた。 そして、黒川の生母探しの言動に、軽くあしらうように接してしまったことを悔いていた。 松山で美枝子は、長崎・原爆・ウメさんのおにぎり・運動会の弁当・美しい女性が登場する黒川から聞いたという話と、広島原爆ドーム前での知念太陽との再会などを語った。もらい泣きしそうになって黒川の孤絶を想ったと語った。元夫婦に在ったはずの絆の大もとを視た気がしたのだ。そうした絆を持ち得るのも、それを解体して憎しみ合えるのも、夫婦ならではの宿業なのか? 憎しみ合っている訳ではないが離れている己が夫婦の姿を思えば、黒川にはそっけなく「ハイハイ」と返してしまうしかない己だったのだ。
(七章 終 次回より 八章、しらゆりⅡ )
連載 72: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (8)
七、 しらゆり⑧
祝いの席だ。黒川は、さすがに美枝子からのプレゼントに関しては口を閉ざした。それがかえって「君には後でゆっくり言うことがあるんだ」というサインに思えた。 ユウくんの「ネクタイとシャツだ」との小声に、黒川が「ひろし、後にしなさい」と言う。ユウくんは半ば明けてしまった荷を申し訳なさそうに隣室へ移動させた。 黒川も裕一郎も怪しいがまあ大人だ、楽しそうに振舞った。祝いの席が終ると、ユウくんが二階で長ズボンに履き替え降りて来て、プレゼントのカラシ色のカッターシャツを着ている。ネクタイは焦げ茶色の地に同系二色で柄が施されている。上品で毅然とした雰囲気のものだった。ユウくんが穿いた焦げちゃ色のズボンにもピッタリ。美枝子がこのズボンを百も承知で選んだのだと判った。 「北嶋さ~ん。ネクタイ付けて」 「はいよ。ネクタイはね、締めると言うんやで」 「ネクタイ、しめて!」 一度では覚えられないネクタイ締めに、ユウくんは「難しいね。面倒くさいね」と言う。暑苦しく首周りが窮屈なこれは「犬の首輪だ」とは言わなかった。役に立つ時もあるのだ。例えば、先日、細川の画廊に債権回収に出向いた時のように・・・、と思って苦笑した。 「似合わない?おかしい?」 「いや、もちろん似合ってるよ。初めてネクタイ締めたとき北嶋さんも苦労したのを思い出して笑うたんや、ゴメンゴメン」  「ふ~ん。北嶋さんでも難しいんだ」 「そうだよ。けど、覚えといて損はない」 「覚えるよ」 ようやくカタチが決まると、ユウくんは玄関の大きな鏡の前へ小走り。 「北嶋さん、写真撮って。ねえチチもおいで、写真をハハに送るよ」 携帯電話で構えると、黒川が苦い顔でユウくんの隣に立った。
「ふ~ん。北嶋さんでも難しいんだ」 「そうだよ。けど、覚えといて損はない」 「覚えるよ」 ようやくカタチが決まると、ユウくんは玄関の大きな鏡の前へ小走り。 「北嶋さん、写真撮って。ねえチチもおいで、写真をハハに送るよ」 携帯電話で構えると、黒川が苦い顔でユウくんの隣に立った。
ユウくんが寝た頃、黒川が部屋へやって来た。黒川はまずは冷静に語り始めた。 「北嶋君。時々電話する、目立つタイミング、印象的な場面で物を送って来る、それは卑怯だと思わないかね?」 「卑怯と言っても、美枝子さんには他に方法が無いじゃないですか」 「出て行ったのはあいつだ」 「それは親の都合でしょう。ユウくんにはハハとの交信の自由、ハハから愛される権利があります。貴方はそれを奪うのですか?」 「いいかい。ひろしと生活しているのはぼくなんだ。時々いい顔をするのは誰にでも出来るんだ。もう会えない、母親をできない・・・、それを覚悟して出て行ったんだろうが、それはあいつが自ら選んだ途なんだ。」 裕一郎は、ここで言ってはならない切り札を出してしまった。 「黒川さん、怒らないで下さいよ。じゃあ、あんたの調査とやらは何なんですか?。生母を探しているじゃないですか。ユウくんに母親に会えないままの同じ想いを強制するんですか?」予想通り黒川の声が変わった。 「それとこれとは違う。ぼくの生母は自ら選んで長崎を去ったのではないはずだ。引き裂かれたのだ。産み役を終えお払い箱にされたに違いない。日本を、実子を封印して戦後を生きたのだ」 「悪いけど、想像でしょう?」 「違う! ほぼ特定出来たんだ。調査の結果、プロフィールが合致する女性の中に、戦後、沖縄で結婚して五六年に五十一歳で亡くなったある女性が、ぼくの幼少期の時代長崎にいたことが判明した。しかも、」 黒川は熱を込めて語る。その女性は一九二七年二十二歳で子を産み、ぼくが生まれた年だ、一九三七年三十二歳の秋沖縄に帰っている。ぼくが尋常小学校四年の運動会の年だ。ほぼ間違いない、母だ。沖縄で結婚し再出発したんだな。母には当然、夫・家・生活・親戚、沖縄の戦後の時間というものがあった。彼女の歳の離れた妹さんがひと度は姉が長崎で子を産んだことを認めていたんだが、後日否定に転じて亡くなったそうだ。調査員は、その妹さんの息子から聞き出した。が、否定したのが遺志でもある。そこを配慮してまだ最後の詳細を言わない。それに、子つまりぼくの妹だねえ、妹も居る。事実を明らかにするには関係者たちが、歴史や事情を越えて協力というか同意してくれないと難しい。容易なことではないんだ。親類縁者・地域社会からの無言にして根深い強迫を押し返して明らかにするには、ぼくの側には在る必然性みたいなものが要るんだが、向こうには無いよね。むしろ秘しておきたい、というのが当然だろう。 「君には解からんだろうが、ぼくは米・日・沖と闘っているんだ。ぼくの戦後総決算だ。闘いは必ず決着してみせる」 「ハイハイ、そうですか。どうぞご自由に」 「聞くんだ。ぼくの生家、ぼくの生家は長崎で有名な料理旅館だったんだが、そこにウメさんという女中さんが居た。原爆被害で大混乱の敗戦直後の長崎、ぼくは生家の前でそのウメさんに再会した。彼女からぼくの出生の事情を聞かされていたんだ。仕事で沖縄へ来るようになって、どうしてもハッキリさせたくなってウメさんのその後を辿った。亡くなっていたよ。生母に関しては、姓名のうち姓はだけは珍しい苗字で思い出せたが、その他聞かされたことを思い出せないで来た」 「美枝子さんから、ウメさんが語った小学校四年の運動会で会った女性の話、聞きましたよ。それはそれとして今はユウくんと美枝子さんの交流の自由の話です。その総決算とやらには、あんたがユウくんと美枝子さんの自由交流を納得することが、むしろ必修条件だとぼくは思いますけどね」」 ここから黒川はさらに語気を荒げた。 「分かったような口を利くんじゃない。本気で総決算などしたことのない崩れ全共闘めが。」 「ちょっと待ちなさい! 本気かどうか怪しいけど、その作業をぼくらなりにして来たんです」 「そのぼくらの{ら}が気に入らないね。君の世代はいつも、何を言うにも{ら}だ。一度くらいぼくと限定しなさい。{ら}なんて無いと知ってるから、お前さんはいつも{ら}なんだよ。しかも本気かどうか怪しいとまで言う。怪しいんじゃなく、してないんだ。ぼくは本気だ。ハッキリと本気だ。米日沖と正面から向き合うぞ。ぼくが母に会うことを妨げる要素は、ぼくにとって全て敵なんだ」 思い込みとは恐ろしい。この自信は何だ。少しは自らの越し方を顧みろよ。 老いの一徹と言えば聞こえは良いが、自身棚上げ方式なのだ。その主張に怯みもする。が、美枝子からの誕生日プレゼントは認めさせたい。 裕一郎は、罵り合いを続けた。
連載 71: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (7)
七、 しらゆり⑦
すぐ三人で移動して玲子の下宿でメシをよばれたから、是非無い待ち合わせではなかったと裕一郎は思っている。 「ぼくじゃない。ぼくでも彼でもない誰か友達やろ。今度、玲子本人に訊いてみるよ」 「な~んだ。男って些細なことを気にしてるんですね。奥さん本人か北嶋さんに訊けば分かるのに、ね・・・。」 「気にしてるのか、あいつ」 「そうは言わなかったけど、奪ったという言葉に負い目みたいなもの感じましたよ。それと、北嶋さんの奥さんが専務の永遠のマドンナだとも言ってました。怒らないで下さいよ、お二人って、何か学生時代や争議や仕事を通じて兄弟のような双子のような、いえ違うな、う~んお互い相手の存在がなければ人生が成り立たないような、相互依存のような・・・。悪いけど、団塊世代?あの人たちみなさんそういう傾向ありません? それって卒業すべきことだと思います」 裕一郎は図星だと思った。だから苛立ちもした。生意気なとも思った。若い女性のこうした言い分に母性のようなものが潜んでいることも知っていた。珍しく不躾な亜希の魂胆が分からない。 「マドンナ? うちの女房が? へえ~意外やな。それはともかく、相互依存? 失礼やろ! なんでそういう話を語るんや?」 「卒業の材料。それと奥さんの処へ帰る後押し」 「余計なお世話やね。放っといてくれよ。何が卒業の材料や、中学生に対する母親みたいなこと言うてくれるな」 「すみません・・・でした」 恥かしさもあって亜希には言えなかったが裕一郎は思うのだ。相互依存だけではないよ、相互刺激や相互研鑽に似た緊張関係の側面だって在るのだ。矜持とも自負とも言えないが、いささかのこだわりはある。その意味をこれまで、体系的に社会的に自他に示せたことなど無い以上、相互依存との指摘に甘んじておこう。 ベンチから起って改札へ向かう亜希が無礼を埋め合わせる為だけではなさそうに言った。 「いい誕生日でした、有り難うございました。永遠の入口と思わせて下さい。いいですよネ」 三十歳も若い亜希に少年をあやすように言われたなとも、彼女が本気で言ってくれたとも思え、この人をこの先も見ていようと思った。こういう年下の女友達は他にいない。貴重なのだ。 「明日のオープンには那覇に留まっているヒロちゃんがお手伝いします。黒川さんに伝えておきました。じゃ、また」亜希は桟橋に去った。
黒川とギャラリーじねんが出るニュース番組を見るべく、黒川宅へ車を走らせた。黒川には悪いが、比嘉の陰の貢献への感謝の想いが無ければテレビ・ニュースはどうでもよかった。コメントは予想が付くし、店の映像は知り尽くしている。 危なっかしい運転は、妻と俺は「そういう関係」なんだろうか?という書生のような問いに支配されていた。勘違いを質せずに来た高志の半生に居座る青臭さ、妻が「専務の永遠のマドンナ」だという亜希の話に驚いている自身の感受性の弛緩。それらは亜希が言う通り相互依存の変異種だ。 最も身近に暮した存在への観察眼や理解力に欠ける若輩者が、天下国家を論じた若い時期を送り、社会運動に関与しそれも中心を担ってしまい、人の生活を左右してしまう経営を背負うとは・・・。 けれども、知者や治者や覇者にその無謀を嘲笑わせたくはない。 高志に「奪った感」や負い目があったとして、それはある面「可愛いわね」と片付け得る要素や、書生っぽい誠実や、甘ちゃんの罪のない無理解だと言えなくはない。けれど、抜けているのは玲子の側の選択、その自律自立への無理解だ。そうした在り様は、実のところ厄介な団塊どもの限界だったし、俺たちの危うさのや欠陥の根本と繋がっていると裕一郎は思う。団塊、厄介、限界ってか? 人のことはこのように思えもするのに・・・。 専務を卒業、・・・か。上手いこと言うな亜希。それが必要なのか、そもそも高志との間に亜希が言うほどの卒業すべき課題があるのか、そこは自覚できない。しかし、裕一郎が「バカだなぁ」や「幼いなぁ」などの感情を、いままで高志に抱いたことがなかったのは事実だ。亜希、君は聡明で美しい。
 黒川宅に戻ると、食堂でユウくんがはしゃいでいる。 「北嶋さん、お寿司が来るよ」 「ギャラリーの完成祝いかな」 「違うよ。」 「何かな?」 「いいことだよ」 チャイムがなって黒川が大きな寿司桶を抱えてやって来た。 「ギャラリーの完成も目出度いが、もっと目出度いことなんだ」 「何です?」 「ぼくが大人になったんだよ」とユウくんが誇らしく言う。 「ひろしの誕生日なんだよ」 「おうおう、そうかユウくん。おめでとう。いくつになった?」 「ひろしは二十歳になったんだ」 黒川さん。黒川裕、ユウくんこそは、貴方がひと度は「そういう関係」だった人との間に生まれた命なんですよね。 三人でわしたニュースを観た。想像通りの内容だったが、黒川は「比嘉君にお礼を言わなきゃな」と上機嫌。ユウくんも「わあ、チチのギャラリだ」と見入っていた。 亜希に諭されたと言うべき今朝からの今日一日が、とりわけ亜希が泊港の待合で語ったことが、ユウくんの母親美枝子を含む身近な女たちを強く想わせ、黒川の生母探し調査費のことを認めるよう心を押している気がしていた。 食卓に並んだ寿司を前に、おめでとうを言って乾杯して・・・、と思って腰掛けた時、またチャイムが鳴った。 出た黒川と宅配業者が言い合っている。玄関に行くと、黒川が受取拒否を通告していた。
黒川宅に戻ると、食堂でユウくんがはしゃいでいる。 「北嶋さん、お寿司が来るよ」 「ギャラリーの完成祝いかな」 「違うよ。」 「何かな?」 「いいことだよ」 チャイムがなって黒川が大きな寿司桶を抱えてやって来た。 「ギャラリーの完成も目出度いが、もっと目出度いことなんだ」 「何です?」 「ぼくが大人になったんだよ」とユウくんが誇らしく言う。 「ひろしの誕生日なんだよ」 「おうおう、そうかユウくん。おめでとう。いくつになった?」 「ひろしは二十歳になったんだ」 黒川さん。黒川裕、ユウくんこそは、貴方がひと度は「そういう関係」だった人との間に生まれた命なんですよね。 三人でわしたニュースを観た。想像通りの内容だったが、黒川は「比嘉君にお礼を言わなきゃな」と上機嫌。ユウくんも「わあ、チチのギャラリだ」と見入っていた。 亜希に諭されたと言うべき今朝からの今日一日が、とりわけ亜希が泊港の待合で語ったことが、ユウくんの母親美枝子を含む身近な女たちを強く想わせ、黒川の生母探し調査費のことを認めるよう心を押している気がしていた。 食卓に並んだ寿司を前に、おめでとうを言って乾杯して・・・、と思って腰掛けた時、またチャイムが鳴った。 出た黒川と宅配業者が言い合っている。玄関に行くと、黒川が受取拒否を通告していた。 すぐに分かった。美枝子からユウくんへの二十歳の誕生日祝いの品だ。 「止めなさい! 黒川さん、貴方に受取拒否する権利はありません」 「話は逆だ。居候の身の君に、ぼくへの荷の受取拒否を阻止する権利は無いんだ!」 「あなたへの荷? ほら、この荷物の宛名は黒川裕です。黒川自然ではありません。横暴だ」 「ぼくは親権者だ」 「黒川さん、ダメです。今日ユウくんは二十歳になったんでしょ。止めなさい。受け取らせて下さい。 美枝子さんからのプレゼントじゃないですか!」 強引にサインして、配達員から受け取った包をユウくんに手渡した。 こらっジジイ! 誰が居候やねん? そう言いそうになった。
すぐに分かった。美枝子からユウくんへの二十歳の誕生日祝いの品だ。 「止めなさい! 黒川さん、貴方に受取拒否する権利はありません」 「話は逆だ。居候の身の君に、ぼくへの荷の受取拒否を阻止する権利は無いんだ!」 「あなたへの荷? ほら、この荷物の宛名は黒川裕です。黒川自然ではありません。横暴だ」 「ぼくは親権者だ」 「黒川さん、ダメです。今日ユウくんは二十歳になったんでしょ。止めなさい。受け取らせて下さい。 美枝子さんからのプレゼントじゃないですか!」 強引にサインして、配達員から受け取った包をユウくんに手渡した。 こらっジジイ! 誰が居候やねん? そう言いそうになった。
連載 70: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (6)
七、 しらゆり⑥
予定通りワックス掛けを終え、夕方の便に乗る亜希を送って泊港へ車を走らせた。 「聞きそびれたが、あの時みんなで笑ってたの何? 黒川さん又何か言うたかな」 「ナイショ」 「教えてよ」 「ちょっと笑えないんだけど、黒川さんが面白おかしく言うから・・・」 「何て?」 「亜希君と北嶋君が実際のところどうかなのかは、当人たちだけが知っている。ヒロちゃん、そういうことなんだよ男女ってのは、だって。それから、ぼくはもうセックスは出来ないから、永遠の入口だと思うかい?実はぜんぜん違うんだよ、だって」 「松下さん、ぼくら、朝方、あそこで引き返して良かったよな。」 「すみません」 「謝るなよ」 携帯電話が鳴った「裕一郎、今どこに居る?」。比嘉からだ。泊港へ向かう途中だと答えると、「すぐ帰れ! 6時までに帰れ」と言う。ん、何だ? 「6時からテレビ視ろ。6時からの、わしたニュースやぞ」 比嘉が何かの取材を受けて出ているのだろうか。 「何です?」 「観りゃ分かる。ジイさんにも見せてやれや」 なるほど、そうか。ギャラリーじねんがローカル・ニュースに出るのだ。比嘉がそこまで手を回していようとは驚きだ。分かりましたと答え駐車場に入った。 亜希に電話の中身を説明すると「どうしてそこまで・・・」と言って、「黒川さん、北嶋さん、比嘉さんの熱い友情と言うか、腐れ縁と言うか、永遠の入口みたいなことかな」と言って笑った。 さっき黒川が言った永遠の入口は男女の「そういう関係」の話だったが、似たようなところがあるのかもしれないと、裕一郎は先輩二人との時間を想うのだった。
高速艇の発時刻まで30分ある。6時前に黒川宅着なら艇が出るまで居ても大丈夫。待合のベンチに座り、争議のとき占拠中の社屋内の倉庫を比嘉に製作工房として貸したこと、それは高志もいっしょに進めたこと、ずっと後年黒川は裕一郎が持ち込んだ比嘉の作品を扱って来たこと、先日ユウくんを比嘉のアトリエに連れて行ったこと、比嘉から聞いた「他者を迫害することなく生きてゆく権利」の話、比嘉が新聞社にギャラリーじねんの記事をねじ込んでくれたいきさつ、などなどをダイジェストで話した。 亜希は、「ああ、沖縄だぁ」そう言って「北嶋さん、黒川さんっていいこと言いますね『永遠の入口』!」と繋いだ。 沖縄と黒川発言がどう結びつくのかよく解からない。だが、亜希の中で、いまそれが結び付いたのだ。そう思うと、黒川の例の「調査」も含め全てがひとつになって迫って来る。裕一郎はそう感じていた。
艇の時間が近付いている。亜希が、「何回か送ったり送られたり・・・。駅や港でのこれ、中島みゆきの歌の気分にちょっと似ていて、これって嫌いじゃありません。もちろん、みゆきさんの突っ張った恋やしんどい別れではないのですが・・・」と笑った。大阪での最終電車の駅、渡嘉敷港、今日の泊港。たぶん三度だけなのだが、亜希との「別れの気分」は裕一郎とて嫌いではないのだ。 亜希が、どこかぎこちなく言いそびれたことを付け加えるように言う。 「北嶋さん、私もそうですけど、北嶋さんも専務を卒業しないと・・・ですね。失礼」 「えっ、高志? 何で?」 「私もたぶん北嶋さんも、あの時、専務のことが頭を過ぎったのだと思います」 「そうか・・・。で、君は卒業できたのか?」 「たぶん。今朝、明け方、霧雨の中で卒業しました」 亜希が泣いているように思いたかった。男を拒否できたことが高志を卒業だとは、分かる気がしないでもない。亜希の人生に貢献できたのかと苦笑して納得した。そして、親子以上の年齢差ある者を誠実に人として扱う彼女の「親切」は、ある種の高齢者介護でもあるに違いないと気付いた。 泣きそうなのはこっちだった。拒否ではなく制止だ、制止してくれたのだ。 近く工房を去ると言う我が子より若い女性に、自らも間もなく大阪に帰ろうとする初老男が、どんな関係を提示できたと言うのだ。 「ひとつ、訊いていいですか? 専務は奥さんを北嶋さんから奪ったんですって?」 「いいやぜんぜん違う」 「北嶋さんと奥さんが待ち合わせているところへ出交わし、そのまま奪ったと・・・」 「え~っ?誤解や。ぼくは、てっきり高志と玲子が待ち合わせてたと思ってた。違うのか?」 「黒川さんの送別会の夜、居酒屋で専務との歴史を聞かせてもらった時、そう聞きましたよね。あれ~?と思ったんですけど、別にどうでもいいことなので言わなかったんですけど」 裕一郎は、高志の幼い思い違いに苦笑しながら、その幼さを嘲笑うのではなく、身を引き締めて受け止めようと思った。高志、お前も俺同様ガキだな。浮んだ大学前駅の鮮やかな記憶画像を、高志目線のアングルで再現して見せてやりたいと思った。 当時玲子は髪が長くて紺のジーンズ姿。駅舎の庇を支える鉄柱にもたれて文庫本を読んでいた。裕一郎が声を発するのとほとんど同時に、後ろから来た高志が声をかけたのだ。ほら、俺が「誰かと待ち合わせか?」と声をかけているだろう? 高志、俺は玲子と待ち合わせてたんじゃないよ、バカだなぁ~。裕一郎は、高志に対してたぶん初めて「バカだなあ」と思ったのだった。
連載 69: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (5)
七、 しらゆり⑤
ギャラリーじねんに着くとヒロちゃんが居て驚いた。昨日休みだったヒロちゃんは、昨日中にフェリーで本島に来ていたのだった。弟が訪ねて来たらしい。大空は仕事上の急用で来れないという。黒川がそう言った。 ヒロちゃんは黒川の指示で梱包を解いていた。物によっては大きくて木組み梱包されている。開梱作業は楽ではない。黒川が汗掻いてバールを使ってこじ開けているが、どうにも危なっかしい。ヒロちゃんが、中のエアーパッキンに包まれた品物を丁寧に出している。裕一郎の出番だ。 「おはよう、早くから始めたんですね」と言ったが、ヒロちゃんは睨み返して無言だ。 黒川が「朝帰りかい? ぼくの予感は的中だな。」と笑ったが、ヒロちゃんの表情はさらに強張っている。その場の空気に気圧されて何か言い返すこともできずに亜希に目をやると、亜希は平然としていた。 「昨夜、沖縄に来ている大阪時代の部下たちに会ってたんです。北嶋さんと共通の知人なんでご一緒に・・・朝まで・・・。ちょっと呑み過ぎました」 「そうかい、まっ手伝ってくれたまえ」 ヒロちゃんは変わらず憮然としている。 亜希が黒川に尋ねながら陳列にかかり、裕一郎は開梱作業を始めた。亜希の方へ行って大皿の配置を指示している黒川を見やって、ヒロちゃんが小さな声で口を開いた。 「北嶋さん、わたしも国際通りで呑んでたんよ。そしたら雨が降り出した頃、北嶋さんと亜希さん見かけたよ」 「そう。偶然やな。見かけたのなら声かけてくれたら良かったのに」 「よう言うよ。北嶋さんデレーっとしてて邪魔せんといてくれ臭振り撒いてたもん。雨の中、店のテントの下でカップルやったでぇ」 「いやー、大阪の連中朝が早いからと引上げたんで、松下さんと二人で呑み直したんや」 「ほら、みんなで呑んだんとちゃうやん」 気が付くと隣に黒川が立っていてまずいと思った。黒川とヒロちゃんのバトルになるのか・・・。と、やはり黒川が言い出した。 「ヒロくん、つまり君は二人がそういう関係だと言いたいんだね」 「そんなこと言うてませ~ん。わたしは北嶋さんが嬉しそうやったと言うてるだけや。大体、そういう関係って何やねん?」 「あのね。男がいる、ある女が気になっている。人柄や内面もそうだが、言動や外面も好きだ。女がいる、その男と同じような気持ちで居る。それがそういう関係の入口だ」 「はあ? なんやねん、ジイさんの恋愛論かいな。入口を入ったらどこ?」 「そりゃセックスを含む男女の関係だろうね。その先へはこの人以外ではダメなんだという、人に説明できない感情?執着?こだわり?、それが必要だがね」 「元奥さんはそれなん? だったらなんで別れたんよ」 「出て行ったのはあいつだ、ぼくじゃない。本人に訊いてくれ!」 大皿を設置している亜希は聞かぬ振りをしていたが、聞いていたに違いない。黒川が会話に使った「そういう関係」というのは、昨夜、いや明け方聞いた単語だ。
朝方バーを出ると、上がりかけた雨が霧のようになって細くかすかに降っていた。店の前から少し離れた角に在る、ゆっくり点滅する看板の下で亜希を引き寄せ、背に腕を回した。顔を寄せる裕一郎に、亜希が小さく「あッ」と声を発し、そして「北嶋さん、私たち・・・」と言いかけたと思う。続きを言おうとするそのくちびるを唇で塞いでいた。夢のシーンを再現しているような浮遊感に泳いだまま、亜希を支え抱えるようにして歩いた。二人は無言だった。 目的の建物の前まで来たところで亜希が言った。 「北嶋さん、私たちはそういう関係ではないですよね」 即答する気は無かったのに、「・・・。そうやな、違うと思う」と答えた。 一呼吸置いて、亜希が返そうとする。その間合いが永く思えた。裕一郎もその僅かの時間に多くのことを考えたのだ。「いや、そういう関係にしよう」と言えばどうなのか。あるいは無言で強引に入って行こうとすればどうなんだ、と。言葉を呑んで発するに至らない亜希の向こうに高志を見たのだ。いや高志ではなく、増幅して言えば男との関係を掴みあぐねて立ち尽くす魂を見たのだ。亜希が返した。 「私もそう思います」 肩に回していた腕を放し、ホテルの前からUターンしたのだ。放した腕がネオンに照らされて赤くなったり青くなったりしていて滑稽だった。 並んで歩いた。霧状の夜がゆっくりと明けて行く。 「私、大胆に恥かしさを棄てて言いますよ」 「ええよ、言うてみて」 「北嶋さんが、永く独りで暮していて女の人を欲しいと思う時があるように、私だって好意を抱く男に強く抱きしめられたいと思ったり、男の肌の温もりを恋しく思ったりする生々しい人間です。私もう三十ですよ。・・・ああ、こんなこと言えなかったのに北嶋さんには言えるんです。」 「聞かせてもらいますよ」 「今ここで北嶋さんにもたれては、知る人の無い沖縄へ独り来た意味が崩れると言うか・・・」
我に返ると、黒川とヒロちゃんが笑っていた。亜希も一緒に会話に入ったのか笑っている。 どういう会話が交わされたのか、聞きそびれた。聞いてみたい。 店頭と店内にはオープン祝いの花が、奮発したのだろう比嘉からの豪華なものをはじめいくつもある。亜希がその花たちを配置した。いくつかは、黒川の指示で巧みに商品を活用してある。花と商品を同時に活かすわけか。その中で、花の一時的な勢いに負けるはずのない大皿がひと際力強い。 黒川宅にあったのを持ち込んだ衝立の裏に配置した事務机に、新聞が読みかけ状態で置いてあった。 手に取ると文化面にギャラリーじねんが出ていた。黒川が寄って来て「まあまあの記事ではあるな」と黒川流の比嘉への感謝を表現する。こき下ろさないのが最大の評価であり感謝なのだ。記事は、店内を背景に黒川が写っているカラー写真付きのもので、取材の時に聞かされたコピーのままだった。「陶芸を通じた、沖縄とヤマトの交流、相互発信の砦」と見出しがあり、紹介記事は「大いに期待される」と結んであった。新聞で見る黒川は一段と学者っぽく絵になるから不思議だ。
黒川宅にあったのを持ち込んだ衝立の裏に配置した事務机に、新聞が読みかけ状態で置いてあった。 手に取ると文化面にギャラリーじねんが出ていた。黒川が寄って来て「まあまあの記事ではあるな」と黒川流の比嘉への感謝を表現する。こき下ろさないのが最大の評価であり感謝なのだ。記事は、店内を背景に黒川が写っているカラー写真付きのもので、取材の時に聞かされたコピーのままだった。「陶芸を通じた、沖縄とヤマトの交流、相互発信の砦」と見出しがあり、紹介記事は「大いに期待される」と結んであった。新聞で見る黒川は一段と学者っぽく絵になるから不思議だ。
連載 68: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (4)
七、 しらゆり④
県庁前の舗道は朝靄に包まれていた。 前夜の雨が上がっても、今にも再び降り出しそうな雲行きだった。明日のオープンに向けてギャラリーじねんに十一時に集合だ。大空とヒロちゃんは一〇時の便で来るだろう。昨夜届いているはずの黒川自慢の十数点の陳列をして、店内最終清掃と床ワックスを夕刻までに済ませることになっている。 裕一郎はモーニング食うか?と独り言のように言って、ギャラリーじねん近くの喫茶店に向かって亜希と歩いた。途中すれ違う勤め人は、大阪とは違ってあくせく歩いてはいないように思えた。喫茶店の斜め向かいの公園入口の門柱が目に入った。そこに座るシーサーのせいだ。彼が、前夜の雨で濡らした身体そのままにこちらを睨んでいる。その視線が何故か気になった。それは責めているというより、嘲笑っている又は呆れている、に近いものだった。
昨夜、亜希は「分からないんです」と言った。オレだっていまだに何も分からないのだ。人が持っているよく働きたいという誠実に近い勤勉が、評価や報酬を得たいという欲を抱えていようと、異性に対する共感や情愛が性的な欲望と区別できないとしても、それは当然だと思う。ただ「分からない」のだ。その狭間の不可思議な感情の立ち位置にあるはずの「そうではない」ものを定位させる方法が・・・。分からないから、いい歳をして上滑ってしまうのだ。裕一郎はシーサーに向かって黙応していた。 裕一郎は昔、高校を卒業してすぐ就職したのだが、普通校だったので商業系の珠算・簿記はもちろん工業系の技術も全く無く、接客のイロハも知らず勤務先で難儀した。最初勤めた企業では経理総務に配属されたのだが、何の戦力にもなっていない実態を誰よりも自身が痛感していた。次々質問して、自ら「仕事」を見つけるべきなのだが、それが出来ない。何を質問すればいいのかさえ分かっていないのだ。胃痛と下痢を繰り返し、一ヶ月で失意の退職となった。引き金は「あの**高校卒だから優秀だと思っていたのにな」という課長と係長のヒソヒソ会話が聞こえたことだった。続いて勤めた小さな個人経営の物販店では店番をした。のだが、雑然とした倉庫まがいの店内を片付けようとは思いながら、商品知識が乏しい上に店の親方と奥さんが使い慣れた商品の配置を勝手に並べ替える訳にも行かず、手を出さなかった。片付けたいのに、何から何処からどういう風にすればよろしいでしょうか?と問う、それが出来ない。若い奥さんの「ボーッとしてる時間があるんやったら、少しぐらい片付けたらどうなん?」との叱責に言い返して退職となった。北海道に行き、いや逃げ、パチンコ屋に住み込んだのだ。
考えて見れば、気が利かず世間知らずの自分がダメなのだが、企業内教育機能など無縁な職場の貧困が根本理由だろう。けれど、働くに際して持っておくべき基本的な、知力・体力・知識・技術以前の、学者が「人間力」などと語る内容に欠けていたことは疑いない。早くから職業選択を前提にした進学先を選ばせるドイツやイギリスの教育制度の歪みや弊害が言われていると聞いたが、誰もが同じように高校大学へ押し出され、同じ価値観・就労観をばら撒く教育がいいとも思えない。 世に在る分かりたいのに分からないことの多くは、こうした構造の中に雑在している。仕事や大人の恋愛を持ち出すまでもなく、例えば学生のクラブ活動や幼い恋愛にだってそれは在る。しかし、人はやがて分かるのだ。分からないことを分かって行く方法を・・・。
裕一郎は自身の古い幼い恋物語を思い起こしていた。 分からなかったのだ、オレも彼女も・・・。互いに相手に対して誠実であろうとしていたに違いないのに・・・、そして終ったのだ。 では、女房との数十年の生活と、今離れている事態はどうなんだ、分からないままの還暦か。 そして亜希との昨夜は何なのだ?
連載 67: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (3)
七、 しらゆり③
「絵葉書にあった『ひと夜秘め』の相手は北嶋さんなんでしょ?って訊いてたんです。亜希さんコクらないんですヨ。北嶋さん、答えてよ」 「絶対に違うし、ぼくもあの葉書見たけど君らが言うような芸能ニュース的事件じゃないような気がするな。『ありや?』という反語、苦い自問やろ?」 彼女らの興味本位にも聞こえる謎解き談義には、行き先を告げず去った上司への信頼や親愛が感じられて不快ではなかった。共に働いた時間の関係性が見えて羨ましいほどだ。 翌日は早朝からレンタカーで各地を回るという二人が「北嶋さんまだぜんぜん飲んでないし、どうぞ残って下さい」と引上げた。予期しない展開で誕生日の約束を果たせる。
おめでとうと言うと「忘れてて、さっき思い出したんでしょ」と言い当てられた。亜希が言う。 「どこかで聞いたんですが、誕生日は本人への祝いの日ではなく、実は感謝の日なんですって。自分を世に産み出してくれた母への・・・。亡くなった母には、普通ではない形で私を産んだことへの感謝を一度も言えなかったので、最近は毎年それをこの日に想うことにしてます」 いつか「母の轍は踏むまいと思って来たんです」と聞かされたし、先日ヒロちゃんが亜希誕生にまつわる人間関係を語るのを聞いた。今その詳細を訊こうとは思わない。 「姉や兄とは、父親が違うんです」 いろいろ想像したが、なお黙っていた。どうであれ、亜希の母親が亜希を産むことにした経過とその後の辛酸は尋常ではなかっただろう。今、亜希が感謝を想えるのなら、その心情が向かう先に在るものが母性というものの原点なのかもしれないと思う。裕一郎は、ユウくんの母親美枝子のことを考えていた。 そして、何故だろう『身捨つるほどの』と心つぶやいていた。 「この泡盛、しらゆり、母親が好きだったんです」 テーブルに控えめにしかし堂々と立っている泡盛の瓶を眺め亜希がポツリと言う。 「誕生日ですからこれ呑んでるんです。母が好きだったこれを・・・」 乾杯を繰り返し、近々黒川の許を去ることを伝えると、亜希も夏が過ぎれば以前居た団体に戻ると告げた。
店を出て歩き始めると、薄くなった髪のせいか落ちてくる雨を敏感に感じる。 「雨やな」 「そう? 降って来た?」 人は我が身の心身の状況によって事態把握に差があるものだ。 路地から国際通りへ出て、何処へ向かうでもなく歩いた。 「分からないんです」 「何が?」 「仕事の意味と言えば堅苦しいんですが、どうやれば身も心も震えるようなことに出遭えるのかとか、それに近いものを感じかけてもそれを上手く表現したり空回らずに行なうのは難しいなぁ・・・とか。これ、男女関係もそうでしょ?」 「黒川さんが、ぼくの人生は祭りだと言ってたんやが、祭りというのは非日常だからいつも祭りというわけには行きませんよねと突っ込んだ。あの人、祭りの終わりを納得できず駄々こねるガキみたいなところがあるやろ」 ![P014118486_238[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/10/P014118486_23811.jpg) 「黒川さん何て?」 「毎日が祭りであるような方法はあるんだ、やて」 「どんな方法?」 「言うてくれんかった」 「仕事に祭りを持ち込まれては、周りが迷惑でしょうね。男女関係も・・・」 「迷惑かけずに、身も心も震えたいよな・・・」 「北嶋さん、大阪へ帰ったらどうなさるの? 仕事」 「あ、降って来たね。あかん、強うなるでこれ。仕事? 何とかなるよ」 人波も絶えて閉じた通りの店先軒に雨宿りするように立ち止まると、すぐに本降りになった。 「松下さん、後輩が泊まってる宿に泊るの?どういう予定?」 「そのつもりだったけど、彼女ら誤解して気遣ったみたい。面倒くさいからそのまま流れに乗ってやった」 「黒川邸に来る?」 「大空さんから明日はオープン前日だから行くように言われてます。ちょうどいいけど、今夜は朝までお酒でもお茶でもいいですよ。雨宿り?」 「了解」 雨の中を歩くにはちょっと遠いが、まあ近いバーに濡れて駆け込んだ。
「黒川さん何て?」 「毎日が祭りであるような方法はあるんだ、やて」 「どんな方法?」 「言うてくれんかった」 「仕事に祭りを持ち込まれては、周りが迷惑でしょうね。男女関係も・・・」 「迷惑かけずに、身も心も震えたいよな・・・」 「北嶋さん、大阪へ帰ったらどうなさるの? 仕事」 「あ、降って来たね。あかん、強うなるでこれ。仕事? 何とかなるよ」 人波も絶えて閉じた通りの店先軒に雨宿りするように立ち止まると、すぐに本降りになった。 「松下さん、後輩が泊まってる宿に泊るの?どういう予定?」 「そのつもりだったけど、彼女ら誤解して気遣ったみたい。面倒くさいからそのまま流れに乗ってやった」 「黒川邸に来る?」 「大空さんから明日はオープン前日だから行くように言われてます。ちょうどいいけど、今夜は朝までお酒でもお茶でもいいですよ。雨宿り?」 「了解」 雨の中を歩くにはちょっと遠いが、まあ近いバーに濡れて駆け込んだ。
連載 66: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (2)
七、 しらゆり②
この看板屋は大阪のノザキのオヤジに電話して業界ルートで紹介してもらった看板屋だ。破格値で引き受けてもらったこともあり、施工後すぐに振り込むと黒川が約束していた先だ。それが事前連絡もなく半額しか振込まれていない。看板屋としては、問い質して当然だ。ましてノザキの紹介でもあり、裕一郎としても不義理はできない。数日前、銀行へ強制連行して振込ませたのだ。半額とはどういうことだ! 「そうギャーギャー言いなさんな。原価には届いているだろう?」 約束をたがえた側が偉そうに言っている。原価に届くかどうかは関係ない。材料費・フィルムシートの加工費・高所に上っての二人一日の人権費・交通費・諸経費、裕一郎から見ても間違いなく格安だった。全額、約束通り支払うべきだ、支払わねばならない。オレも困るし・・・。 裕一郎は言い返す黒川の言い草に苛られて、「あんたね、ぼくの顔に泥塗るんですか? 支払えるじゃないですか!」と声を荒げた。携帯電話を手で塞いで黒川が小さな声で言う。 「持ち金が厳しい。運転資金と生活費に取って置くんだよ!」 黒川は、すぐ「月末に残りを払うよ! 必ず払う。逃げやせん」と言い放って電話を切った。
看板屋への無作法は論外として、運転資金と生活費というのが解からない。 「黒川さん、当分の金はあるじゃないですか!」 「いや、二ヶ月分しかないんだ」 「えっ! どういうことですか」 「少し余裕が出来たので、未払いの金を払った。この先も調査を続けてもらわなないとならんのでね」 「調査? 何の?」 「一身上の大事な調査だ」 「聞いてませんよ! いくら払ったんです?」 「三十五万だ」 「そんな大金を払う調査って一体何なんです? ぼくには訊く権利があります。約束の報酬もまだ貰ってない。それは譲るとしても、当面の運転資金にとやっとのことで確保した金。いわば共同運営者、当然何の相談もなく金を動かすのは信義即違反です。誰の何の調査です? 支払先は何処の何という会社です。」 「調査機関だ」 「だから、何処の何という?」 「君に言う筋合いはない。」 「黒川さん、ええかげんにしてくれや! 余裕資金じゃないんですよ。看板屋への支払いは約束通りしていただきます。それと、ぼくへの給与。即刻払って下さい」 「いいよ、払ってやろうじゃないか。残金がゼロになっても、ひろしが腹を空かして泣いても看板屋と君の給与が優先だ。明日にでも払おう」 「黒川さん、何の調査なんです? 言いなさい!」 「言いたくない。もう間もなく結論が出るところまで来ているんだ。相当絞り込んでいる。手付けの五万を半年前に払っただけなんだ。調査の女性はよくやってくれている。報いなければならないし、今後のこともある」 「何のことです?」 「この話は終わりだ。さあ、そこの梱包開けてくれないか。有田の作家の焼物だ」 「はいはい開けますよ。黒川さん、来週、店のオープンを見届けたらぼくは去りますからね。もう貴方には何を言っても通じないことがハッキリしましたから。看板屋への支払いは、明日ぼくが振込ませてもらってもいいですか?」 「通帳は渡さないよ。大丈夫、明日するから」 「絶対ですよ」 「くどい!」 「ぼくの給与は、去るまでに頼みますよ」 そうは言ったものの、「ギャラリーじねん」の多少はあるだろうオープンご祝儀の売上がある間に確保しなければ永久に取れないだろうと裕一郎は思うのだった。 調査? このジジイの物事の優先順位、処理手順、思考回路・・・、解からない。![IMG_3697[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_36971.jpg) 黒川が先夜言っていた生母の話が事実なら、彼が言う調査は「母探し」だと思う。しかし、最初に費用を払ったのが半年前、黒川生後約八十年、戦後六十年・・・、判るのだろうか。生母はヤマトと絶縁して戦後を生きただろうに。 思い出した。黒川の妻美枝子は「沖縄移住を決めた直前に女性から電話があって」と言っていた。半年前に費用の一部支払い。話は符号している。
黒川が先夜言っていた生母の話が事実なら、彼が言う調査は「母探し」だと思う。しかし、最初に費用を払ったのが半年前、黒川生後約八十年、戦後六十年・・・、判るのだろうか。生母はヤマトと絶縁して戦後を生きただろうに。 思い出した。黒川の妻美枝子は「沖縄移住を決めた直前に女性から電話があって」と言っていた。半年前に費用の一部支払い。話は符号している。
夜、助けを求めるような心境に駆られて亜希に電話した。大阪の元部下が二人沖縄に来ているので、早仕舞いさせてもらって今那覇に居る。呑み食いしているので出て来ます?とのこと。もちろん、と返事して思い出した。今日は水曜日。しまった、亜希の誕生日だった。憶えていたことにしておこう。 裕一郎もよく知っている元部下の女性二人とワイワイやっていた。二人は大きな現場をやり終えて休暇を取って沖縄旅行ということらしい。 「北島さ~ん、お久し振り。沖縄まで亜希さん追っかけて来たんですかあ~?」 「相当呑んでるみたいやね」 テーブルには「しらゆり」がど~んと置いてある。 この泡盛は石垣のもので、独特の癖というか風味がある。以前大阪で「畳の匂いがするな」と言ってしまって「せめて井草の匂いと言いなさいよ」と亜希にたしなめられた酒だ。実際、数回呑むと癖になり、裕一郎も好みの泡盛なのだ。 亜希はその味わいの虜になったと言っていた。癖になっているのだろうか・・・?
連載 65: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (1)
七、 しらゆり①
「ギャラリー・じねん」のオープンの日が迫っている。 黒川宅から店で使える家具備品を運び込み看板の取付も終え、印刷用に写真撮影をした。ついでに表で黒川を立たせ記念写真を撮った。特急でDMを作り、黒川の名簿で五百、大空が自分の名簿で二百、カウンターバーのオーナーが二百、比嘉が三百、食堂のオバサン・ひかり園・他で三百、それぞれ名簿を提供してくれ、計千五百人宛に発送した。 宛名書きは、亜希・ヒロちゃん・洋子さんたち「手作工房おおぞら」組がほとんどやってくれた。
黒川と二人で焼物・陶芸作品を並べていると、比嘉が押し込んでセットした琉球弧タイムスの記者とカメラマンが昼前にやって来て、インタヴュー取材と撮影をした。何故かビデオ・カメラも回している。黒川は有名人にでもなったような気分らしく、新聞社に対してもどこか横柄なのだ。が、そこは文化部、心得たもので「陶芸を通じた、沖縄とヤマトの交流、相互発信の砦」などと煽てている。オープン前日の朝刊にカラー写真付きで載せるという。黒川はいつも以上にハイテンションだった。 それには別の理由もある。 海へ行った翌日から、ヒモ付き金=苦労してせっかく回収したのに支払い義務のある百六十六万=預った時の言い値は二百万近いという額を、平伏して減額依頼して完済していた。加えて、沖縄の未回収の残り二件、ヒモ付きではない計六十七万は裕一郎が三日前に回収したし、黒川が身勝手にも高志に依頼したという大阪の未回収金、芦屋の自称資産家のマダムの七十五万と大阪の教師夫婦の三十万計百五万も、回収に走ってくれた高志から数日前に全額振込まれたのだ。高志は、回収するに当たって交通費や経費だけでなく時間を作って出かけた手間もあっただろうが、満額振込んで来たのだ。黒川はこういう高志らしい対応を承知して読み切った上で依頼したのだ。ジジイめ! これで、僅かだが支払った大空以外の改装費用を支払っても、しばらくの黒川親子の生活維持と店運営は大丈夫だ。![0fb10a22dec61bdb0eed312802c9e4051[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/09/0fb10a22dec61bdb0eed312802c9e405111.jpg)
振込みがあった日の翌々日、裕一郎は高志からの手紙を受け取っていた。 「債権の回収自体のことはいいのだ。ただ、それほど金策に難渋しているのであれば、ギャラリー開設してもその後の運営は大変だなと危惧する。自宅ギャラリーに足を運ばなかった客が、ギャラリーにはやって来るというのが解せない。黒川氏は分かった上で玉砕する気なんじゃないのか? お前が巻き込まれ、無償ボランティアどころか持ち出し状態になりそうで気になる。お前の撤退を早期に実現し、黒川氏がいつでも閉められる道・方策を用意しておいてやるというのが、それなりの人生経験を持つ者の誠意ではないか? 黒川氏を手伝うと聞いた時に止めもしなかったぼくが言えた義理ではないのだが・・・。」 「追伸:風の便りに松下君が沖縄に居ると聞いた。もし遭うことがあればよろしく伝えてくれ」 亜希が渡嘉敷島の工房件民芸店に居ること、黒川氏が作品を扱っていた知念太陽、知ってるよなお前も作品を所有している太陽、その甥がそこの主であること、亜希にはその関係ですでに会ったことなどだけを、簡潔に書いて手紙で返事したのだった。
手を携えて「渡し」を超えた黒川と美枝子、そうは出来なかったあるいはしなかった高志と亜希。二組の男女が採ったそれぞれの道が目の前に見えている。その明暗・破綻・悔恨・惜情・未練・・・・、そうなのだ人間はそう強くは出来てはいない。とりわけ男女間の関係や感情や、生活とか生業という厄介で本質の一部に確実に組み込まれている事柄の総体は、結局は人が生きることを描いた透かし絵の裏表なのだ。だから、強くは出来ていないのだが弱いばかりでもない。したたかでしつこく、ピュアであったり淡々としていたりもする。激情に駆られたり、成り行き任せだったり、無私の奉仕だったり・・・。その透かし絵は、それぞれの人の命の時間と同じ長さを生きるのだ。たとえ、その人が自ら命を絶ったとしても・・・。 裕一郎は、記者の取材と撮影をよそに、ぼんやりして窓際に立って、目の前の県道を走る車が轍でバウンドして上げる音を聞いていた。「オレは、黒川にはなれない。高志になれそうにもない」、そう思った。先のことや、オレにとって亜希とは何なのか、亜希にとってオレは何なのかなどはもちろん、高志への微妙な感情の深層の正体も表面的な感情も整理がつかずにいた。
記者が引き上げてすぐ、携帯電話に看板屋から抗議の電話があった。 慌てて黒川に代わった。
連載 64: 『じねん 傘寿の祭り』 六、 ゴーヤ弁当 (10)
六、 ゴーヤ弁当⑩
酷なことを言うなよ。オレと君との距離より、君と学生の距離の方が近いことがよーく解かった。オレは黒川さんの組なんだ。裕一郎はそう言いそうになって溜息をついて、首を振って大きな声で返した。 「ユウくんのクロールに付き合っただけでフラフラや。休憩させてくれや」 亜希は笑って頷いた。 黒川とユウくんがトイレに立っていて一人で居ると、程なくバレーを止めた亜希がパラソルにやって来た。ヒロちゃんは続けている。 ハアーハアッ、と息切れている。 「確か、高校時代バスケット部やったと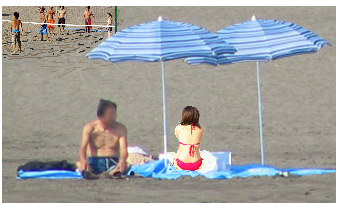 聞いてたけど、アカンか?」 「私も歳ですね。来週三十ですよ。やっぱりヒロちゃんは若いなぁ」 「来週誕生日?」 「ええ」 「おめでとう。いつ?」 「水曜日。おめでたくもありませんが、ちょっと区切りかなあ」 「二人で呑む?」 「そう言ってくれると思ってました。北嶋さんと呑みたいよ」 「連絡するよ」 「はい。」 亜希の水着姿から視線を反らそうとしても、それは視角内に在った。
聞いてたけど、アカンか?」 「私も歳ですね。来週三十ですよ。やっぱりヒロちゃんは若いなぁ」 「来週誕生日?」 「ええ」 「おめでとう。いつ?」 「水曜日。おめでたくもありませんが、ちょっと区切りかなあ」 「二人で呑む?」 「そう言ってくれると思ってました。北嶋さんと呑みたいよ」 「連絡するよ」 「はい。」 亜希の水着姿から視線を反らそうとしても、それは視角内に在った。
戻って来た黒川が上機嫌で言う。 「何だ、やはり亜希くんはヒロくんや学生より、こっちの組かい?」 「はい、悔しいけどそうみたいです、エヘヘ」 「そうかい。じゃあ今後は大人扱いしてあげようね」 「黒川さんに大人扱いされるって、ホント有難く光栄な事です。」 黒川もいっしょにアハハアハハと笑った。 亜希は「ユウくん、私と泳ごうね」と、ユウくんの手を取って海へ小走りに去って行った。二人の背中に黒川が懇願するように言う。「亜希君、弁当にしようよ」「ひろし、すぐ上がって来るんだぞ」、二人が「はーい」と返事していた。 「北嶋君。もう少し若けりゃ、ぼくはあの娘に猛アタックするな。どう?君は」 「どうって、親子以上の年齢差ですよ、あり得ません。そう思っているとしても、こちらの都合だけでことは成りませんよ。あなたと美枝子さんは、そこを超えたんですよね?」 「超え損なったんだよ。結果としては・・・」 穏やかだった入江の浪が少しざわついたように思えた。陽が陰って来ている。
この日をきっかけに、裕一郎は沖縄を去る日まで何度か、せがまれてユウくんを海へ連れて行った。その海行きも含め、親子との距離と関りは最後に黒川から激しく罵られることになるのだ。 裕一郎は、一人では受け止められない黒川の言い分を、我が身の中に鎮めて理解しているだろうか・・・と考えている。 黒川の、叫びのような難癖のような無い物ねだりのようなその言い分を、斥けるほど自分が黒川と違う種類の人間だとは今も思えずにいる。
(六章 ゴーヤ弁当 終。 次回より 七章 しらゆり )