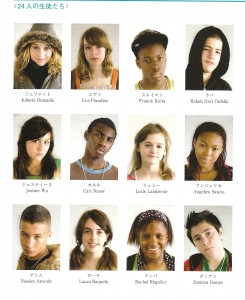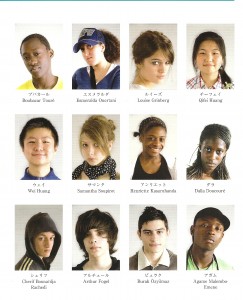Archive for 6月, 2010
通信録: 送られて来た「宣言文」に、 当方は「・・・・・・」
知人からメールが舞い込んだ。 『本日、6月23日慰霊の日に「琉球自治共和国連邦独立宣言」が発せられました。』 とだけ書かれていて、「宣言文」が添付されている。 「宣言文」そのものと、半端な添え書きなど書けなかったのだろう送信者の気持ちが ジワリ 押し寄せてくる。
(画像はクリックで拡大可)**************************************************************************************************************************
琉球自治共和国連邦 独立宣言
2010年、われわれは「琉球自治共和国連邦」として独立を宣言する。現在、日本国土の0.6%しかない沖縄県は米軍基地の74%を押し付けられている。これは明らかな差別である。2009年に民主党党首・鳩山由紀夫氏は「最低でも県外」に基地を移設すると琉球人の前で約束した。政権交代して日本国総理大臣になったが、その約束は本年5月の日米合意で、紙屑のように破り捨てられ、辺野古への新基地建設が決められた。さらに琉球文化圏の徳之島に米軍訓練を移動しようとしている。日本政府は、琉球弧全体を米国に生贄の羊として差し出した。日本政府は自国民である琉球人の生命や平和な生活を切り捨て、米国との同盟関係を選んだのだ。
琉球人は1972年の祖国復帰前から基地の撤去を叫び続けてきたが、今なお米軍基地は琉球人の眼前にある。基地があることによる事件・事故は止むことがない。日本国民にとって米軍の基地問題とは何か?琉球人を犠牲にして、すべての日本人は「日本国の平和と繁栄」を正当化できるのか?われわれの意思や民族としての生きる権利を無視して米軍基地を押し付けることはできない。いまだに米国から自立することができない日本国の配下にあるわれわれ琉球人は、絶えず戦争の脅威におびえ続け、平和に暮らすことができない。
琉球人はいま、日本国から独立を宣言する。奄美諸島、沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島からなる琉球弧の島々は各々が対等な立場で自治共和国連邦を構成する。琉球は三山時代(14C半ば~15C初期)を経て、1429年に琉球王国として統一された。その後1609年、薩摩藩は琉球王国に侵略し、奄美諸島を直轄領とし、琉球王国を間接支配下に置いた。1850年代半ばに琉球王国は米・蘭・仏と修交条約を結んだ。1872年に日本国は琉球王国を一方的に自国の「琉球藩」と位置づけ、自らの命令に従わなかったという理由で1879年、「琉球処分」を行い、「琉球王国」を日本国に併合した。その後、琉球王国の支配者たちは清国に亡命して独立闘争を展開した。日本国に属した期間は1879年から1945年、1972年から2010年までのわずか104年間にすぎない。琉球が独立国であった期間の方がはるかに長いのである。
太平洋の小さな島嶼国をみると、わずか数万の人口にすぎない島々が独立し国連に加盟している。これらの島嶼国は、民族の自立と自存を守るために、一人ひとりの島民が「自治的自覚」を持って独立の道を選んだのである。国際法でも「人民の自己決定権」が保障されている。琉球も日本国から独立できるのは言うまでもない。
これからも日本政府は、「振興開発」という名目で琉球人を金(カネ)で支配し、辺野古をはじめとする基地建設を進めていくだろう。長い歴史と文化、そして豊かな自然を有するわが琉球弧は、民族としての誇り、平和な生活、豊かで美しい自然をカネで売り渡すことは決してしない。平和運動の大先達・阿波根昌鴻は「土地は万年、金は一年」と叫び、米軍と闘った。われわれ琉球人は自らの土地をこれ以上、米軍基地として使わせないために、日本国から独立することを宣言する。そして独立とともに米軍基地を日本国にお返しする。
2010年6月23日 慰霊の日に 呼びかけ人 松島 泰勝 石垣 金星
歌遊泳(歌詞研究): 演歌の向こう側と「切れて」「繋がる」ために ⑤/5
初期中島みゆきにおける「ふるさと」
もちろん、歌謡曲は広く聴かれ歌われることを希い、売れることを前提に作られる。 そこに表れる「言葉」は、時代の「気分」「雰囲気」「大衆的抒情」や、日本近現代の人々の生活感や社会観に居座っている「語」群によって構成されている。言い換えると、たとえ「負」の歴史との「共犯」関係に動員されただろう「言葉」であっても、人々にとって「他に置き換えられない」「言葉」である限り、いまなお生き続けている自明の(説明不要の身に沁み付いた)「言葉」たちによって、構成されるしかない。もちろん曲に乗ることも前提だ。ある意味では、詩や短歌以上の制約を生きている。 その「言葉」が担わされた「共犯」性の痛みを共有しながら、自身の心情をその「言葉」によってしか表せないときがある。作者はその自明の「言葉」を駆使しながら、どうにかして、聞き手が思い描く「それまでの」歴史に培われた自明性を覆し、「共犯」性の「再生産」からは隔たった自身の立ち位置を模索して告げているはずだ。それが、ぼくらに届く歌なのだ。 初期中島みゆきの歌詞には、その模索の痕跡があった。
多用されている「ふるさと」「わかれ」「帰る」「忘れる」を拾ってみる。 「いつか故郷に出会う日を」(『時代』)、「私はわかれを忘れたくて」(『わかれうた』)、「遠いふるさとの歌を歌おう」(『海よ』)、「帰ろう」「急ごう」(『遍路』)、「遠いふるさとは落ちぶれた男の名を、呼んでなどいない」(『あぶな坂』)、「ふるさとへ向かう最終に乗れる人は急ぎなさい、と」(『ホームにて』)・・・・・・。 これらの、「センチメンタリズム」「土着的浪漫」を基礎にした「自明」の「大衆的抒情」「語」を前に、聞き手はそれらが呼び覚ます馴染んだ情感に充たされ、違和感なく受け止めるのだ。 が、やがて下記の歌詞によってその情感の仮解体・再編へと誘われ、いささか「うんざり」もした「大衆的抒情」「語」の多用の先に在る、自明「語」観の変更を迫られることとなる。大きな役割を果たしているのは、もちろん「言葉」を支える曲ではある。 前回述べた『あぶな坂』(http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=53790 )の「ここからは見える」の「ここ」に通底する「場」として、いくつかの歌詞を思い付く。 「若い船乗りの夢の行方を 海よお前は覚えているか」(『海よ』http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=23856) 「死んで行った男たち呼んでるような気がする 生きている奴らの言うことなんか聞かないが」 「浮気女と呼ばれても嫌いな奴には笑えない おかみさんたちよあんたらの方が あこぎな真似をしてるじゃないか」 (『彼女の生き方』 http://www.youtube.com/watch?v=1U43icOLJD4 ) 「別れの気分に味をしめて あなたは私の戸を叩いた」「立ち去る者だけが美しい」(『わかれうた』http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=4951 ) 「包帯のような嘘を見破ることで 学者は世間を見たような気になる」(『世情』http://www.youtube.com/watch?v=fOEOiVAD1-o&feature=related『3年B組金八先生』画像と歌 ) 「叩き続けた窓ガラスの果て」「窓の中では帰りびとが笑う」(『ホームにて』http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=11632 ) 「うなづく私は 帰り道もとうになくしたのを知っている」(『遍路』http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=41420) 「泳ごうとして 泳げなかった流れの中で」(『時は流れて』http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=53891 ) こうして初期中島みゆきを見てみると、これらの歌詞との、ある緊張感を伴った同居が可能なものとしての「演歌」語、 つまり「大衆的抒情との訣別」・「回収されることのないもの」・「回帰ではない復権」としての、 彼女が言う「ふるさと」とは何なのかと考えてしまう。 それが、「大衆的抒情」「語」のひとつに違いないと思うからだ。
話は飛ぶ(ように見える)が、そして歌謡曲と詩を同時的に論じるのは無理がある(両方から叱られるだろう)が、 金時鐘(キム・シジョン)が若き日に多大な影響を受けたという、小野十三郎『詩論』にある「短歌的抒情の否定」という命題について、 倉橋健一が語るブログが目に留まった。 『小野さんが「歌」を否定したのだと戦後、誤って解釈されてきた節がある。じつはそうではなく、 小野さんが嫌悪したのは当時の歌人であり、そこで歌われた短歌だった。 決して日本古来の文化伝統としての「歌」そのものを否定したものではなかったのです』 ぼくは、金時鐘の講演か著作で『短歌的抒情との訣別』とか『短歌的抒情と「切れて」「繋がる」』、また『まみれても垢じまない』とか『何十年となく平俗なお上の正義を説き続けている、人気番組「水戸黄門」ぐらいからは離れねばなりません』という言葉に出会ったこともあるので、詩人が身に沁み付いた自身のリリシズム(情緒)と如何に格闘しているかを聞きかじってはいた。 だから、署名「umineko」氏のちょっと浅い論難(http://po-m.com/forum/showdoc.php?did=95709 )に出遭ってビックリだ。 曰く、『抒情や情感を排除することが詩人の目標じゃない気がするんですけどね』 『土砂降りの雨に濡れてしまっては正確な判断が出来ない、だから窓の内側からそれを眺めなさいっていうのは、それでは時代から孤立するだけだ。雨の真ん中でも流されない強さが狭義の「詩人」って気がするんだけど。』 ん?
金時鐘の場合、身に居座り、ゆえに存在を脅かし、拘り越えねばならないもの・・・、それは、根が「朧月夜」など幼い日々に唄った戦前日本の唱歌や、中学で暗記した「万葉」などに発し、身から追い出そうとしても出て行かず、幼少年期の情操的記憶を辿ればそればかりが出てくるという痛切の「公的」受難だ。それは、植民地朝鮮の「日本」語「抒情」を自明として受け容れ(てしまっ)た、元:皇国エリート少年の臓腑に宿る、遡って消し去ること叶わぬ宿業としての「抒情」なのだ。「切れて」「繋がる」とは、境界を跨ぐ者が辿り着いたアイデンティティであり、強いられた「自発」によって屈折の果てに棲み付いてしまった「日本」語「抒情」の「魔力」との格闘だ。 その歴史から、ぼくらは多くを学び知るのだ。 己に何が巣食っているのかを・・・。 そして、逆に、何が「回収」されざる「個」的情感なのかを・・・。 「大衆的抒情」「語」(だけ)を「排除」せよとか、土砂降りを「窓の内側から眺めなさい」などとは誰も言ってはいない。こうした浅はかな論者は、その「魔力」に圧し潰されそうな心的境遇に閉じ込められたことも、まさに土砂降りの中に立ったことも無いのだろう。 金時鐘こそはずっと土砂降りの中に立ち尽くしている。 その雨の、肌を引っかき身を刺す痛さを、骨に沁みる疼きを、想像できないのか?
ところで、初期中島みゆきには、この「umineko」氏のような無理解とは違う、彼女なりの(年齢や生育過程{産婦人科病院の娘}や境遇の制約を越えた)立ち位置(想像力・構想力)が見えるので、曲の素晴らしさと相まって腑に届いたのだった。彼女が、どちらかと言えばウェットな曲の歌詞中で多用する、「ふるさと」という「語」の危うさ(無批判な郷愁・保守・撤退・諦念・課題放棄・マザコン/ファザコン)が気になってしかたなかった。気になって『ホームにて』の主人公に分け入った。 『演歌の向こう側と「切れて」「繋がる」ために①~⑤』の最終として、『ホームにて』仮説ストーリーに乗せて、初期中島みゆき「ふるさと」について述べて締めくくることとする。
『ホームにて』( http://www.youtube.com/watch?v=RcgDe3CcU5I&feature=related ) 主人公は、いまで言えば、それこそ西原理恵子の漫画に登場するような女性ではないだろうか? 保育士(か美容師か看護師)を目指して短大に行ったのだが、父入院もあり中退した。事務員として中堅商社に勤めるも、経理能力などなく、元々の職業的希いもあり仕事に馴染めない。着飾って色恋の話に明け暮れ寿退社で辞めていく同僚、いささか不器用で美人でもない「わたし」。 いつしか「雑用係」になっていた。数年遅く入社した美人のA子は男性社員からチヤホヤされ、まるで先輩づらだ。女が職場に進出したとは言え、30年以上前、70年代末の中堅商社はなお「お飾り女性社員」「職場の華」「男性社員の妻予備軍」をこそ求めていたのだ。 【「わたし」の独白】 けれど、「わたし」に、制度とも言えるその風土を覆す「技能」も「智恵」もない。女の「キャリア」への願望は、その手前で踏みつけられていた。 70年代末に(今はもっとそうだけど)、実家の援助なく女ひとり都会で暮す、その困難が解りますか? 会社を辞めたのは、確かにアパートと自宅との往復しか出来ない経済的・人間関係的「貧困」も理由だし、永く病床に在った父が亡くなった家の事情も、いいかげんな男に多額を貸して返って来なかった失敗も大きなきっかけです。けれど今の、昼のアルバイトと夜の接客業は自ら選んだ道です。男の裏表(いや裏ばかり)も人並みに知りはしました。そりゃ、OL時代より収入はうんと増えたし、大学へ通う弟に職業を隠して支援もしてやれる。 だけど、あの最終に乗らないと、このネオンライト輝く虚飾の街が、「わたし」の出てゆけない棲処となってしまうヨ。(21世紀。今、「単身」「派遣女性社員」の多くがこの周辺を生きている)。 「わたし」、若く見えても、もう来年31歳よ。けれど、遅くはない。来年必ずあの最終の汽車に乗って行き、不足単位を取って保育士になるんです。今度の春から再開するんです。去年も一昨年も出来なくて、「ドアは閉まり」「手のひらに」は「空色のキップ」だけが残って溜まるけれど、それはこの夜の街のネオンライトでは燃やせやしないのよ。残ったキップを燃やせない間は、汽車にも乗れやしないのよ。
ハッキリして来たヨ。「ふるさと」は、後ろではなく前に在る。時間的には過去ではない。距離的には遠方ではない。 実際の「ふるさと」は変わってしまっているだろうし、そこには友はもういない。そして、ネオンライト下を生きる「わたし」を歓迎するはずもない。 けれど、「わたし」が抱いて来た希いが「未来」へ向かおうとするなら、必要なものをきっと見せてくれるハズ。 そうだ、「ふるさと」は明日であり未来であり、困難だけれど「わたし」次第で実現可能な世界への入口だ。 「わたし」が、それと「切れて」、そして「繋がる」べき、「わたし」の歴史と未来、その可能性総体だ。 汽車で行った先には、「わたし」のような人たちがたくさん居るに違いない。 あなたが望むのなら、「わたし」がその人たちと自分とを、「We」と呼んでもいいよ。
****************************************************************************************************************
【余談】①(ウィキペディアより) 互いにライバルと認め、仲もいいと言われているユーミンは、 「私がせっかく乾かした洗濯物を、またじとーっとしめらせてしまう、こぬか雨のよう」と中島の音楽を評したそうだ。 ユーミンは「恋愛歌の女王」と呼ばれ、中島みゆきは「失恋歌の女王」と言われているそうな・・・。
【告】:本稿をもちまして歌詞研究:『演歌の向こう側と「切れて」「繋がる」ために①~⑤』を一旦終了します。 閲覧を感謝します。①~⑤通して再読され、上のEメール・タグを開きご感想・異論など下されば幸いです(非公開です)。 ①『「阿久・大野・ジュリー」組が駆け抜けた70年代最後の五年間』 http://www.yasumaroh.com/?p=5779 ②『演歌における多頻出「語」』 http://www.yasumaroh.com/?p=5887 ③『大衆的抒情の一義的「在処」』 http://www.yasumaroh.com/?p=5930 ④『「We」の不在。「我らが我に還りゆくとき」⇔「我らなき我と切れゆくとき」その往還』 http://www.yasumaroh.com/?p=6376 ⑤『初期中島みゆきにおける「ふるさと」』 本稿 http://www.yasumaroh.com/?p=6603
たそがれ映画談義: 『パリ20区、僕たちのクラス』
追悼: 1960年6月15日樺美智子さんの死 から50年
6月15日、梅雨入り前の薄曇。 日ごろの行ないが良い(?)のか、巡り合せなのか赤坂の工事現場にいた。 国会議事堂まで徒歩20分圏だ。近いので、昼休みに向かった。12:00から樺美智子さんの追悼集会がある。 50年前の今日、1960年6月15日、日米安保条約の改定に反対する全学連主流派(安保BUND)ら学生が 南通用門から国会内に突入。混乱の中、東大生樺美智子さんが死亡した。警察は転倒による圧死と発表し、 全学連は官憲の暴行による虐殺だと告発した。 60年安保フォトギャラリー: http://www.arekara50.org/gallery/ 安保BUND書記長:島成郎 : http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1101872026/subno/1

12:20に南通用門に着いて、献花・焼香した。 当時樺さんと共に活動していて東大生だったという古賀康正氏、他に蔵田計成氏・三上治氏、塩見孝也氏などから発言があった。いずれも、ひと世代上の人々だが、こんな発言が耳に残った。 『人は二度死ぬ。一度目は生命の終わり。二度目は人々の記憶から消えること。 樺さんを二度死なせてはならない。樺さんが目指したものを記憶から消してはならない』 『50年経って、今ほど日米安保が、戦後そのものが、問われている時はない。あれほどの国民運動だったが、安保体制は沖縄への基地集中という遺産を遺したまま生きている』 『私を含め安保全学連、安保BUNDを構成する者の辞書には「沖縄」はなかったと思う。そのことを真摯に認めたい。50年経ってぼくらが出した回答が「民主党政権」による先般の「日米共同声明」では・・・・。樺さんが生きていたら、きっと「それは違うんじゃないかしら」と言われるだろう』 みなさん、さすがに弁舌達者。 
 最後に全員で黙祷していると、右翼の街宣車が大音量でやって来て、吠えた。 『祀り上げるよりも、女子学生一人助けられなかった無計画・無謀・無力を恥じよ!』 『女子学生が官憲に殺されたと言うが、テメエら身内同士で一体何人殺したのだ?』 彼らに言われる筋合いはないが、それも遺産だ。悔しく耐え難いことだが、50年の中には間違いなくそのことも含まれている。
最後に全員で黙祷していると、右翼の街宣車が大音量でやって来て、吠えた。 『祀り上げるよりも、女子学生一人助けられなかった無計画・無謀・無力を恥じよ!』 『女子学生が官憲に殺されたと言うが、テメエら身内同士で一体何人殺したのだ?』 彼らに言われる筋合いはないが、それも遺産だ。悔しく耐え難いことだが、50年の中には間違いなくそのことも含まれている。
昼休憩が終るぅぅ・・・・・・一時半に資材が来るぅ~・・・。あわてて現場に戻った。 右の二葉は献花・焼香して佇む元某派議長S氏。
抗議: 報道ファシズム
閣僚が国旗に一礼しなかったと騒ぐマスコミ
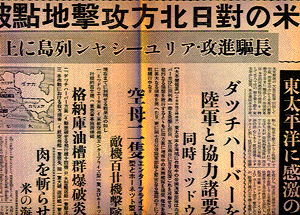 民主党政権を「極左的政権」と呼ぶ知事が居るかと思えば、今度は閣僚のうち何人が国旗に一礼しなったかをカウントして騒ぎ立てている新聞がある。
民主党政権を「極左的政権」と呼ぶ知事が居るかと思えば、今度は閣僚のうち何人が国旗に一礼しなったかをカウントして騒ぎ立てている新聞がある。
【産経新聞】 14日配信 『 官邸での会見後に、担当省庁などで開催された「省庁会見」では、千葉法相と蓮舫行政刷新担当相、玄葉光一郎公務員制度改革担当相、直嶋正行経産相、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相の5閣僚が会見室に設置された国旗に頭を下げなかった。9日午後、内閣府での会見に臨んだ蓮舫行政刷新担当相も国旗に一礼はなし。亀井・玄葉・直嶋の3閣僚も会場に掲揚された国旗におじぎなどはしなかった。これらに対して菅直人首相は14日、衆院本会議の代表質問で、平成11年成立の国旗国歌法に反対した当時から方針転換した“心境”を語った。 首相は「もっと元気のいい国歌でもいいかなという意見があった」と、同法の採決で対応が割れた民主党内の情勢を説明したが、自身が反対した理由は触れずじまい。その上で「今は常に国旗があるところではきちんと敬意を表し、国歌斉唱もしている」との弁明も忘れなかった。 』
のだそうだ。民主党政権が「極左」とは全く思わないが、この種の口撃のエスカレートは「いつか見た風景」だと思うし、近年激発している排外主義団体の市民への各種暴力と同根の三人四脚(国家・報道・草の根極右)だと思う。菅首相の対応は、軍部の台頭を前に腐心したリベラル政治家の姿に似ている。その後の15年戦争への道は誰もが知るところだ。事態は容易ならざる局面だと思う。 こうした構造を変えていくのは、国民的反撃、報道機関を「まともさ」へ向かわせる世論、宗教・団体・政党、その合力、包囲しかない。そう心したい。同じ14日福岡高裁が、生活保護:老齢加算廃止を違法として逆転判決を出したが、 時にはこうした司法判断もあるこの社会にも、ぼくらにも、まだ包囲力はあると思いたい。
歌遊泳(歌詞研究): 演歌の向こう側と 「切れて」「繋がる」ために ④/5
「We」の不在。「我らが我に還りゆくとき」⇔「我らなき我と切れゆくとき」その往還。
全ての「語」を通じて、最も多いのは、ダントツで二人称「君・あなた・お前」だった。これは予想通りなのだが、気になったのが「我々」「我ら」「ぼくら」の少なさだ(もちろん歌いにくいが)。 日本の現代で「我ら」「我々」が生きていた時代として、明治の殖産興業・富国強兵の時代、昭和の戦争期、戦後の復興と民主主義(?)建設~60年安保以前、などを思い浮かべる。民はその時代が提供した「我ら」を抱いて生きた。 我が父(故人)が、最晩年にさえ「何を置いても」出かけたのは「戦友会」だった。思えば、学校や青年期の「特権」とは無縁だった彼(ら多くの同状況の人々)にとって、軍隊が「我ら」を実感・体現できるほとんど唯一の空間だったとしても不思議ではない。「我ら」の回収先は、同時に大衆的抒情の仮終着駅でもあり、用意された「我ら」が持ついかがわしさを思えば、「我ら」論はいくつもの条件を付けて考えなければならないと思う。 20世紀に語られた「我ら」が、主として「国家」と「体制」の側とそれを支持した民から提起され、「我」なき「我ら」に終始した歴史や、近年でも政治性を帯びた過剰な「我ら」に翻弄(?)された記憶があり、「我ら」忌避症候群となっている根拠は納得できる。 「我ら」喪失は、共同性の認知が成立し難い社会の反映だとは思うし、20世紀以降の世界的傾向かもしれない。
日本語には、英語の「We」に当る「語」がない。「我々」「我ら」は訳せば「We」だろうが、「We」という独立した関係性そのものではないように思う。 「We shall over come」 「We are the world」的な「ぼくら」の歌はほとんど無い(海外は不知)。 モノマネよろしく揶揄を込めて演じられたりする、ぼくらの時代の若者の「我々は~」という語り口調は、「我ら」欠乏を嗅ぎ取った若者の直感が、それを埋め合わせようと言わせたものだったように思うが、それが、イデオロギーによる過剰な「我々」だった不幸(?)を認めない訳には行かない。 「We」が成立する条件は、その社会の共同の目標や公的受難の歴史性だ。昨日今日「頭で考えた」だけの促成「我ら」にはその条件が不充分ではなかったか。同時にその「我ら」は、「我」の「何処へも転嫁できない」己ひとりの「自己責任」を霧散させ「回収」してくれる、都合のいい装置でさえあったと認めたい。同世代の歌人:道浦母都子さんの初期の歌集『無縁の抒情』に、自己免責装置にしてイデオロギー過剰な「我ら」との自戒的訣別を詠んだ 『今だれしも俯(うつむ)くひとりひとりなれわれらがわれに変わりゆく秋』 がある。 章の標題は 『われらがわれに還りゆくとき』であった。
もうひとつの側面として、仕事・労働の歌が無い。大衆歌謡が普及した社会の初期にはあった協働社会は姿を変え、労働現場や地域社会での「共 助」は解体して行く。その反映だろうか、抵抗・祭典・共同創作・労働(直接表現は白々しいが)での「我ら」を匂わせてくれる歌もほとんど無い。 どうやら、個人は二人称とは強い絆で結ばれてはいるが、その先は飛躍して「国家」(さすがに歌には直接は登場しないが)に直結し、その間にあるのは「企業」や「食扶ちを稼ぐ労働」「意識せざる個利(個人ではない)主義」であって、Sociaty・Community・社会ではない。「友」や「仲間」との共同体験・共通苦難が、辛うじて「我ら」への道筋だが、それも労働現場では、「労働組合」が「まとも」である場合以外は、企業が用意した「我と乖離した」「我ら」が大手を振って来た。共同体・協働性・共助を支えるものとしての、我と我ではないひとつの「We」なる別もの、その欠落。それは、その社会の正直な表現だと言って差支えないのではないか。であればこそ、『我らなき我と切れゆくとき』をあえて意識していたい。
21世紀、グローバル世界の経済・軍事、旧宗主国(旧ソ連を含)の資源や輸送陸路確保の領土的野心に晒されている地域には在るだろう「We」。ある社会が総体として受難を被る場合以外「We」は在り得ないのか?先進○ヶ国に共通だろう「We」欠乏の傾向は、どうしよもないことなのか? 宗主国と植民地に例えれば、「We」存命可能な社会への傾倒・共感・同化によって、「We」を掴んだとしても、倒錯した代行性はシッペ返しを食らうだろう。宗主国の民は、植民地から収奪(財・土地・資源・文化・全て)して維持されている当の宗主国の民として、宗主国に物申す立場、植民地を手放せと迫る以外に、植民地の民と「We」関係を結べないのではないか?
歌謡曲歌詞を語るつもりが脱線気味だが、語らねばならないのは、21世紀先進国日本の歌謡曲に心動くぼくら民の「We」の話だ。 歌詞の中に「我ら」「我々」などを入れよと言いたいのではない。「回収先」からの「我ら」はすでに先手を打って提案されている(「回収先」が用意した「我ら」など、ベタベタの個人主義より質〈タチ〉が悪い)。言いたいのは、演歌の向こう側に潜むものの呪縛と「切れて」、前回の文で言う、「大衆的抒情との訣別」、「回収されることのないもの」、「回帰ではない復権」への挑みと「繋がる」・・・そういう歌詞のことだ。
その歌詞には、それがどんなに「私」的歌であっても、色恋の「恨み辛み」歌であっても、大衆的抒情語を駆使するものであっても、そして一見社会性と断絶していると思えても、その向こうに別のものが見えるのではないか? 見えるもののひとつに、潜在的「We」がかすかにあるかもしれない。 演歌に『われらがわれに還りゆくとき』と近似の意志を見るときがある。それが、『我らなき我と切れゆくとき』との往還という、困難な課題を唄う「場」に立つとき、その歌はぼくらの腑に届いてしまうのだ。 初期中島みゆき『あぶな坂』(http://www.youtube.com/watch?v=I55y-q4U7Eg )にある、黒い喪服の女性が言う「遠いふるさとで傷ついた言い訳に」「坂を落ちて来るのが」「ここからは見える」の、その「ここ」は、そうした「場」に近いように思う。そのことをひとつの仮想として、次回、初期(ここ20年はほとんど知らないので)中島みゆき歌を取り上げたい。 「ふるさと」「わかれ」「帰る」「忘れる」のあまりの多用に、「郷愁」と「執着」を聞き辟易した友人もいたが、ぼくは逆に、歌詞中の主人公の「切れ」ようとして「繋が」れない物語に、「切れて」「繋がる」方法を探しあぐねる「我がことのような」彷徨を見たのだった。そしてぼくは、いまなお、その彷徨の「途上」=品川宿に、居残っている。 ところで、では一体、当時の中島みゆきが言う「ふるさと」とは何だったのか? 『ホームにて』 http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=11632
たそがれ映画談義: 公開中『パーマネント野ばら』
日曜日、映画『パーマネント野ばら』(2010年、監督:吉田大八)を観て来た。 http://www.nobara.jp/ 西原理恵子の漫画が原作。菅野美穂、実にええですね。
夏木マリ、小池栄子、江口洋介、宇崎竜童、池脇千鶴らも好演、よろしかった。 原作は全く知らないのだが、ストーリーの「からくり」は途中で解ってしまった。 けれど、それがわかったときの透き通った感覚は、何とも言えず痛く恋しいものだった。 生きることが日常近辺の「非日常」を含めた繰り返す「日常」と、それを超えるもの- 【夢とか、見果てぬ夢とか、浪漫と呼ばれている、譲ることのできないもの】- と「切れて」「繋がる」想念によって成り立っているということを、 (これまで)終始「受身」に生きてしまった主人公の「物語」を借りて描いたと思う。 きっと、主人公ら登場人物と作り手自身と観客の、再生・復権の明日を希って撮ったと思う。 間違いなく秀作です。
ぼやき: 何が正念場なのか
沖縄以外のマスコミの身勝手には、開いた口が塞がらない・・・
「二重権力だ」「小沢支配だ」とガナリ立て、脱小沢を煽り、世論調査なる伝家の宝刀で 辞任を求めたマスコミ。今日のヤマトの大新聞の紙面では『小沢抜きで大丈夫か?』とか 『政権の危機、正念場だ』と騒いでいる。この無節操は何なのだ。要は、旧政権へ戻したいだけなのだ。 どうやってもケチを付けるヤクザの論方だ。ぼくらにとって、そんな論議はほとんど無意味だ。 新内閣が、日米軍事同盟・戦後体制の根本の見直しへと進むことを願うだけだ。 その第一歩『普天間-辺野古の日米共同声明』の修正協議へと進むことを願うだけだ。 その実現を目指す動きに関わっていたい。
日米共同声明撤回を 那覇市議会、県内初の意見書可決 【6月8日10時0分配信 琉球新報】
那覇市議会(金城徹議長)は7日午前、6月定例会で、普天間飛行場の 移設先を名護市辺野古と明記した「日米共同声明」の撤回を日米両政府に求める意見書を全会一致で 可決した。そうぞう会派の3氏は「普天間飛行場が固定化されることがあってはならない」として退場した。 日米共同声明撤回を求める意見書可決は県内で初めて。同意見書では、「『県内移設』反対という 県民の総意よりも米国政府の意向を最優先するもので、民主主義を踏みにじる暴挙であり、断じて 許せない」と強い反発の意思を示し、「県民の『県内移設』に絶対反対との総意は、4・25県民大会や 全市町村長の反対表明、マスコミの世論調査などでも明確だ。 怒りを込めて日米合意の撤回を強く求める」としている。
歌遊泳(歌詞研究): 演歌の向こう側と「切れて」「繋がる」ために ③/5
大衆的抒情の一義的「在処」
阿久悠歌詞を、日本の大衆的抒情と「切れた(い)」とか、それとの「訣別」と、容易く書いてしまったぼくの舌っ足らずかも・・・。 あの文章(http://www.yasumaroh.com/?p=5779)が、「文学論」「サブ・カルチャー論」に届くとは思っていないが、結語に書いた 『阿久悠は、「終焉」の前の「喘ぎ」を演じた(作詞した)のだろうか。』 『日本の歌謡にへばりつく大衆的抒情と「訣別」することを通してしか、出来はしないと考えたのだろうか。そして、それに成功しただろうか? そこは各自の評価だ。』 辺りの言い回しで、ぼくの水準からは「精一杯」の阿久悠の挑みへのエールとご理解願いたい。もちろん、阿久悠・ジュリー歌も次の三つの阿久悠:代表曲と同様に、基本的には「演歌」ではある。 『ジョニーへの伝言』(74年) http://www.youtube.com/watch?v=b5z94O4-ZgA 『津軽海峡・冬景色』(77年) http://www.youtube.com/watch?v=38on-Pw7MRo&feature=related 『雨の慕情』(80年) http://www.youtube.com/watch?v=P0I3moSIU4M 
ところで、その「日本の歌謡にへばり付く」「大衆的抒情」とは、いかなるものなのか? 吉本隆明は古い論考『日本のナショナリズム』(64年)の中で、 『冬の夜』(ともしび近く衣縫う母は 春の遊びの楽しさ語る)、『赤とんぼ』(お里の便りも 絶え果てた)、『青葉の笛』(一の谷のいくさ破れ 討たれし平家の公達あわれ)、『七里ヶ浜の哀歌』(真白き富士の根 緑の江ノ島)、『故郷』(兎追いしかの山 小鮒釣りしかの川)、などを取上げた後、 『ある種の愚者たちは』『日本の大衆にのみ固有なものであるとかんがえている。かれらは、ロシアやアメリカには大衆のセンチメンタリズムが存在しないものと錯覚しているらしい。』『大衆のセンチメンタリズムは、そのナショナルな核にしたがって質がちがっているというにすぎないのを知らないのである。』『ボートが沈んだとき中学生たちは、いかにもがき苦しみ、われ先にと生きのびようと努めたか、という大衆の「ナショナリズム」の裏面に付着したリアリズムを忘却するように書かれている。』『わたしたちが大衆の「ナショナリズム」としてかんがえているものは、この表面と裏面の総体(生活思想)を意味するもので』あって、『その表現にすくいあげられている一面性を意味しているのではない。』 と述べている。 確かに、『故郷を離るる歌』(ドイツ民謡」)とか、『埴生の宿』(イングランド民謡)とか、『ともしび』(戦地に赴く若者とその恋人=1942年作、ソ連時代の歌)などたくさん思い付く。 これらは、大衆的抒情が「そのままでは」国家意志に回収される危うさの中を浮遊していることの論証になるだろう。
ぼくも、社会的(あるいは政治的)な主題の喪失・忘却・放棄や土着のロマンチシズムが覆う歌謡は、作り手と聞き手の往還の中で増幅・再生産されて行ったと思うし、それは今も変わらないと思う。ぼくが求めているのは、吉本の言葉を借りれば「表面と裏面の総体」を掴む歌謡だ。決して、無味乾燥な政治性や思想性過剰な「思想歌」「プロパガンダ歌」「メッセージ歌」ではない。そんなものに、生活総体を射る「力」などない。大衆的叙情・センチメンタリズムというものの一面性同様、ぼくらが持つ政治的・社会的な怒り・不満・目標・理想を並べ立てたところで、それもまた一面性なのだ。
次々回(⑤/5)、初期中島みゆき歌詞を取り上げる。そこに、前回書いた 『自身に棲む「大衆的抒情」「センチメンタリズム」「土着的浪漫」との「訣別」と、それらへの回帰ではない「復権」。「切れて」「繋がる」。』 が、潜んでいるかも・・・。 「復権」。 それは、国家意志・地域社会の黙契・企業の没我要請・宗派の排他的教義・党の独善と非複数主義、「個」が見えない政治性、 などから影響・誘導・支配を受けないものとして、それらへと回収されることのないものとして、 かならずや社会性・普遍性に繋がっている個的世界を確保しようとする、「個」の内側に宿る固い意志によってのみ可能なのだ。 そのことを共有できるような「演歌」が、心に届くのだと思う。 それは、熊沢誠が各個人の個的体験(とされてしまった過労死)の葬列を、あえて「くどい」ほど書き綴ることによって、 「個」のかけがえのない「生」(夫婦・家族・労働・希/夢・人並みの欲・趣味・こだわり事)の重量覚知から、 つまり情理によって導かれた個別性への拘泥から、全体性(社会性・普遍性)を描き出した作業に、ちょっと似てはいないか? ☆熊沢誠:著『働きすぎに斃れて』(2010年、岩波書店)← http://www.yasumaroh.com/?p=5251
歌遊泳(歌詞研究): 演歌の向こう側と「切れて」「繋がる」ために ②/5
演歌における多頻出「語」
過日、阿久悠・ジュリーに関する過去の文章を加筆修正して当ブログに掲載(http://www.yasumaroh.com/?p=5779)したところ、早速知人からお叱りを頂いた。 曰く、『阿久悠が日本の歌謡にへばりつく「大衆的抒情」と訣別している、などとはとうてい思えない。阿久悠の現代・都会「演歌」には、同じものが「へばりついている」と思う。』 現代・都会「演歌」、うーん上手いこと言うねぇ。頭に「現代」や「都会」と付けたところで、「演歌」であることに変わりはないと言っている。それに関しては、全く同感だ。 ぼくが言いたいのは、阿久悠作詞に於ける挑戦、そして映像的であることによる「歌」の「抒情」「語」拘束からの仮解放である。 http://www.youtube.com/watch?v=BNfs8dL0hjg http://www.youtube.com/watch?v=hNZ4VvMaYt4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=3AszYpnrpUE&NR=1
過日ブログで取り上げた歌詞は次の通り。彼の「違う演歌」への挑みが、「切れて」「繋がる」映像が、垣間見えないか? 「身体の傷なら直せるけれど 心の痛手は癒せはしない」(『時の過ぎゆくままに』75年)、 「思い出かき集め 鞄につめこむ気配がしてる」(『勝手にしやがれ』77年)、 「傷つけ合うのが嫌いだからと ずるずるみんなを引きずって」(『憎みきれないろくでなし』77年)、 「片手にピストル 心に花束 唇に火の酒 背中に人生を」(『サムライ』78年)、 「あなたには帰る家がある やさしくつつむ人がいる」(『LOVE抱きしめたい』78年)、 「男がピカピカの気障でいられた。ボギー、ボギーあんたの時代はよかった」(『カサブランカ・ダンディ』79年)。
「大衆的抒情」の世界的一般性と「日本の」特性について考える為に、昨09年作った、歌謡曲に登場する「語」(名詞・動詞に限る)から特に多いものを探ったメモを添付する。歌謡曲は、これらの「語」の組合せによって作られてもいるが、それには理由がある。ぼくなりに気が付いたことを、次回ここに書くが、今日はまず、その一覧を見て欲しい。



【Uta-Net 歌詞検索】より
タイトルあるいは唄い出しに、その「語」が含まれる曲数の一覧。(09年7月筆者集計)
凡例: 例えば、語「時」なら、時代・時間・時・時に・時計、など「時」が含まれる「語」のすべてが該当。 タイトルにも歌詞にもその「語」があれば、重複カウントされている。 また、例えば、『なごり雪』なら「雪」、唄い出しの「汽車」「待つ」「君」「ぼく」「時(計)」、など全ての項目に重複カウントされている。 狙い: 実際『なごり雪』は、後の歌詞も「季節」「最後」「呟く」「春」「窓」「唇」「さよなら」「ホーム」など、下記の多頻出「語」のオンパレード構成となっていて苦笑する。『なごり雪』こそは「演歌の王道」を歩んでいるのだ。 高齢者には「ニュウ」ミュージックでもあるこの歌は、昔も今も老若男女に受け容れられ支持され続けている。もちろん、メロディーの美しさが大きな要素だが、ぼくらに刷り込まれた「語」感と、そこをくすぐる「演歌の王道」を行く歌詞とは響き合い抱擁し合うのだ。「言葉」化されることを待っているぼくらの大衆的抒情と、「語」の側の時代を超え時間を経て培われた吸引力は、決して侮れない。世とぼくら自身に沁み付いている。それを検証もなく「琴線」などと持ち上げて呼ぶ論者がいるなら、いかがわしい限りだ。素朴で無垢な、そのままではいか様にも弄ばれる危うい情感、まさに大衆的抒情の核心ではないだろうか? 国家・郷土・戦争・教義・党・日本の企業風土・・・、回収先はいくらでもある。 ところで、下の表は、歌のジャンルを一切問わないので、数は盛り場歌謡に影響されたりもしているが、それらは、おんなと男の立派な艶歌です。 全体でのベスト9は、①君・あなた・お前 ②時 ③夜 ④空 ⑤愛 ⑥風 ⑦恋 ⑧花 ⑨夢 である。その理由、そして各欄の最多「語」の理由、そこを探り歌謡曲に於ける大衆的抒情の在処を考える糸口としたい。他に、種類が多くて正確なカウントができなかったが、「生物」という項目を作れば花:約3800、木・樹:約950、鳥:約900である。また、モノ名詞・情感・想念・抽象の「語」、動詞、人の心の動き、などで記載できなかったものは多数ある、ご容赦。 「ひとり」1019、「ふたり」534、「水」675、「森」263、「火」523、「炎」192、、「音」1001、「鐘」105、「影」632、「群」166、 「都会」249、「詩」257、「香・匂」479、「乱」188、「流」1428(時間含)、「消」655、「終」1170、、「過ぎ(る)(て)」602、 「追」529、「逃」247、「回」360、「飛」846、「咲」845、「散」468、「踊」422、「落」696、「崩」51、「堕」57、「迷」429、 「惑」179、「発」180、「起」254、「鳴」473、「燃」281、「憧」117、などが、いい歌詞の中にあるのですが・・・
中島みゆき歌が「演歌」だと断ずる人の言い分は、おそらく、それが下記の表の多頻出「語」の組合せという 「演歌の王道」の枠内にあるという確信に拠っているのだろう。 ぼくは、「演歌主義者」なので、それがどうした?という立場だ。 歌は、すべからく演歌なのだ。 艶歌・怨歌・厭歌・縁歌・宴歌・焔歌・援歌・演歌、だ! 問題は、自身に棲む「大衆的抒情」「センチメンタリズム」「土着的浪漫」との「訣別」と、それらへの回帰ではない「復権」。 「切れて」「繋がる」。そこなのだ。
| 区分 | 語(名詞・動詞)、曲数 | 寸評 |
| 季節 | 春1415、夏1763、秋438、冬588、季節657、 | 夏を好むが、熱・暑ではないんです。わかります。 |
| 気候 | 暖117、熱・暑155、涼・爽39、寒・凍256、 | |
| 気象現象、自然 | 雨3078、風4095、雪1178、霧335、雲776、嵐213、波791、晴554、光・輝1981、闇583、 | 雨ではなく「風」か |
| 地理的場所等 | 海1892、浜294、川・河916、道2091、山538、岬155、島321、丘・坂652、草(草原)975、 | 草、意外に多いですね |
| 時間帯 | 夜明け434、朝1537、午後274、夕・夕日・夕暮486、たそがれ177、暮756、夜5238、 | 歴史は夜作られる? |
| 人的時間① | 生2433、命635、死379、人生478、若・青年397、少年290、少女・乙女305、子供261、 | |
| 〃 ② | 時5319、昔・過去410、最後439、現在・いま812、未来531、明日933、昨日388、初571、 | 時・時間・時代。 |
| 行動・動作・伝達 | 旅1049、走・駆955、泳110、歩1253、卒業128、遊255、休206、疲273、眠・寝1228、 話935、告206、語508、叫178、呼554、囁・呟134、伝404、泣1493、笑1490、歌1492、 | 人は本来、歩く。眠る。 |
| 最後は、泣いて笑って歌うのか | ||
| 社会性・共同性 | 仕事・働261、祭165、闘・抗・集・絆368、村59、世1653、街2505(共同性なのかどうか)、 | 働・闘が歌になりにくいのは解る |
| 人工的場所 | 駅・ホーム787、港398、空港18、校舎・学校・教室183、窓430、扉228、ビル178、 | やはり駅か。別のホームも混入 |
| 天体 | 星2035、月2328、太陽868、空4182、宇宙231 | 空、多いんですね |
| 乗り物 | 汽車・列車389、船517、バス254、飛行機75、車1031(クルマではなく車全て)、 | 汽車よりも船か・・・ |
| 人称 | 私・ぼく・俺1925、君・あなた・お前10618、我々・我ら・ぼくら・仲間695 | そりゃそうでしょう |
| 情感 | 喜113、怒・恨193、哀・悲1152、苦202、傷・痛765、楽473、涙・泪1839、 | 泪には全て含まれるもんね |
| 想念 | 故郷・ふるさと364、希・願587、夢3375、心2349、思い出535、忘1013、諦142、欲243、 酒・酔885、遠655、帰る770、待つ989、棄・捨259、切れる・果てる・絶える・離2657 | 夢。 人は、これなしでは生きられないのだと思う。 |
| 男女 | 男1155、女2376、出会(逢)438、抱1116、惚161、別・さよなら2258、恋3916、愛4138、 | さよなら(だけが)、恋、愛 |
| 婚姻・血縁 | 妻・女房2372、夫・だんな11、夫婦・めおと73、母・おふくろ276、父132、 | 当然でしょうな。 |
| 身体 | 顔1168、目1876、口・唇765、声939、耳245、腕203、手2494、指611、爪107、背中345 | 手が最多とは・・・ |