連載 21: 『じねん 傘寿の祭り』 二、 ふれんち・とーすと (8)
二、ふれんち・とーすと ⑧
大宜味村の海岸沿いから山に数キロ入ったところに比嘉のアトリエは在る。数年前に行った時、彫塑も続けているので一定の広さも必要なのだと聞いた。確かに広いのだ。近隣に、陶芸家や染物の工房が点在していた。  比嘉のアトリエに向かった。二時を過ぎていて、時間も無いが高速を使えばユウくんが帰宅する六時前後には帰れそうだ。許田インターを出て海岸沿いに走った。 比嘉に会うと、黒川の大風呂敷は影を潜めていた。大阪を閉めたことを詫び、沖縄に来てから訪問も電話も出来ていないことを謝罪している。比嘉の方も「たくさん売ってもろうた恩人や」「奥さんは元気ですかの?」「子供さんは?」「次に来る時には息子を連れて来なさいや。ワシ、あの子のことはよう憶えとる」とやっている。 去年夏の、米軍ヘリ墜落の際の意外な逸話を聞くことが出来た。「第一報は黒川さんじゃった。ワシ、琉大の図書館で調べもんしとったんじゃ。携帯電話が何度も何度もブルブルとしつこう震えとる。とうとう出たらこの人やった。何人もが連絡くれてたんやが、出たときは黒川さんやった。たぶんテレビ速報の直後じゃ。すぐ、親しい院生に現場近くまで送らせた。非常線張られててなあ・・・。黒川さん礼を言います。」 これで打ち解けたのか、黒川は自分の不手際を隠しながら国際通りの物件のことまで話し、「どこかいいところご存じないですか」とやっている。何の事はない、事態を正確に把握しているではないか。 「ああ、あそこのビルなあ。あれは確か大城のビルじゃのお。店子の出入りが激しいと噂しきりじゃ。客が寄らんみたいやのぉ。店子はみな苦戦しとるんやないか。あの辺りはヤマトの観光客から銭を搾り取る場所や、あんたの商売向きやないな。まあ、ゆっくり探しなさいよ、なっ黒川さん。」 ビルの賃貸条件を詳しく伝えた。契約し手付金を払ってしまった、戻らないと思うのでそれは捨ててもこの案は白紙、今後何かと相談に乗ってやって下さい。数秒沈黙があって、比嘉が天井に響く大声で言った。 「黒川さん、急病になれや!」 黒川が目を丸くしている。裕一郎が引き継いだ。 「いや、さっきビルの事務所でもうその予告編はして来たんです。」 説明すると、比嘉は「アハハ。昔のお前さんと高志のコンビを思い出すよ。裕一郎、ワシ昔、労働組合より大阪商売人が向いとると言うたやろ。何で商売失敗したんじゃろかのぉ」と笑った。 「いや、色々ありまして。けど大阪商人が怒りますよ、そんな誤解。東京で、テレビの大阪お笑いものが大阪だと言うのと同じような先入観でしょ。まじめな商人に悪いですよ。今回の芝居が不動産契約に通用しないように、比嘉さんが評価してくれた高志・裕一郎のハッタリ商いも、大阪のまともな商人に見破られた・・・。そういうことです」 「まぁまぁ、そう卑下せんでもええ。お前さんらの会社がハッタリやったとは思うとらんぞ。高志が社長、お前さんが専務してた初期の悪戦苦闘をワシは見とるがな・・・。とにかく急病の線でやってみろや。手付金はたぶん戻ってくるやろ。どないもならんかったら連絡くれ、ビルのオーナー大城の息子、専務じゃが、奴はワシの高校の同級生じゃ。」
比嘉のアトリエに向かった。二時を過ぎていて、時間も無いが高速を使えばユウくんが帰宅する六時前後には帰れそうだ。許田インターを出て海岸沿いに走った。 比嘉に会うと、黒川の大風呂敷は影を潜めていた。大阪を閉めたことを詫び、沖縄に来てから訪問も電話も出来ていないことを謝罪している。比嘉の方も「たくさん売ってもろうた恩人や」「奥さんは元気ですかの?」「子供さんは?」「次に来る時には息子を連れて来なさいや。ワシ、あの子のことはよう憶えとる」とやっている。 去年夏の、米軍ヘリ墜落の際の意外な逸話を聞くことが出来た。「第一報は黒川さんじゃった。ワシ、琉大の図書館で調べもんしとったんじゃ。携帯電話が何度も何度もブルブルとしつこう震えとる。とうとう出たらこの人やった。何人もが連絡くれてたんやが、出たときは黒川さんやった。たぶんテレビ速報の直後じゃ。すぐ、親しい院生に現場近くまで送らせた。非常線張られててなあ・・・。黒川さん礼を言います。」 これで打ち解けたのか、黒川は自分の不手際を隠しながら国際通りの物件のことまで話し、「どこかいいところご存じないですか」とやっている。何の事はない、事態を正確に把握しているではないか。 「ああ、あそこのビルなあ。あれは確か大城のビルじゃのお。店子の出入りが激しいと噂しきりじゃ。客が寄らんみたいやのぉ。店子はみな苦戦しとるんやないか。あの辺りはヤマトの観光客から銭を搾り取る場所や、あんたの商売向きやないな。まあ、ゆっくり探しなさいよ、なっ黒川さん。」 ビルの賃貸条件を詳しく伝えた。契約し手付金を払ってしまった、戻らないと思うのでそれは捨ててもこの案は白紙、今後何かと相談に乗ってやって下さい。数秒沈黙があって、比嘉が天井に響く大声で言った。 「黒川さん、急病になれや!」 黒川が目を丸くしている。裕一郎が引き継いだ。 「いや、さっきビルの事務所でもうその予告編はして来たんです。」 説明すると、比嘉は「アハハ。昔のお前さんと高志のコンビを思い出すよ。裕一郎、ワシ昔、労働組合より大阪商売人が向いとると言うたやろ。何で商売失敗したんじゃろかのぉ」と笑った。 「いや、色々ありまして。けど大阪商人が怒りますよ、そんな誤解。東京で、テレビの大阪お笑いものが大阪だと言うのと同じような先入観でしょ。まじめな商人に悪いですよ。今回の芝居が不動産契約に通用しないように、比嘉さんが評価してくれた高志・裕一郎のハッタリ商いも、大阪のまともな商人に見破られた・・・。そういうことです」 「まぁまぁ、そう卑下せんでもええ。お前さんらの会社がハッタリやったとは思うとらんぞ。高志が社長、お前さんが専務してた初期の悪戦苦闘をワシは見とるがな・・・。とにかく急病の線でやってみろや。手付金はたぶん戻ってくるやろ。どないもならんかったら連絡くれ、ビルのオーナー大城の息子、専務じゃが、奴はワシの高校の同級生じゃ。」
明日、ビル事務所へ行くしかない。タロウの大皿を二点買ったまま代金を支払わないという細川にも、近々会うしかない。重い気分で運転している横で、黒川が鼾をかいて眠っていた。 こらっ!ジジイ! 眠っている場合か! 黒川宅には軽自動車が停められるスペースがある。駐車スペースの錆びて重いスライド・ドアを必死に開けていると、ユウくんが帰って来た。長時間バス通園からの帰還だが、疲れた様子もなく元気に「ただいまあ」と言う。六時少し前だった。 食事のことは忘れていた。あわてて黒川に訊くと 「う~ん、売掛金のことなど君にも少し知っておいて欲しいので、今夜はミーティングをと考えている。食堂に行きたいが連夜というのはいただけない。今夜は作るの中止して、ぼくが食堂のオバサンに頼んでおかずを買ってくるので、君はメシを炊いてくれるかね」 「いいですよ。そうだ黒川さん、明日朝のパン、ついでに近くで買って来て下さいね。」 米を研ぎながら思った。来いよ、来いよ、と誘っていた時、黒川は「メシ? もちろん、ぼくがこさえているさ」と言った。半ば疑いながら感心したのだが、今朝の「パン食」の意味が、パンのみとジャム又は漬物だったように、あれは「米はぼくが炊いている」だったに違いない。笑ってしまった。 確かに、「メシをこさえている」のだ。
連載⑳: 『じねん 傘寿の祭り』 二、 ふれんち・とーすと (7)
二、ふれんち・とーすと ⑦
後に分かったことだが、玲子、高志の妻玲子が、比嘉の彫塑や版画以上に彼の詩のファンで、「比嘉さんに場所を提供してあげてよ」「ええなあ、子供連れて比嘉さんの泥こね手伝いに行こうかな」と羨むように望んでいたという。それを知った当時、玲子ならそう言うだろうと納得した。 受け容れを決定した三日後、比嘉は泥こねのトロ箱を持ち込み、頭にバンダナを巻いて早速下地板の製作から始めた。
 垂木を軸組みしてコンパネ=厚いベニヤを、ビス縫いして行く。レリーフと言ってもこういう下仕事があるのだ、銭なし弟子なしの身であればそれを作家自らするのか・・・、と感心して見ていた。下地が組み上がった頃には、組合のメンバーと比嘉との間に「いっしょにやってみるか」という連帯感のようなものが芽生え、とうとう作業を手伝うことになった。製作ノートのスケッチには、レリーフが一部大きく立体に、つまり凸状になる構想で、その部分は塑材を支える金属の骨が要る。立体で飛び出すのは米軍の「銃剣とブルドーザー」による基地建設用地強制収用の戦車の前で竦む沖縄の子や、GHQ支給のミルクのガロン缶を抱える東京の子とその缶などだった。沖縄ー東京での、子供たちの目に映る敗戦直後の光景の落差を示していた。作品タイトルは『子供たちの戦後』だったと記憶している。何でも、教員組合からの依頼で、新しく完成する会館のロビー壁面に設置されるという。幸いこっちは金属加工業だ。比嘉が求める骨も容易く作れる。助手の希望者が多く困ったが、話し合いの結果若い久保君に決まった。久保君は数日後の比嘉が来る日に、奥さんを連れてきて比嘉に紹介し、買ってきた比嘉の版画詩集にサインをもらっていた。
垂木を軸組みしてコンパネ=厚いベニヤを、ビス縫いして行く。レリーフと言ってもこういう下仕事があるのだ、銭なし弟子なしの身であればそれを作家自らするのか・・・、と感心して見ていた。下地が組み上がった頃には、組合のメンバーと比嘉との間に「いっしょにやってみるか」という連帯感のようなものが芽生え、とうとう作業を手伝うことになった。製作ノートのスケッチには、レリーフが一部大きく立体に、つまり凸状になる構想で、その部分は塑材を支える金属の骨が要る。立体で飛び出すのは米軍の「銃剣とブルドーザー」による基地建設用地強制収用の戦車の前で竦む沖縄の子や、GHQ支給のミルクのガロン缶を抱える東京の子とその缶などだった。沖縄ー東京での、子供たちの目に映る敗戦直後の光景の落差を示していた。作品タイトルは『子供たちの戦後』だったと記憶している。何でも、教員組合からの依頼で、新しく完成する会館のロビー壁面に設置されるという。幸いこっちは金属加工業だ。比嘉が求める骨も容易く作れる。助手の希望者が多く困ったが、話し合いの結果若い久保君に決まった。久保君は数日後の比嘉が来る日に、奥さんを連れてきて比嘉に紹介し、買ってきた比嘉の版画詩集にサインをもらっていた。
やがて、比嘉とは呑み仲間となって行く。裕一郎!と呼び捨てる語りは信頼と親交の証だと裕一郎は思うことにしているが、下の名を敬称抜きで呼ぶのは比嘉にとっては普通なのだった。製作の五ヶ月間はもちろん、その後も今日に至るまで比嘉は争議中の占拠中社屋の、その工房の日々を大切に思ってくれていた。週に一度か二度だったが、五ヶ月もの間、勤務の関係で主として昼間に通ってきた比嘉は、組合の実情もよく見ていた。 「裕一郎、お前さんと高志は絶妙のコンビじゃ。ワシの受け容れを決めた時も工夫したんじゃろ?」 「工夫?」 「いや、手伝ってくれてる久保君に聞いたよ。いつものように片方が異論を吐く。今回は北嶋さんが消極的意見担当で、と言うとったぞ」 「いつもそうなってしまうんですけど、それは偶然です。」 「じゃから絶妙や言うとるんじゃ。けど、周りはそう見てるし、納得もしとるんじゃ」 「そんな政治屋やないですって」 「三階の壁の落書き、覚えとるで」 「何です?」 「党ならざる者たちによる大規模叛乱と自治・・・。全部拭き取ってるのに、あれだけが遺されているように見えた。最後にある自治というのがええ。」 「ああ、あれはたぶん社長高志が書いたと思いますよ。ぼくには高志のように、党というものと絡む歴史も葛藤もありません」 「ワイ・トラップという社名の由来が、どうもワシには読み解けん。トラップというのは動物を生け捕りにする罠のことじゃが…。Y、や行の始まり音、優しい罠、やっかいな罠、ゆかいな罠、いろいろ考えたがどうも変じゃ。アルファベットで、Y-TRAP。教えてくれんか。あの落書きと通じておると直感しとるんじゃ」 「どうでしょうか・・・知りません。あれも命名者は高志です。Xトラップという、設立時に発注してくれた客先からもらったと聞きましたが・・・」 「そうかのぉ? 文字の謎々じゃろ」
冬、作品製作が終わりかけた頃、作品の前で腰掛けて、差し入れたコーヒーを飲みながら話を聞いた。比嘉は沖縄の戦後ではない「占領下」を生きた時間を語ってくれた。 比嘉は、高卒後嘉手納基地でのバイトなど転々とし、五九年米軍政下のオキナワから、琉球政府の特殊法人である琉球育英会が管轄する「国費・自費沖縄学生制度」で、パスポートを携えて関西の大学に渡航留学した。二十歳を過ぎていた。大阪北部にある沖縄県人会寮に住み九年かけて卒業した。貧乏学生が、汽車と船を乗り継いで長時間と大金をかけての往復は一苦労で、めったに帰れなかったと言い、随分努力して慣れた関西弁だが、言葉の壁などからアルバイトと言っても肉体労働や内職的な軽作業しかなく、学生生活は厳しいものだったという。 「どうじゃ、立派な大阪弁やろ」 五〇年に「琉球諸島米国民政府」(USCAR)が琉球政府という「半自治政府」を作る。USCARは立法院の同意無く法令を公布し、立法院が施行した法令の修正権を有していた。琉球政府行政主席・琉球政府裁判所長官は、六八年屋良朝苗氏が初の公選主席なるまで、USCARによる任命や間接選挙だった。 元々、米軍基地基建設は強制的な土地接収で行なわれ、地主の事前合意・適正補償などの法的基礎なく行なわれた。土地を無くした住民を、軍に関わる仕事、軍人と家族への商品・農産品・サービスの労働力として雇用することを、就業機会を提供していると言っているに過ぎない。知らなかったことが一杯だった。 比嘉は、復帰後何が変わったのか?と言い、返還後の実情も話してくれたが、「自分で考えろ」とでも言うように、口調が訴え調から穏やか調へと変わるのだった。 「まぁ、占領後ずっと去年七八年まで、車がアメリカ式に右側通行だったことに象徴されるように米軍政下やったと言うことじゃ。返還から七年、今はどうか・・・。日本人は実は知っとるんや、何故そうなっっているのかを、その何世紀にも亘る永い琉球と日本の関係史を・・・」と結んだ。もう二十五年になる。 一番印象深い言葉は今も憶えている。その後、比嘉はこう言ったのだ。 「裕一郎、お前さんらは職場を奪われ、こうやってこの職場を占拠して食うや食わずで、ここの小さな空間に居る。沖縄はまるごと奪われているんじゃ。ワシは思うんじゃが、どこかで、お前さんたちとおんなじじゃ」 比嘉はそう言ってくれたが、裕一郎は「あなたがたと、これこれで繋がっている」と言える中身も無く、ただじっと聞いていた。
連載⑲: 『じねん 傘寿の祭り』 二、 ふれんち・とーすと (6)
二、ふれんち・とーすと ⑥
「断腸の想いで売った代金なら、なおのこと早く回収しましょう」 「そうだね、それが入れば保証金払ってもお釣が来る」 「いや、それがなければ保証金払えない、でしょ。現在の持ち金はいくらあるんです?」 「君にぼくの懐具合を洗いざらい全部見せなきゃならないという法でもあるのかね?」 「いえ、細川から回収できない場合、保証金は払えるのか払えないのか、と」 「払えないよ、払えるもんか!六十九万も…。裕一郎君、値切れないかね」 「値切ったところで払えませんよね !」 「君は、人の話の腰を折る。ロマンというものを解さない野暮な男なんだねえ」 ロマンでも何でもいい、何とでも言ってくれ。契約前なら手付金はたぶん戻って来るだろう、しかし契約後では・・・。仕方がない、手付金を棄ててでも、白紙に戻すしかない。 保証金など頭になったのだろうか。家賃タダというのはどういうシステムなのか考えなかったのだろうか。在庫がどれくらい在って、店を埋める品の仕入れは・・・、常駐店員を雇うならどれだけの人件費で・・・、次々と質したい疑問が溢れた。いくつか質問したが要領を得ない。在庫なんか要らない、今自宅に在る品と、都度委託で入手する全国の陶芸家の作品ですぐに埋めて見せる。委託だから、仕入れは発生しない。ゆえに金はいらぬ。売れてから、その分を払えばいいのだ。永く、無名の駆け出しの頃から可愛がり育ててきたんだ。みんな協力するさ、この黒川自然が国際通りに店舗を構えるんだよ。放っときゃせんよ。 有り得ないことだが、文字通りの「売上の一〇%」のみで最低家賃云々がなければ、確かに在庫と委託で維持出来なくはないかもしれない。それでも人手は要るのだが・・・。 話にならない。国際通り案を断念させねばならない。
そうだ比嘉真に説得してもらおうと思いつき、黒川に訊いた。 「黒川さん、沖縄に来て比嘉さんに会いました? 大阪のギャラリーを閉めることになって作品返したきりでしょう、ちょっと挨拶に行きますか? 美枝子さんの話では、去年夏米軍ヘリ墜落の時に電話されたそうですけど・・・」 「あそこは遠いだろう。沖縄は電車がないし、移動はバスだ。彼んとこは確か」 「ぼくが知ってます。以前お邪魔してますし」 「車は便利だねえ。だから、ぼくは車を借りようと言ったんだよ」 電話すると、比嘉はアトリエに居た。 「おう裕一郎、沖縄に居るんやろう?」 「えっ、どうして知ってはるんです?」 「相棒から電話あったよ。裕一郎が二・三ヶ月行くのでよろしくってな」 高志が比嘉に電話していたとは・・・。 高志と裕一郎は、比嘉にとってワンセットだ。今は反戦版画家として有名な比嘉だが、沖縄に帰りドッカと座る前、大阪で夜間高校の教師をしていて、彫刻、正確には彫塑だが、彫塑中心に制作していた。七〇年代が終わろうとする頃、大型のレリーフ作品を依頼されたとのことで、工房を探していた。製作する作品は5M×2Mの大作で、広い場所が必要だ。金が無かった比嘉は困っていた。
 職場占拠して二年目の夏だった。倉庫の片隅を工房空間として貸してもらえないか・・・。労働組合に話を持ってきたのは、比嘉と親しい滋賀の市会議員で、高志・裕一郎とは大学期の知人だった。占拠開始以来、旧会社が使用していた状態のままで荒れ放題の倉庫を、整理すれば空間は作れる。比嘉の作品を多少は知っている裕一郎は話を受けようと考えていた。 高志と裕一郎は、互いに、発議者がもう一方なら、反対ではないにしても発議された提案のリスクを言い不備や足らずを語る。二案が組合の論議の遡上に上り、結果として落ち着くところへ落ち着く。一度たりとも事前に相談や調整などしたことはなかったが、他の者からは、まるで出来レースのように見えたことだろう。 比嘉の要請を受けるには、やや消極的な態度で臨めば実現するかもしれないと考えた。そう踏んで、裕一郎は何とも本心から反れて秩序的な言い分を吐いた。職場占拠中の警備は、いつ占拠解除を目指して物理力が行使さえれるかもしれないとされていて、事実夜間の見張りを交代で配置している。昼間であってもオープンな出入りはいかがなものかと、その警備の面から、もうひとつは作品製作という「創造的」な事態に目を奪われ仕事への集中が疎かにならないか、そこをまずクリアする対策が必要だと、仕事の面から。 高志は、比嘉の創造する心や姿が争議に与えるプラスの影響は計り知れないと力説し、多くが賛同して、比嘉からの要請の受け入れがあっさり決まった。 してやったり・・・、だった。
職場占拠して二年目の夏だった。倉庫の片隅を工房空間として貸してもらえないか・・・。労働組合に話を持ってきたのは、比嘉と親しい滋賀の市会議員で、高志・裕一郎とは大学期の知人だった。占拠開始以来、旧会社が使用していた状態のままで荒れ放題の倉庫を、整理すれば空間は作れる。比嘉の作品を多少は知っている裕一郎は話を受けようと考えていた。 高志と裕一郎は、互いに、発議者がもう一方なら、反対ではないにしても発議された提案のリスクを言い不備や足らずを語る。二案が組合の論議の遡上に上り、結果として落ち着くところへ落ち着く。一度たりとも事前に相談や調整などしたことはなかったが、他の者からは、まるで出来レースのように見えたことだろう。 比嘉の要請を受けるには、やや消極的な態度で臨めば実現するかもしれないと考えた。そう踏んで、裕一郎は何とも本心から反れて秩序的な言い分を吐いた。職場占拠中の警備は、いつ占拠解除を目指して物理力が行使さえれるかもしれないとされていて、事実夜間の見張りを交代で配置している。昼間であってもオープンな出入りはいかがなものかと、その警備の面から、もうひとつは作品製作という「創造的」な事態に目を奪われ仕事への集中が疎かにならないか、そこをまずクリアする対策が必要だと、仕事の面から。 高志は、比嘉の創造する心や姿が争議に与えるプラスの影響は計り知れないと力説し、多くが賛同して、比嘉からの要請の受け入れがあっさり決まった。 してやったり・・・、だった。
連載⑱: 『じねん 傘寿の祭り』 二、 ふれんち・とーすと (5)
二、ふれんち・とーすと ⑤
 出来高による家賃は売上の一〇%だ。ポス・レジになっていて集中管理、もちろんそれはレンタルで、電気代は坪数に比例して各テナンントが応分に負担する。普段が坪千円前後、冷房使用季には倍。共用部分、通路やトイレの電気代も同じだ。かつ、売上の多少に拘らず、設定されている最低家賃は坪六千円だった。契約面積は、通路の半分も含まれていて二十三坪。要するに、売上が多ければパーセントで、少なくても最低坪計算額はいただきますよ、ということなのだ。 売上百万という、聞いていた売上水準からは無理だが、ひょっとしたら可能かもしれない数字を頭に描き巡らす。賃料は売上の一〇%十万が最低家賃に届かないので、坪六千円で再計算。すると、十三万八千円、光熱費は平均で三万四千五百円、商品原価は黒川が言うには概ね七割。これだけで、計八十七万二千五百円。店に立つ常駐者の人件費・交通費・通信費・送料・包装費・思いつかないが色々あろう諸雑費、あっそれからポス・レジのレンタル料、それらを加えると完全に赤字、無理だ。 さらに食費用の保証金が坪三万、つまり六十九万ということも分かった。無理だ。
出来高による家賃は売上の一〇%だ。ポス・レジになっていて集中管理、もちろんそれはレンタルで、電気代は坪数に比例して各テナンントが応分に負担する。普段が坪千円前後、冷房使用季には倍。共用部分、通路やトイレの電気代も同じだ。かつ、売上の多少に拘らず、設定されている最低家賃は坪六千円だった。契約面積は、通路の半分も含まれていて二十三坪。要するに、売上が多ければパーセントで、少なくても最低坪計算額はいただきますよ、ということなのだ。 売上百万という、聞いていた売上水準からは無理だが、ひょっとしたら可能かもしれない数字を頭に描き巡らす。賃料は売上の一〇%十万が最低家賃に届かないので、坪六千円で再計算。すると、十三万八千円、光熱費は平均で三万四千五百円、商品原価は黒川が言うには概ね七割。これだけで、計八十七万二千五百円。店に立つ常駐者の人件費・交通費・通信費・送料・包装費・思いつかないが色々あろう諸雑費、あっそれからポス・レジのレンタル料、それらを加えると完全に赤字、無理だ。 さらに食費用の保証金が坪三万、つまり六十九万ということも分かった。無理だ。
ビル側の設定は無理難題ではない。どのテナントも同じ契約で入っているのだ。頭が真っ白になって、裕一郎は事態を白紙に戻す術を必死に考えていた。 黒川が重ねて失言しないようにと、ここは一旦引上げることにした。 「オーナー! 大丈夫ですか?お顔が冴えませんよ。病院の先生が、まだ早いと仰ったのに・・・。今日は戻りましょう・・・」 「何を言ってるのだ。ぼくは大丈夫だ、君こそ顔が火照っているのかい?真っ赤だぞ!」 ビル事務所の担当者が心配そうに見ている。黒川を抱えるようにして、その場を去った。
それからが、大変だった。喫茶店に陣取り、まず保証金のことを訊いた。 「そもそも保証金あるんですか?」 「保証金というのは戻ってくる金だ」 「いや、それは出る時の話であって、店を続ける限り手を付けられないんですよ。積んでおく金です。続けるんでしょ! だから預けっ放しです。あるんですか?保証金」 「細川という同業者に、タロウの七十五万円の大皿を二点売ったんだが、それの代金を回収するよ」 「いつ売ったんです?」 「沖縄へ来てすぐだよ。」 「もう半年じゃないですか。催促してるんですか?これまで・・・」 「会えばいつも言ってるよ、早く払ってくれと。もう払うだろう。いつも今月末には払うって言うんだよ。困った奴だ」 「で、タロウって誰です」 「えっ、知らないのかい? 人間国宝の玉城太郎だよ。これだから素人は困るんだよ。タロウの大皿は、前期・中期・後期とあって、西欧から、次いで大正・昭和初期のヤマトから受けた影響を超えて、後期のものはタロウが琉球独自タロウ独自の釉薬技法に辿り着いた、云わばアイデンティティの復権に至った逸品だ。沖縄へ来て、まだビジネスが軌道に乗る前に、生活の為に断腸の想いで細川に売ってしまった大皿は、そのタロウが独自技法に辿り着く直前の、ごく短期間の作品にしか視られない迷い・葛藤・模索が滲み出ていて、復権が仄見える、全国のタロウ愛好家から羨望の眼差しで視られている作品なんだ」 黒川の話は終わりそうにない。なお先を語り始めていた。タロウを語る目は輝いていて、ほとんど涙ぐんでさえいる。だが、この話に異論を唱えてはいけない。軌道に乗る前って、じゃあ今は軌道に乗っているのですか、などと突っ込んではいけない。
連載⑰: 『じねん 傘寿の祭り』 二、ふれんち・とーすと (4)
二、ふれんち・とーすと ④
物件があるビルは国際通りに面してはいない。面したビルの後方にドンと凹んだビルだった。だから、ビルの入口は、国際通りに直角に交差する路地に在る。若者や観光客向けの派手な四階建てのビルだった。平日とはいえ、そして昼食時だとはいえ、ビル内は人が疎らだった。それだけで判断はできない。夜や休日、観光シーズン、全てを観察しないことには・・・。ビルには、CDショップ、若者向けのファッション店、ジーンズ店、女性下着店、安物のアクセサリー店、化粧品店などがあったが、各フロアに空店舗が目立つ。  黒川が案内した「物件」は、四階の隅に在った。四階には特に空店舗が多く、半分くらいしか稼動していない。空店舗の中から、この物件を選択した理由が分からない。 黒川の取扱い商品、顧客の層、長時間話し込み店主と意気投合してじっくり吟味して買う…そういう商いのカタチに絶対合わない。この場所はそれらの要素からはむしろ敬遠される派手さ・喧騒・軽薄さに溢れている。 「どうして、この場所このビルこの区画なんですか?」 「フフフン、見てみなさい。他は全部フロアの中央部だろう、四面がオープンだ。従って、高価な品を管理するのに大変だ。その点、これは後ろが壁、三角形だから通路に面しているのは一面。管理し易いじゃないか」 「物件」は売場通路に沿って斜めになった区画だ。ビル自体が、土地の関係で一面が斜めになっている。通路配置を考慮したレイアウトの結果、斜め構造の一面は各フロアとも同じ区画割に違いない。バックが躯体壁面、右側が三角形の鋭角の頂点、左がトイレへ通じる通路を仕切る壁面だった。バックの壁が約十八M、左の壁面が約六M。五十四㎡、約十七坪。広い。 営業時間はどうなのか、商品管理も何もそもそも誰が店に常駐するのか? 黒川から聞いていた話では「百貨店の催事、沖縄各地の展示会に向けた営業、成約時の準備、全国の陶芸家・画家・版画家などの確保と品物の収集、その開梱作業、終了した後の品物の荷造り、その返送、金銭管理・集計と目が回るほど忙しいんだよ」だった。その忙しさが話半分いや四分の一であっても、ユウくんとの日常生活から判断しても、ニトロを離せない健康状態からしても、黒川は連日遅くまで店に居ることは出来まい。ならば、ギャラリー・ショップの常駐は誰がするのか?まさか俺が? それは聞いていないし、無理だ。商品知識も無い、ずっとここに居るわけでもない。 「ここは、若者向けのファッション・ビルです。焼物陶芸や絵画版画のギャラリーとしてはどうでしょうか? それなりに金もある、陶芸品に興味がある、黒川さんを支援したい、そういう人が来ますかね? ぼくは、ここは違うと思いますよ。大阪で構えていたような場所がいいんじゃないですか?」 「そんなことはない。第一、家賃がタダなんだ。ぼくの構想から言えばこんないい条件は二度とないよ。それにすでに契約している。三日前契約は済ませたんだ。今日、手付金を払うんだ」
黒川が案内した「物件」は、四階の隅に在った。四階には特に空店舗が多く、半分くらいしか稼動していない。空店舗の中から、この物件を選択した理由が分からない。 黒川の取扱い商品、顧客の層、長時間話し込み店主と意気投合してじっくり吟味して買う…そういう商いのカタチに絶対合わない。この場所はそれらの要素からはむしろ敬遠される派手さ・喧騒・軽薄さに溢れている。 「どうして、この場所このビルこの区画なんですか?」 「フフフン、見てみなさい。他は全部フロアの中央部だろう、四面がオープンだ。従って、高価な品を管理するのに大変だ。その点、これは後ろが壁、三角形だから通路に面しているのは一面。管理し易いじゃないか」 「物件」は売場通路に沿って斜めになった区画だ。ビル自体が、土地の関係で一面が斜めになっている。通路配置を考慮したレイアウトの結果、斜め構造の一面は各フロアとも同じ区画割に違いない。バックが躯体壁面、右側が三角形の鋭角の頂点、左がトイレへ通じる通路を仕切る壁面だった。バックの壁が約十八M、左の壁面が約六M。五十四㎡、約十七坪。広い。 営業時間はどうなのか、商品管理も何もそもそも誰が店に常駐するのか? 黒川から聞いていた話では「百貨店の催事、沖縄各地の展示会に向けた営業、成約時の準備、全国の陶芸家・画家・版画家などの確保と品物の収集、その開梱作業、終了した後の品物の荷造り、その返送、金銭管理・集計と目が回るほど忙しいんだよ」だった。その忙しさが話半分いや四分の一であっても、ユウくんとの日常生活から判断しても、ニトロを離せない健康状態からしても、黒川は連日遅くまで店に居ることは出来まい。ならば、ギャラリー・ショップの常駐は誰がするのか?まさか俺が? それは聞いていないし、無理だ。商品知識も無い、ずっとここに居るわけでもない。 「ここは、若者向けのファッション・ビルです。焼物陶芸や絵画版画のギャラリーとしてはどうでしょうか? それなりに金もある、陶芸品に興味がある、黒川さんを支援したい、そういう人が来ますかね? ぼくは、ここは違うと思いますよ。大阪で構えていたような場所がいいんじゃないですか?」 「そんなことはない。第一、家賃がタダなんだ。ぼくの構想から言えばこんないい条件は二度とないよ。それにすでに契約している。三日前契約は済ませたんだ。今日、手付金を払うんだ」
黒川が勇んでビルの事務所へ向かうので、付いて行くしかない。黒川は何度か面識があるのか担当者と親しく挨拶を交わし、早々と手付金一〇万円を渡してしまった。重要事項説明も三日前に受けているのだ。 こういうことだった。家賃無料というのは売上の出来高制ということで、単に固定ではないという意味だった。もちろん、最低家賃は設定されている。裕一郎は、無期懲役というのは終身刑ではなく期間を定めない刑である、そんなことを思い浮かべていた。
連載⑯: 『じねん 傘寿の祭り』 二、 ふれんち・とーすと (3)
二、ふれんち・とーすと ③
黒川が「物件を案内しようか?」と乗り込んだ助手席で、右だ左だ真直ぐだと指示を出す。園へ来るとき走った道だ。 「来るときに走った道ですね」 「分かるのかね、勘がいいねえ。さすがドライバーだ。この道はひろしがバスで通る道じゃないんだ。ひろしが使っている路線はまわり道をしやがる。うちから園に行くには、本来この道が正しい道なのだ。」 正しいとは黒川らしい言い分だが、まわり道の側にも言い分はあるだろう。公共機関や商店街、住居密集地を通れば、結果としてまわり道になるのだろう。今走っている道の両側には、それらしき気配は無かった。 ユウくんのバス通園は、自宅最寄のバス停から園直近のバス停へという路線を選択している。それはこの道ではなくグルリと遠回りとなる路線だ。バスに乗っている時間は五〇分近くにもなるという。遠まわりにならない路線、つまり今走っている道、それは園側のバス停が園から一キロも離れた所にある。黒川は迷ったが、その一キロの道の危険を考え乗車時間五〇分近いまわり道になる路線を選択したという。バス停から園までの一キロの危険は、道が狭く、車とすれ違いう際の危険、特に雨の日の傘による危険と、同じく雨の日に車がハネ上げるドロ水だと言う。選択した路線のバス停は園の目の前だ。なるほど、選択は賢明だ。
黒川の懸念を余所に、ユウくんはバス通園を楽しんでいた。交通機関に乗るのが大好きなのだ。裕一郎も昔、祖母が住む父親の実家へ向かう時に乗る、大阪梅田から近鉄上六までのタクシー乗車を楽しみにしていた。そこへ行ったところで、小遣い銭にありつける以外楽しいことが待っている訳ではない老人の住まいになど行きたがらない幼児を、父母はそのタクシー乗車を餌にして連れ出していた。孫を連れて行かないことには、親たちも間が持たなかったのだと今では理解できる。 ともかくユウくんは長時間のバス通園を嫌がらなかった。ユウくんは苦にしないどころか、バスに乗っている時間が長ければ長いほど有り難いとさえ思っていたようだった。そのもっとも大きな理由に黒川が気付くのは、裕一郎が去る真夏になってからだ。 ユウくんも男なのだ。人の行動決定理由には、自覚せざる様々な要因が介在している。学者でも、聖人でも、高名な作家でも、それは変わらない。自分自身にもそれはある。黒川さん、あなたはどうです?
 国際通りの裏手の駐車場に車を停めた。通りで沖縄そばとジューシー半ライスにゴーヤチャンプルの小盛りが付いたサービス・ランチを食べた。代金を払おうとすると、黒川が「朝夕は条件に入っているが、昼飯は当然自前だね。まぁワリカンにしておくか」と言う。そうなのか?と思ったが、意地で「今日はぼくが出しましょう。よろしく料です」と二人分千六百円出した。黒川は「そうかね。では遠慮なくいただいとくよ」と爪楊枝を銜えて悠然と先に出て行った。 店を出た黒川が国際通りをスイスイ歩いて行く。 「物件を探すんですよね?」背中に声掛けすると、歩を止めて振り向いて言う。 「任せなさい。黙ってついて来なさい。君が来る前に素晴らしい物件をすでに契約しているんだ」 契約? 気になるが間もなく真相が分かると思って無言でいた。 「裕一郎君、驚くなよ! 何と家賃はタダなんだよ、スゴイだろう」 「タダ? 信じないとは言いませんが、他に条件があるでしょう何か。ほんとうにタダなんですか、有り得ないことです。」 「売上の一〇%ということだ。売上げが全くなきゃ、タダだろう? まあ、ついて来なさい。もうそこだよ」
国際通りの裏手の駐車場に車を停めた。通りで沖縄そばとジューシー半ライスにゴーヤチャンプルの小盛りが付いたサービス・ランチを食べた。代金を払おうとすると、黒川が「朝夕は条件に入っているが、昼飯は当然自前だね。まぁワリカンにしておくか」と言う。そうなのか?と思ったが、意地で「今日はぼくが出しましょう。よろしく料です」と二人分千六百円出した。黒川は「そうかね。では遠慮なくいただいとくよ」と爪楊枝を銜えて悠然と先に出て行った。 店を出た黒川が国際通りをスイスイ歩いて行く。 「物件を探すんですよね?」背中に声掛けすると、歩を止めて振り向いて言う。 「任せなさい。黙ってついて来なさい。君が来る前に素晴らしい物件をすでに契約しているんだ」 契約? 気になるが間もなく真相が分かると思って無言でいた。 「裕一郎君、驚くなよ! 何と家賃はタダなんだよ、スゴイだろう」 「タダ? 信じないとは言いませんが、他に条件があるでしょう何か。ほんとうにタダなんですか、有り得ないことです。」 「売上の一〇%ということだ。売上げが全くなきゃ、タダだろう? まあ、ついて来なさい。もうそこだよ」
連載⑮: 『じねん 傘寿の祭り』 二、ふれんち・とーすと (2)
二、ふれんち・とーすと ②
翌朝、先に目が覚てめすぐに台所に下りた。冷蔵庫を漁ると、野菜室にネギ・キャベツ・レモンなどがある。ソーセージ・未開封のハムがあり、ドアに購入日シールを貼った玉子がある。昨夜黒川が「パン食だ」と言ったので、パンに合うものをと思い、スクランブル・エッグとソーセージ炒めとサラダを作ろうとキャベツを刻んでいると、ユウくんがやって来た。「朝にごはん作るの?」と訊く。ん? 裕一郎が作ったサラダには、スクランブル・エッグを変更して用意した薄焼き玉子を細く切って混ぜてある。オイルとレモンに塩・コショー、隠し味に味醂と醤油を半サジ加え作ったドレッシングを、黒川は絶賛してくれた。 三人で食べ始めて、キャベツを切っている姿を見ただけでユウくんが「朝ごはん作るの?」と訊いて来た理由が判った。「朝はパン食だ」と言うのは「パンだけだ」という意味だったのだ。普段はパンにジャムまたはバター、ときに「漬物」を挟んで喰うという。調理作業が、たとえ刻むだけでもあれば、それは「ごはん」を「作る」時なのだ。なるほど・・・。
近くのバス停まで一人で行けるユウくんを送り出すと、黒川が「北嶋君、ついてきなさい」と着替え始めた。 ギャラリー候補物件を回るにも、百貨店や同業者を訪ねるにも、車が要る。黒川はバスを乗り継いでそれをしていた。北嶋君が来た以上は車確保だな、というわけでレンタカー屋に向かった。どんな車であろうが、この際安いものにこしたことはない。しかも、沖縄の狭い生活道路・・・、だから軽であるべきだ。しかも最新の割高のものは不要、旧型で充分。が、黒川は車のデザインに凝って、ああだこうだと言い始める。反論すると挙句に言った。 「金を出すのは君じゃないんだ」 「いえ誰が出そうが無駄なものは無駄なんです」 少々険悪な空気が流れたが、軽の旧式のものを月極めで契約して事なきを得た。早速、事前の話の通り候補物件を見て回るのかと思いきや、「ひろしにが通う園を案内しておく」と来た。車のデザインに拘っていたのはこれだったのか・・・。ユウくんが通う「ひかり園」へ向かった。 園ではちょうど園自家製のパンを袋詰めしているところで、黒川は作業室で通所者といっしょに作業していた指導員を呼び出した。 「ぼくのビジネスの右腕となる大阪から来た北嶋君だ。雨の日だとか帰宅が急がれる場合には、ここへも車で走って来ることになる。まあ、よろしく」 いや、やってもいいがユウくんの送迎など聞いてないぞ。 パンは、役所ロビーの常設店で販売したり、役所の職員が一定量買ってくれるという。指導員が、園を案内してくれた。指導員が苦笑を堪えているように見えた。真新しい行き届いた園で、ユウくんも生き生きと作業している。三十分で退散した。園の駐車場へ歩くと、作業が一段落したのか指導員が気を利かせ促してくれたのか、ユウくんが追ってきた。正午近い太陽が真上に輝いている。 「これ、うちの車?」 「そうだよ。これからは、北嶋さんがときどき送ってくれるぞ。嬉しいねぇ~」  「ぼくは、バスがいいよ」 意外な反応だった。黒川がキョトンとしている。 ユウくんの言葉に、幼き者が時に発揮する遠慮がちな気遣いだけではない、別の意志が感じ取れた。ユウくんの口調がハッキリしていたからだ。 だが、裕一郎はそれが何なのか掴めたわけではなかった。
「ぼくは、バスがいいよ」 意外な反応だった。黒川がキョトンとしている。 ユウくんの言葉に、幼き者が時に発揮する遠慮がちな気遣いだけではない、別の意志が感じ取れた。ユウくんの口調がハッキリしていたからだ。 だが、裕一郎はそれが何なのか掴めたわけではなかった。
連載⑭: 『じねん 傘寿の祭り』 二、ふれんち・とーすと (1)
二、ふれんち・とーすと ①
頬にまだ生クリームが付いているユウくんが、冷蔵庫からグレープ・フルーツ・ジュースを出そうとして言う。 「あっ、まだ、もうひとつ別のケーキがあるヨ」 カンケイ会から、帰宅したユウくんの第一声だった。 近くの食堂、親子が頻繁に行っているらしい民芸店兼喫茶店兼レストランである黒川が言う「食堂」で、歓迎会は行なわれた。黒川に言わせれば「親しげに世話を焼いて来るんだよ。外で喰う時は行ってやらにゃあね」であるその「食堂」は、黒川家から徒歩三分だ。 「食堂」が最後に出してくれたケーキを頬張りながらユウくんが、黒川がトイレに立ったとき教えてくれていた。週に四~五度はここで夕食を摂ること。黒川の帰宅が遅い時は、閉店時刻まで独りでここで待つこともあること。そんな時は店のオバサンがケーキを出してくれること。だから、黒川の帰宅が遅い日も嫌ではないこと。園が休みの土曜・日曜に黒川が出かける場合には、五百円玉を持ってここへ昼ごはんを食べに来ること。黒川が言う「外で喰う時は行ってやらにゃあ」は実態と全く違うのだ。ここのオバサンは二人の生活をサポートしているのだ。 今夜は、黒川が店のオバサンに「大阪から来た北嶋君だ。ぼくのギャラリー開設やビジネスの構想を手伝ってくれるんだ」「今夜は彼の歓迎会なんだ」と言うので、黒川と裕一郎には飲み物がサービスされ、ユウくんにはケーキが振舞われたのだった。 カンケイ会では黒川が泡盛の水割りを三杯呑み、裕一郎もかなり呑んで、黒川の「構想」に花が咲いた。 ユウくんはそうした空気の余韻を肌で感じ黒川の機嫌を推し量ってか、ジュースを飲みながら冷蔵庫から箱を出した。 「チチ、これも食べていい?」 「だめだよ、甘いものは一日一回だ」 ユウくんが恨めしげにテーブルに置いた箱をじっと見ている。黒川が訊ねた。 「買ったのかね? 誰かからの貰い物かね?」 「買うたんですよ。ぼくからのお土産です」 黒川が箱を手に取り、しげしげと見ている。 「ならいい。けどぼくは喰わん。これは、松山の名物じゃないか! 誰かとおんなじで、名称と中身が違うまがい物だ。それは、美味い美味くない以前の問題なんだよ。嫌いだねぼくは。明日、ひろしと君が喰えばいい」 黒川は箱を冷蔵庫に戻し「ひろし、あした帰ってからだぞ」と言って、来客用和室に向かい、何やら仕事を始めた。
「チチはおベンキョウ」とユウくんが教えてくれる。 「毎日?」 「うん、そうだよ。夜ぼくがおしっこに降りて来ても、まだしてる時もあるよ」 ユウくんが風呂に向かった。和室に行って黒川に訊いた。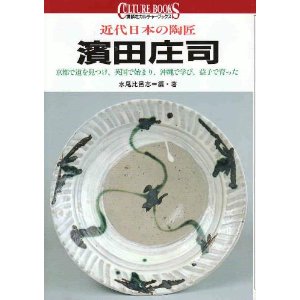 「何のお勉強ですか?」 「いや、通信の原稿だよ」 見ると、人差指一本でポータブルの古いワープロを打っている。訊けば、五百名ほどある馴染客名簿から、沖縄内百強を主に計百五十人宛に、月一回の通信を出しているという。参考資料を広げ、写真を選び、原稿版下を作っている。ワープロで打ち出した記事を鋏で切って貼り付けて版下を作っているのだ。過去のものを見せてもらうと、見事な構成だった。A3サイズを折り畳み、A4サイズ両面四頁に仕上がったそれらは、表紙と最終頁がカラーの「自然通信」と名付けられた立派な通信だ。記事を書き、ワープロを打ち、記事を切り貼りして版下を構成し、たぶんカラー・コピーに走り折込までを一人でする。封書詰めをして出す。それを毎月一人でして来たのか。その労力に頭が下がる。 「黒川さんワープロ打てるんですね」 「美枝子の仕事だったが、仕方がない、ぼくがしてるよ指一本で・・・。あいつが居ないからといって止めれば人に笑われる。それは嫌だね」 つい、「ワープロだけでも、ぼくがしましょうか?」と言いそうになったが、黒川の大切な仕事を奪うことになると理由付けして思い留まった。 「表紙と最後の頁はカラーですけど、カラー・コピー代も馬鹿になりませんね。一枚八十円でしょ。一五〇セット裏表で三〇〇枚、二万四千円」 「印刷に出すより安いじゃないか。それにね裕一郎君、観察が雑だねぇ。裏はカラーじゃない。白黒だ!白黒は一枚一〇円だぞ。」 過去の記事には「千利休と秀吉」「浜田庄司と沖縄」「比嘉真の叫び」「タロウにおける琉球の復権」「青磁・白磁の源流」などの標題があり、いずれ読もうと思わせるものだ。黒川の言い分が詰まっているのだろう。宛名書きも「客に失礼だよ」と手書きしているとのことだった。パソコンを扱えて写真も添付して一斉送信かプリントアウトすれば、労力は半減どころか二〇分の一だ。 「北嶋さーん、お風呂空いたよ」とユウくんの声が響いた。風呂に向かう前に「明日の朝食はぼくが作りましょうか?」と問うと、黒川は「それには及ばん、朝はパン食だ」と答えた。
「何のお勉強ですか?」 「いや、通信の原稿だよ」 見ると、人差指一本でポータブルの古いワープロを打っている。訊けば、五百名ほどある馴染客名簿から、沖縄内百強を主に計百五十人宛に、月一回の通信を出しているという。参考資料を広げ、写真を選び、原稿版下を作っている。ワープロで打ち出した記事を鋏で切って貼り付けて版下を作っているのだ。過去のものを見せてもらうと、見事な構成だった。A3サイズを折り畳み、A4サイズ両面四頁に仕上がったそれらは、表紙と最終頁がカラーの「自然通信」と名付けられた立派な通信だ。記事を書き、ワープロを打ち、記事を切り貼りして版下を構成し、たぶんカラー・コピーに走り折込までを一人でする。封書詰めをして出す。それを毎月一人でして来たのか。その労力に頭が下がる。 「黒川さんワープロ打てるんですね」 「美枝子の仕事だったが、仕方がない、ぼくがしてるよ指一本で・・・。あいつが居ないからといって止めれば人に笑われる。それは嫌だね」 つい、「ワープロだけでも、ぼくがしましょうか?」と言いそうになったが、黒川の大切な仕事を奪うことになると理由付けして思い留まった。 「表紙と最後の頁はカラーですけど、カラー・コピー代も馬鹿になりませんね。一枚八十円でしょ。一五〇セット裏表で三〇〇枚、二万四千円」 「印刷に出すより安いじゃないか。それにね裕一郎君、観察が雑だねぇ。裏はカラーじゃない。白黒だ!白黒は一枚一〇円だぞ。」 過去の記事には「千利休と秀吉」「浜田庄司と沖縄」「比嘉真の叫び」「タロウにおける琉球の復権」「青磁・白磁の源流」などの標題があり、いずれ読もうと思わせるものだ。黒川の言い分が詰まっているのだろう。宛名書きも「客に失礼だよ」と手書きしているとのことだった。パソコンを扱えて写真も添付して一斉送信かプリントアウトすれば、労力は半減どころか二〇分の一だ。 「北嶋さーん、お風呂空いたよ」とユウくんの声が響いた。風呂に向かう前に「明日の朝食はぼくが作りましょうか?」と問うと、黒川は「それには及ばん、朝はパン食だ」と答えた。
連載⑬: 『じねん 傘寿の祭り』 一、 チヂミ (9)
一、 チヂミ ⑨
裕一郎は、その後高志と当然仕事で何度も顔を合わせたが、亜希のことには触れていない。介入はまるで自身の家庭崩壊を辿るようなことでしかないと思ったし、何よりも、高志が亜希に心奪われた理由がよく解かったからだ。 一週間後、亜希は仕掛りの現場を後輩へ丁寧に引継ぎ、一身上の事情によりと告げて退社して行った。余りの素早さに驚いたが、高志が自らスパッと身を処さない経過に先行きを確信したのか、高志とのしたくも無い駆け引き、妻とのドロ試合など「キャリア」にならないと考えたのか…。 裕一郎は、その行動をアッパレと思った。もちろん裕一郎には何の連絡もなかった。 元居たNGO団体に戻ったとか、沖縄に向かったとか噂されたが、亜希の交友関係は社内の誰も知らず、年が明けた頃にはもう亜希の話題は出なかった。
 黒川からの誘いを何度も受け沖縄へ行こうかと思い始めていた。拾ってもらいながら三年にも届かず去ることははばかられたが、三月末とうとうノザキの野崎氏に願い出た。それを伝え聞いた高志は一応慰留したが、それは形式的なものだった。 一女性社員の退社が、例え自身との私的な関係に由来しているとしても、それが裕一郎が職場を去る理由に重なると、高志が考えるのは奇妙ではある。裕一郎が、自分の撤退と亜希のことが関連しているだろうなと自覚するのも同様だ。 何故だろう。その奇妙をむしろ当然だと思ってしまう六十近い男が二人、若い娘が遺して行ったある鮮やかさに支配されて向かい合っていた。 「秋に松下君が辞める前、逢うたんか? 何か言うてたか?」 「いや。現場帰りに呑んだけど何も言うてなかったぞ。なんで?」 「そうか。そんな気がしたんや」 高志のデスクと社員のデスク群との間の壁面に、コルクボードがあって、様々な連絡事項が貼られている。資格試験の講習会、新入社員歓迎会・・・。隅に絵葉書がピン止めされている。松下さんより!と矢印を描いた紙が横に貼ってあった。 「見てもええかな?」 「ああ・・・。辞めた直後、チーム宛に来たらしい。何ヶ月にもなるのに、連中が外し忘れとるんや。瀬戸内海の写真やな、消印は下関や。携帯電話の番号もアドレスも変わっていて繋がらないらしい」 手に取って、絵写真の裏を見ると、宛名欄の下半分にチーム員四人のニックネームがあって、その一人一人への短い激励とアドバイスが書いてある。寝過しが貴方のホントの力量を半減させていると思う、現場に足を運べば今以上に人は動いてくれるはず、発注遅れは結果としてと言う以前に元々現場軽視なんです、連日事務所に遅くまで残っているのは決して誇るべきことではありません、などとあって、最後の行にこうあった。 私? 『ひと夜秘め独り往く朝霧あさし身捨つるほどの恋路はありや』 高志が「そんな気がしたんや」と言った根拠は分かっていたが、答えようもない。 「松下さん、誰かと別れたんか?」 「心当たりないな・・・。社員のプライベートは知らん」 「パロディと言うか、これ本歌取りやな。本歌作者は笑うてるやろうけど、これは相手を責めるというのではなく、精一杯、自分と相手両方と言うか、関係全体を相対化しようと真面目に振り返っているよな」 「・・・・・・」 「高志。得難い人が辞めたな」 「・・・・・・・。黒川さんを手伝うって? 二度ほど彼から焼物を買うたことがある。大変やぞ、あのジジイ」 「ああ分かってる。まぁ短期間やし、沖縄には迷惑やろうが、癒し?リフレッシュ?」 「裕一郎、大阪に帰ったら、戻って来てもええんやぞ。場所は用意する」 声を出さず、片頬だけ崩して返した。
黒川からの誘いを何度も受け沖縄へ行こうかと思い始めていた。拾ってもらいながら三年にも届かず去ることははばかられたが、三月末とうとうノザキの野崎氏に願い出た。それを伝え聞いた高志は一応慰留したが、それは形式的なものだった。 一女性社員の退社が、例え自身との私的な関係に由来しているとしても、それが裕一郎が職場を去る理由に重なると、高志が考えるのは奇妙ではある。裕一郎が、自分の撤退と亜希のことが関連しているだろうなと自覚するのも同様だ。 何故だろう。その奇妙をむしろ当然だと思ってしまう六十近い男が二人、若い娘が遺して行ったある鮮やかさに支配されて向かい合っていた。 「秋に松下君が辞める前、逢うたんか? 何か言うてたか?」 「いや。現場帰りに呑んだけど何も言うてなかったぞ。なんで?」 「そうか。そんな気がしたんや」 高志のデスクと社員のデスク群との間の壁面に、コルクボードがあって、様々な連絡事項が貼られている。資格試験の講習会、新入社員歓迎会・・・。隅に絵葉書がピン止めされている。松下さんより!と矢印を描いた紙が横に貼ってあった。 「見てもええかな?」 「ああ・・・。辞めた直後、チーム宛に来たらしい。何ヶ月にもなるのに、連中が外し忘れとるんや。瀬戸内海の写真やな、消印は下関や。携帯電話の番号もアドレスも変わっていて繋がらないらしい」 手に取って、絵写真の裏を見ると、宛名欄の下半分にチーム員四人のニックネームがあって、その一人一人への短い激励とアドバイスが書いてある。寝過しが貴方のホントの力量を半減させていると思う、現場に足を運べば今以上に人は動いてくれるはず、発注遅れは結果としてと言う以前に元々現場軽視なんです、連日事務所に遅くまで残っているのは決して誇るべきことではありません、などとあって、最後の行にこうあった。 私? 『ひと夜秘め独り往く朝霧あさし身捨つるほどの恋路はありや』 高志が「そんな気がしたんや」と言った根拠は分かっていたが、答えようもない。 「松下さん、誰かと別れたんか?」 「心当たりないな・・・。社員のプライベートは知らん」 「パロディと言うか、これ本歌取りやな。本歌作者は笑うてるやろうけど、これは相手を責めるというのではなく、精一杯、自分と相手両方と言うか、関係全体を相対化しようと真面目に振り返っているよな」 「・・・・・・」 「高志。得難い人が辞めたな」 「・・・・・・・。黒川さんを手伝うって? 二度ほど彼から焼物を買うたことがある。大変やぞ、あのジジイ」 「ああ分かってる。まぁ短期間やし、沖縄には迷惑やろうが、癒し?リフレッシュ?」 「裕一郎、大阪に帰ったら、戻って来てもええんやぞ。場所は用意する」 声を出さず、片頬だけ崩して返した。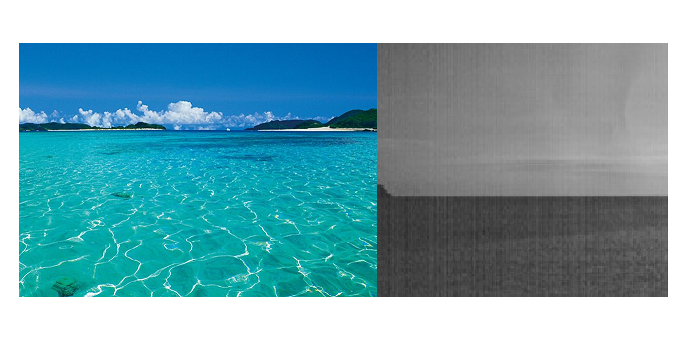
高志の背中の向こうのモノクロ映像には、墨絵薄闇の海と寄せて返す仄白い波が見える。映画の場面転換法ワイプのようにそれを追い出すカラー画面には、澄んで輝く空の下、緑の島とコバルト・ブルーの海が広がって行く。 噂を聞いていたからか、亜希が沖縄に居るような気がしていた。
(一章 チヂミ 終)
連載⑫: 『じねん 傘寿の祭り』 一. チヂミ (8)
一、 チヂミ ⑧
あれから二年と少し。今、亜希は若い男女社員四人を部下に持つチーム・リーダーとなっている。人が時として迷い込む不本意な些事に翻弄されることなどなく、きっと仕事にプライベートに二十代最後の充実した時間をテキパキと送っているだろうと思って来た。その後何度も仕事をしたが、呑むのはその時以来もう何度目だろう。その多くは現場関係の連中も居て二人ではなかったが・・・。現場でも呑む場でも「男前」を崩すことなど決してなかった亜希の迷路など思ってもみなかった。 最終電車前に合わせた閉店時間だ。最後まで騒いでいた文化祭打上げ組も帰った。レジに進もうとして、皿に数片残されたチヂミが目に入った。いつぞやは、亜希は残さず食べた。その夜より本場風で美味いチヂミだったが、チヂミ自身は残されたことに納得しているように見える。 亜希を送って駅へ向かうと、駅前の広場にラーメンの屋台が出ている。 さっき黒川一家の送別会に最後にやって来た、教師だという若い夫婦が仲睦まじく木の長椅子に腰掛けてすすっていた。あの後、黒川節を延々と聞かされたのだろう。軽く会釈して過ぎた。 「キャリアの話ですけど、あれ、あの時は胸に沁みたんですよ、ほんとに・・・。けれど、最近の私、そんな感覚失ってるんです。仕事をこなしているだけみたいな、どうでもいいやみたいな」 「・・・・・・」 亜希、それはぼくのことだ、「こなしてるだけ」「どうでもいいや」。 「最近の私」は「最近の北嶋さん」と聞こえて来るのだった。 「北嶋さん。あの時のキャリアにひとつ大切な要素が抜けてません?」 「ん? 何」 「年齢! 残念ながら人間は歳を取るんです。これお互いですけど」 「・・・・・・残念ながらではなく、『幸いなことに』と開き直るしかないね」 そうは返したが、階段を上りながら思った、その通りだと。人が早くに識っている事柄に歳を重ねてから気付くというのは、単に不誠実な半生の証しでしかない、と。それがどんなキャリアになると言うのだ・・・。 券売機で亜希の切符を買った。
さっき黒川一家の送別会に最後にやって来た、教師だという若い夫婦が仲睦まじく木の長椅子に腰掛けてすすっていた。あの後、黒川節を延々と聞かされたのだろう。軽く会釈して過ぎた。 「キャリアの話ですけど、あれ、あの時は胸に沁みたんですよ、ほんとに・・・。けれど、最近の私、そんな感覚失ってるんです。仕事をこなしているだけみたいな、どうでもいいやみたいな」 「・・・・・・」 亜希、それはぼくのことだ、「こなしてるだけ」「どうでもいいや」。 「最近の私」は「最近の北嶋さん」と聞こえて来るのだった。 「北嶋さん。あの時のキャリアにひとつ大切な要素が抜けてません?」 「ん? 何」 「年齢! 残念ながら人間は歳を取るんです。これお互いですけど」 「・・・・・・残念ながらではなく、『幸いなことに』と開き直るしかないね」 そうは返したが、階段を上りながら思った、その通りだと。人が早くに識っている事柄に歳を重ねてから気付くというのは、単に不誠実な半生の証しでしかない、と。それがどんなキャリアになると言うのだ・・・。 券売機で亜希の切符を買った。
裕一郎は、改札口を越えるとき亜希が言った言葉を忘れられずに居る。 「北嶋さんにしといたらよかった。北嶋さん、独り身だし」 松下亜希。酔った女の戯言であっても、罪なことを言うてくれるなよ。それに俺は独り身じゃない。帰れないだけだ。 今夜三ヶ所で呑んだ亜希は、もう、ことの終りを宣言していたと思った。さっき、黒川一家の送別会でユウくんと言い合っていた「沖縄へ来てね」「行こうかな。泊めてくれる?」も案外本気かもしれない。 駅から独り住まいの自宅マンションへの、もう閉まっていて街灯も消えている商店街を歩きながら認めていた。さっき亜希と呑み始めてすぐに二人の関係に気付いたのではなく、元々知っていたのだと。 年初めの現場で、亜希から菓子を貰ったことがあった。現場の職人らとおやつに食べた。友人の結婚式に行って来たとのことだった。 翌日、別の場所で同じものを食べたのだ。高志と呑んで、「うちに来いや、呑み直そう。久しぶりやから玲子も喜ぶよ」と誘われ、深夜に訪ねた。起きていた玲子が「もう呑みすぎでしょう」と咎めたが、しばらく呑んだ後、亜希から貰ったものと同じ菓子が出て来たのだ。 「さあさあもうお終いや。これ、高志が業界の一泊ゴルフ旅行で貰って来たんよ、案外美味しいよ。タルト言うんよ。甘いもの食べてお茶飲んで、二人とも明日も働かんと」 裕一郎は納得した。その時きっと自分は、瞬時に、二つの場所で出た同じ菓子を結び付けないことにしたのだと。 「この和風ロール・ケーキのどこがタルトやねん?」と酔った頭で思っていた記憶はある。