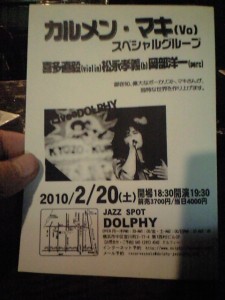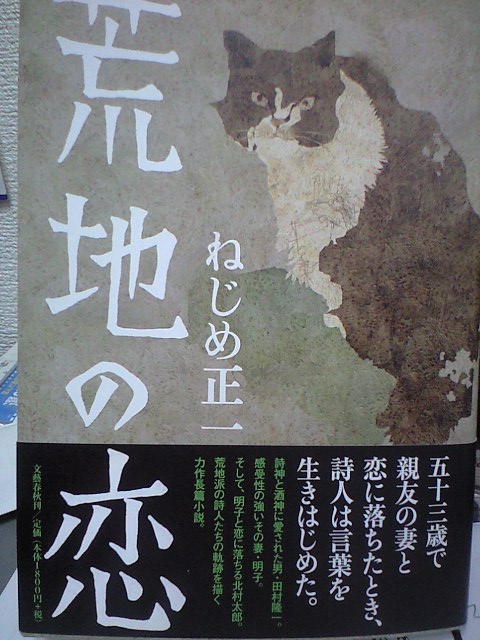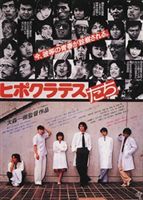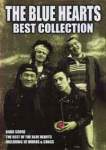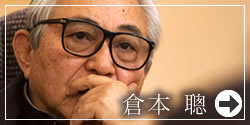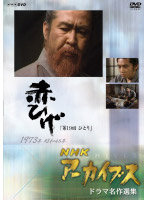つぶやき: 新宿現場足捻挫。 ふと母を想う
病床に身を起こし居り膝撫でて
「これ可愛いねん」と 母のつぶやく
膝切断部 「ぬいぐるみ」のごと
「わて諦めても脳憶えとる」
たそがれ映画談義: 教えてくれた 夫婦の絆・意味・価値
『ぐるりのこと』 08年。監督:橋口亮輔、出演:リリー・フランキー、木村多江
待望していて身籠った子の死から、こころのバランスを崩しやがてこころを病んで行く妻、
その妻を何とか支えようとする夫。妻が再生への入口に立つまでの日々を描き、 夫婦ということの絆の意味を見せてくれた。 作者は言っているのだ、夫婦は究極の同志・戦友でもある、と。 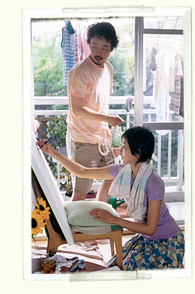
靴修理の仕事から「法廷画家」に転職した夫は、
最近の、凶悪・悲惨・冷酷犯罪の裁判と関係者を目の当たりにする。
作者は、人や社会との関係も成立し難い病に沈んで行く妻を支えようとする夫の、
こころを広げ浄化し高めて行ったものが、逆に「法廷」で知る眼を覆いたい事実だったことを通して、
ある「可能性」を示したかったのだ。
事件の悲惨、被害者の無念や打ち砕かれた未来・希望、加害者のこころの闇、・・・・ その「公的」意味を自己の内に刻み蓄積できた者だけが持ち得る、ある「可能性」を・・・。
私的ラブ・ストーリーであり、公的社会性を抱えた物語だ。
繊細な描写、丁寧な映画作りに感心しました。
リリー・フランキー演ずる夫。「ええ男」とはこういう人のことだと思う。
彷徨う友へ: カルメン・マキ ふたたび
私がこうして歌ってこれたのもマキさんがいたからだと言っても過言ではない。
私が多大な影響を受けた日本では唯一の歌手である。
他にも素晴らしい人はたくさん居たし今も居るけれど誰もマキさんには及ばない。
40年前、今にして思えばマキさんの第1回目のあのステージを
今は無き新宿「蠍座」で体験した時に(そう、あれは体験だった)
すでに私の歌手人生は決まっていたと言ってもいい。
あの時から浅川マキさんは私の指針だった。目標だった。
でも誤解してほしくないのは、私は浅川マキになりたいわけではないし、
なれるものでもないし、なりたいと思ったこともない。
マキさんの、唯一無二の確固たる自己表現に衝撃を受け胸を打たれたのだ。
私には何ができるのだろう・・・と。
そうしてあれからの長い道のりの中で、あっちへ行ったりこっちに来たり
紆余曲折あって試行錯誤を繰り返しながら辿り着いたところは
私はいつも、どんな時も、私自身であるべきだ ということ。
そしてそれは当り前のようでいてとても難しいことでもあるということ。
マキさんはそれを私に教えてくれた。
読書: ねじめ正一著『荒地の恋』
ベルリン-共同から: ドイツ市民 ネオナチ・デモを阻止
空襲をナチスのユダヤ人大量虐殺(ホロコースト)になぞらえ「爆弾によるホロコースト」と主張するネオナチなど約5千人が、ドレスデンの新市街などに集結。
これに反対する市民らは、戦災の象徴・フラウエン(聖母)教会がある旧市内への極右の侵入を阻止するため、人間の鎖をつくったり座り込みをした。衝突回避のため、数千人の警察官が出動。双方の計約30人が拘束され、警官15人を含む計約30人が軽傷を負った。市内各地では同日、反ナチスのシンボルの白いばらを献花するなどさまざまな追悼行事が行われた。
たそがれ映画談義: 若者の時間
TV画像とスピッツによる主題歌を採録: http://www.youtube.com/watchv=d44630XkPgk http://www.youtube.com/watch?v=P-I9Tn6RL0Q http://www.youtube.com/watch?v=uHt6-yOLuIM&feature=fvw
歌 遊泳: 栄光に向かって走る
はだしのままで飛び出して あの列車に乗って行こう
弱い者達が夕暮れ さらに弱い者をたたく
ほろ酔い通信: 脚本家と役者さん
歌遊泳: 品川宿で見る雪は・・・
つぶやき: 失われた記憶と蘇える記憶の交差点
さらに聞くと同じ小学校出身だと分かった。 曰く「あんたと同じ小学校で同学年らしいで!」