読書: 三浦しをん著 『舟を編む』 -元始 教育は「私」に在った-
三浦しをん著: 『舟を編む』(2011年光文社、¥1575)
辞書編纂という地味で壮大な作業に取組む人々の悲喜を、三枚目の構えで描いて一気に読ませる。この作者のものは『まほろ駅前多田便利軒』しか読んでいないので作者については語るものを持たない。 が、言葉との格闘、言葉の自律・自立、言葉の「公共性」、社会・国・権力・政党・宗派を超えた「公」的普遍性・・・という重いテーマが、文体とストーリー、会話とエピソードのある種の軽妙な技法によってかえって浮かび上がって秀逸。 実は、七〇歳を前にした実兄から「読んだら?」と薦めのメールがあって、『まほろ』の好印象もあって読んだ。
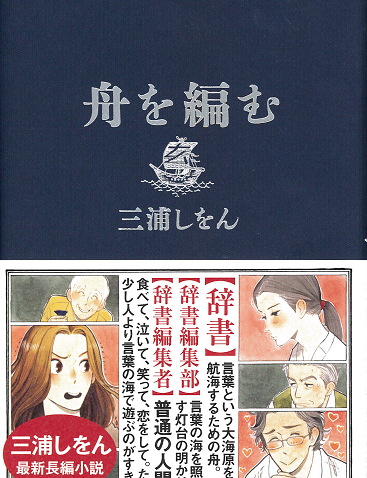 【本の帯より】 玄武書房に勤める馬締光也。営業部では変人として持て余されていたが、人とは違う視点で言葉を捉える馬締は、辞書編集部に迎えられる。新しい辞書『大渡海』を編む仲間として。 定年間近のベテラン編集者、日本語研究に人生を捧げる老学者、徐々に辞書に愛情を持ち始めるチャラ男、そして出会った運命の女性。 個性的な面々の中で、馬締は辞書の世界に没頭する。言葉という絆を得て、彼らの人生が優しく編み上げられていく・・・・。しかし、問題が山積みの辞書編集部。果たして『大渡海』は完成するのか・・・・。
【本の帯より】 玄武書房に勤める馬締光也。営業部では変人として持て余されていたが、人とは違う視点で言葉を捉える馬締は、辞書編集部に迎えられる。新しい辞書『大渡海』を編む仲間として。 定年間近のベテラン編集者、日本語研究に人生を捧げる老学者、徐々に辞書に愛情を持ち始めるチャラ男、そして出会った運命の女性。 個性的な面々の中で、馬締は辞書の世界に没頭する。言葉という絆を得て、彼らの人生が優しく編み上げられていく・・・・。しかし、問題が山積みの辞書編集部。果たして『大渡海』は完成するのか・・・・。
企画から出版まで十数年という歳月と人材を投入し、出版社の気概とステータスを賭け、権力に阿(おもね)ることなく、流行り・俗情・熱狂・強権押し付け に迎合・屈することなく、言葉の持つ「公」を維持し追及する人々。『舟を編む』とは、文中に登場する言葉 『辞書は、言葉の海を渡る舟だ』 『海を渡るにふさわしい舟を編む』 からの命名だが、そのこと自体「なるほど」だ。 言葉の大海原へ、支配勢力・時の権力の水先案内、宗派・党派の教条や意向、などを求めず、舟の乗り手たる「民」を信頼しても過剰に影響されることなく舟を編む。その作業には、どのような資質が求められるのだろうか。 文中にこうある。持てる時間のすべてを注ぎ、自身の生涯をかけて大槻文彦が完成させた、日本の近代的辞書の嚆矢(こうし)とされる『言海』から料理人という言葉を引く場面。 『料理人:料理ヲ業トスル者。厨人。 この「業(わざ)」は、務めや仕事といった意味だろうが、それ以上の奥行きも感じられる。「天命」に近いかもしれない。料理をせずにはいられない衝動に駆られてしまうひと。料理を作って大勢の腹と心を満たすよう、運命づけられ、えらばれたひと。』 『職業にまつわる「やむにやまれぬなにか」を、「業」という言葉で説明するとは、さすが大槻文彦だ。馬締は感じ入るのだった』
思い出す。かつて、金時鐘について鶴見俊輔がこう評した。『感情そのものが批評であるような地点に立つ詩業』。なるほど「業」だ。確かに、ぼくが師と仰ぐ幾人かの方の営みは正に「業」である。それは、「やむにやまれぬなにか」を「大勢の」頭と心と感覚と体に伝えようと、それこそ生涯をかけて取組んでおられる「業」なのだ。それは又、お上に庇護され、あるいはお上の代弁者となり、お上の厚遇(財や機会)を得る、などとは無縁のものだ。そして又特定の宗派・党派・営利団体との距離は「業」の生命線でさえあえる。 「業」はこうして、「私」に立って営まれながら、最も「公」に近い位置へと本人と我らを導く舟だ。辞書編集者の資質とは、このような辞書「業」を身に刻むことが出来る者に備わるもののはずだ。ラスト近く、老日本語学者と馬締が語り合う。 『「オックスフォード英語大辞典」や「康熙(こうき)字典」を例に挙げるまでもなく、海外では自国語の辞書を、国王の勅許で設立された大学や、ときの権力者が主導して編纂することが多いです。つまり、編纂に公のお金が投入される』 『翻って日本では、公的機関が主導して編んだ国語辞書は、皆無です』 『大槻文彦の「言海」。これすらも、ついに政府から公金は支給されず、大槻が生涯をかけて私的に編纂し、私費で刊行されました。』 『これでよかったのだと思います』 『言葉とは、言葉を扱う辞書とは、個人と権力、内的自由と公的支配の狭間という、常に危うい場所に存在するんですね』 『言葉は、言葉を生み出す心は、権威や権力とはまったく無縁な、自由なものです。自由な航海をするすべてのひとのために編まれた舟』
かつて、友人(清百合子さん)が『私塾の歴史』という大著を出した。『元始、教育は「私」に在った』を、記紀時代にまで遡り、奈良時代・平安~江戸寺子屋・明治自由民権へと、「教育」の脈々たる「私」の系譜を辿って解き明かした。公的機関とか公共サービスという言葉に冠されている公はおおむね、「権力の」とか「政府の」とか「地方自治体の」と訳し得る公だが、権力や国家を含む「私的な」存在を越えた「公」は何処にあるのだろう・・・。 実は「私」に立脚し、私費での刊行もいとわない「私」の営みこそ、もっとも真の「公」への可能性を持っている。その「公」こそ鴎外・漱石・啄木の明治以来、人々が探し求め、「天皇」だったり、「軍国政府」だったり、「大和魂」「武士道」「特定宗教」だったりしながら日本人が掴みあぐねているものだ。漱石はこう言っている。 『東郷大将が大和魂を有(も)つて居る。肴屋(さかなや)の銀さんも大和魂を有って居る。詐偽師、山師、人殺しも大和魂を持つて居る』 『大和魂はそれ天狗の類(たぐひ)か』(『吾輩は猫である』)
ヨーロッパの「公」、権力・国家といった移り行く私的な存在を越えた「公」は、やはりキリスト教の「神」なのだろうか。少なくとも、ぼくはたかだか百数十年の国民国家形成後のつまり明治以降この国に公であると宣して舞い降りたものども(マッカーサー以降の危うい「民主主義」を含め)、「公」たり得ないと思う。それは、多くの「業」によって今後育まれるはずだ。ぼくに「業」と呼べるものは無いが、師(ブログ:プロフィールの「勝手に師事・兄事」欄に記載)の「業」を案内文献・水先案内として、「公」を求めて歩きたい。そして「公僭称」には断固として抗いたい。
『舟を編む』一冊からハシズムと呼ばれる潮流の旗振役市長(元知事)の主張を思い浮かべている。公立小中学校選択制・教育基本条例・教員相対評価と二年連続下位者の解雇・教育委員会の改組・教育目標設定の権能を知事へ・公務員の人件費カットと人員削減・福祉と教育への競争と選別原理の持ち込み・・・・などを思い浮かべている。【次頁『舟を編む』からハシズムを想う】 ぼくに本著を薦めた実兄、三浦しをんさん、本ページ中に紹介した清女史、そしてハジズム頭目、偶然全員早稲田卒。 早稲田卒者には異論もあろうが、早稲田卒者の書き手・創り手を列挙すれば、不思議と『私塾の歴史』の論旨に通底する精神を維持している人たちに充ちている。(列挙しようと思ったが、無意味なので中止) 早稲田卒の歌人の歌を・・・。 『マッチ擦るつかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの祖国はありや』 寺山修司
通信: 汝は人を生きよ、吾は猫を生く(当家猫)
1980年ころからだから、もう30年以上ネコを飼っている。今、大阪の実家に居るのは確か四代目のネコで二匹の姉妹だ。各代のネコは、それぞれ病死や老衰大往生で逝ったが、猫生を全うした。十九年間生きた長寿のネコもいた。 妻は子供の頃から犬を飼ってきたそうで、最初「子沢山の我が家、この忙しい中、猫の世話なんかようせんよ。あんたしいや」と反対気味だった。 幼いころから家にネコが居て、「世話」などほとんど何も要らないことを知っているぼくは「ええよ」と答え、ネコ好きの友人から子ネコを貰い受け、我が家のネコとの生活が始まった。 蓋を開けば、ぼくよりも妻の方がネコ好きとなり、30年後の今では、ネコ世界でもたぶん有名(?)だろう「猫派」の堂々たる主要サポーターだ。
妻は子供の頃から犬を飼ってきたそうで、最初「子沢山の我が家、この忙しい中、猫の世話なんかようせんよ。あんたしいや」と反対気味だった。 幼いころから家にネコが居て、「世話」などほとんど何も要らないことを知っているぼくは「ええよ」と答え、ネコ好きの友人から子ネコを貰い受け、我が家のネコとの生活が始まった。 蓋を開けば、ぼくよりも妻の方がネコ好きとなり、30年後の今では、ネコ世界でもたぶん有名(?)だろう「猫派」の堂々たる主要サポーターだ。
【猫生訓七ヵ条】(大切なことはネコに教えてもらった。) あたいの猫生、いつでも晴れ♪ http://www.youtube.com/watch?v=1U43icOLJD4
① 彼ら人間は飼主ではなく、共同生活者・仲間だ。彼の妻・子供を含め、共同生活者間に序列などない。縦にではなく横に繋がっているんだニャン。 ② 我々のことを身勝手・我が侭などと言う人間も居るが、あんたの思惑通りには動かないだけで、何か迷惑をかけました? そして、あんたらの個人性に介入したことなどあります?! ③ 出来れば仲良くしたいけど(仲良くしているが)、いつ独りになっても生きて行く覚悟を放棄したことなどニャイ。 ④ 犬君には悪いが、こち虎、主(あるじ)やお国や教祖や党理論に照らしてその指示を待って生きているのではない。「犬は三日の恩を三年憶えているけど、猫は三年の恩を三日で忘れる」と人間は言うが、そうではない。別れの切情を表して人様の負担にならないよう配慮しているに過ぎない。浅いのぉ、人間! そんなに、恩を忘れていないことの可視的確証が欲しいのか? ⑤ 時と場面によっては、甘えるけど、媚びない。仲間内では、競わない・争わない・誇らない・蔑まないのだニャン。 ⑥ 頼りにしてはいるが、委ねはしない。物理的期待と精神的依存は全く違うのだニャン。 ⑦ 自分にとって大切なことは、最後に自分で決めるのだニャン。決定権は吾に在り。 追:某市長(元知事)は大嫌いだ!
たそがれ映画談義: 浦山桐郎 初期三部作
浦山桐郎初期三部作、山田洋次新作のことなど
年末のブログ、2011年に逝った人を挙げた記事の、脚本家石堂淑朗という名と共にあった映画:「『非行少女』って何でしょう?」と若い人から質問がありましたので、お答えしておきます。 【『非行少女』:あらすじ→goo映画 http://movie.goo.ne.jp/movies/p21010/story.html 】
彼女によれば、ネット検索しても『非行少女ヨーコ』なる作品にヒットして、監督名と共に入力しても、「画像なし」「ソフトなし」「中古品¥28,000」(ソフトが廃版なんでしょうね)だそうで、「これは成人指定映画?」「よほどのお宝エロ・シーンがあるのですか?」となる。ちなみにぼくはそのビデオを持っているので、お望みならお貸し出来ますが・・・。互いの住所確認などお厭でしょうね。 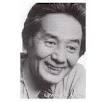 日活に浦山桐郎という監督が居りました。この人は1930年生まれ、敗戦時に15歳ということになる。1985年に55歳で早逝しています。同世代の映画監督としては、大島渚、山田洋次、篠田正浩、熊井啓、吉田喜重などがいる。50年代~60年代初頭の日活映画を注意深く観ていると「助監督:浦山桐郎」というクレジットに出合う。確か『幕末太陽傳』(監督:川島雄三)や『豚と軍艦』(監督:今村昌平)もそうだった。監督第一作が62年『キューポラのある街』で第二作が63年『非行少女』、第三作が69年『私が棄てた女』。これを、ぼくは「初期浦山三部作」と命名して一文を書いたことがある。浦山は観客動員が見込めない映画ばかり企画しては日活を困らせた問題児で、ゆえに寡作家であった。その後75年・76年に東宝で『青春の門』二作、83年断末魔の日活で『暗室』、85年東映で『夢千代日記』。生涯に全部で9作だった。が、初期三部作以降の作品は、三部作を越えられなかった。
日活に浦山桐郎という監督が居りました。この人は1930年生まれ、敗戦時に15歳ということになる。1985年に55歳で早逝しています。同世代の映画監督としては、大島渚、山田洋次、篠田正浩、熊井啓、吉田喜重などがいる。50年代~60年代初頭の日活映画を注意深く観ていると「助監督:浦山桐郎」というクレジットに出合う。確か『幕末太陽傳』(監督:川島雄三)や『豚と軍艦』(監督:今村昌平)もそうだった。監督第一作が62年『キューポラのある街』で第二作が63年『非行少女』、第三作が69年『私が棄てた女』。これを、ぼくは「初期浦山三部作」と命名して一文を書いたことがある。浦山は観客動員が見込めない映画ばかり企画しては日活を困らせた問題児で、ゆえに寡作家であった。その後75年・76年に東宝で『青春の門』二作、83年断末魔の日活で『暗室』、85年東映で『夢千代日記』。生涯に全部で9作だった。が、初期三部作以降の作品は、三部作を越えられなかった。![キューポラs[2]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/01/08624be1cb54af03c5c983317ab2f0a26.jpg)
ぼくが、『キューポラ』『非行少女』『棄てた女』が三部作だというのは、60年代の「おんな」の悪戦を、主人公に寄り添って描き、同時に自らの「戦後第一期青年性」とその限界を等身大に描いた誠実がそこにあり、間違いなく「時代」を切り取ってみせたと思えたからだ。浦山は、主人公ジュン(キューポラ)、若枝(非行少女)、ミツ(棄てた女)を、60年代を生きる少女~おんなとして、時と境遇の違いを越え、同じものの変容態として提示し、もって「時代」の正体を逆照射して見せたのだ。それは、そのまま自身=男の正体を晒すことでもあった。
『三丁目の夕日・異論』( http://homepage3.nifty.com/luna-sy/re57.html#57-3 )で書いたが、東京タワーを背に蠢く三丁目の人々が、アッカラカンと置き去りにして行くものども・ことどもにこそ「時代」を視ていた浦山が選んだ主人公三人は、貧困と無知に正面から立向かおうとするジュンであり、そうは出来なかった若枝(注:まわり道をして遅れて挑むラストです)であり、60年安保学生に棄てられる集団就職のミツである。三丁目の六子(堀北真希)のような虚構の「いい子ちゃん」などではない。彼女らは、浦山が捉えた「時代」と「おんな」を、従って「男」を三作を通してようやくおぼろげに示したのだった。 質問者でも知っていよう『キューポラ』のジュン(吉永小百合)が、貧困・進学無理家庭の、いわばその層内の精神的エリートだとすれば、『非行少女』の若枝(和泉雅子)はノンエリートであり、『棄てた女』のミツ(小林トシエ)とは、彼女らの無垢な努力に共感を覚えながら、「所得倍増」「高度経済成長」に走った元左翼青年のモーレツ勤労者に再び棄てられる存在なのだ。 それはそのまま、時代が「選び取り」「選び棄てた」もの全てだと語っていた。 「お前が棄てたもの」は何なのか?と。 ところで、良い映画とは確実に「時代」を写してもいるのだが、浦山桐郎と同世代の作家とは、思春期に戦争を体験し、戦後の混乱期と復興期に大学に学んでいる。その奥深い記憶の光景は、戦争・焼跡・闇市から復興・所得倍増・モーレツとバブルに走る狂想曲であるに違いない。彼らが描く世界には、その光景と「今」とが写し取られていた。
山田洋次が「男はつらいよ」のヒットを背景に、盆・正月に「寅さん」を撮ることを交換条件にして、数年に一本自主企画実施を松竹に飲ませ、世に出した作品群は実に時代を写し取っていた。『家族』『故郷』など「民子三部作」、『幸福の黄色いハンカチ』『ダウンタウン・ヒーローズ』『学校』『息子』『母べえ』などがそれだ。そして、寅さんこそ、実に時代を描いていた。 話は変奏するが、『寅次郎忘れな草』のリリーさん、ええねぇ~! 時代のインチキ提案とは和解すまいとアナーキーに生きる者の「孤独」「不安」「自立」は、地位・家・財との現実的距離感も確立したい模索の中に在った。全48作中、寅さんとぼくが最も惚れた「おんな」なんですねぇ。浅丘ルリ子が100年に一度出会った役として演じていた。リリーさんは難しいことは言わないが、困難な生であり、見事な世紀末の「おんな」振りの可能性を示していた。その先に確実に「時代」が立ちはだかっていた。願わくば、リリーさんは一回こっきりの登場にして欲しかった(スミマセン、ミーハー願望です)。 *実際には、その後『寅次郎相合い傘』『ハイビスカスの花』『紅の花』と三作に登場 最近の日本映画には、何が写し取られているのだろうか・・・?と不安だ。 山田さんが、『東京物語』(小津安二郎)をベースに、いわばその21世紀版らしい、『東京家族』を撮り始めるという。今秋公開か? 出演は、菅原文太、妻夫木聡、蒼井優、市原悦子、室井滋、夏川結衣とぼくの好みの役者ばかりだという。楽しみだ。
不器用だった浦山桐郎を久し振りに思い出させてくれた通信でした。 『非行少女』の印象深いシーンも思い出した。 寒い寒い夜、更正施設に入寮している若枝を浜田光夫が訪ねるのだが、廊下の洗面台前の窓越しの会話のシーン。今井正『また逢う日まで』の岡田英二と久我美子の窓ガラス越しのキス・シーンは映画史に残る名場面と言われているが、この和泉・浜田のシーンもなかなか・・・。 若枝の旅立ちのラスト・シーン。駅(確か金沢駅)の待合室の場面では、カメラが360度グルリと回りながら二人を撮るという禁じ手で、小説でいえばナレーション・地の文が足許フラフラ、定まらないみたいな論難があったのを記憶している。実際、その浮遊感に驚いた。批判の言い分は織り込み済みだったと浦山は語っている。
さて、後年「あの時代」として次のような括りになることだけは「大阪府民(?)」として避けたいものだ。 『市民や・労働団体・市民運動・政党が官僚に認めさせ培って来た、高コストの施策を、官僚支配打破を謳い文句に、根こそぎ効率主義で斬って棄てようとする知事が選挙の圧倒的勝利を得て大阪に登場。 大阪府民は、威勢よく歯切れのいい知事を、レーガン・サッチャー・小泉のようにいやそれ以上に支持し喝采を送った。 教育と福祉の場に競争と選別を持ち込み、競争に「勝てる子」を作らんとしている。初期に言った「子どもの笑顔が政治の中心」との言は「競争に勝って微笑む子ども」のことだったのだ。一握りの勝者と多くの敗者・・・儲ける自由・勝ち抜く自由・選別する自由・・・、そのことを子どもに排他的競争を通じて「教育」するのか?!! やがて、大阪を震源地とするハシゲ現象は全国を覆い、それがファシズムか否かの論争に明け暮れる知識人・政党を尻目に、21世紀型「ハシズム」として国民運動になった。就労先を探し歩き疲れ果てた「府民」は、己より弱いもの、虐げられし者、障害者、少数者、マイノリティ、在日外国人、女性・・・を排除すれば「俺の雇用は確保出来るのだ!」と、さらに一層「ハシズム」の運動員となって奔走し始めた。 2012年とは大阪発のそういう「時代」の始まりであった。』
そうさせてはならない!
通信: 2011年 逝った人々
今年も得難い人々(や特異な人)が逝きました。 合掌。
1月 細川俊之、和田勉(NHK『阿修羅のごとく』)、喜味こいし(晩年被爆体験の語り部を続けた)、ジョン・バリー(「野生のエルザ」テーマ曲) 2月 永田洋子、アニー・ジラルド(60年『若者のすべて』)、 3月 坂上二郎、エリザベス・テイラー、いいだもも、 4月 シドニー・ルメット(ポーランド系ユダヤ人、57年『一二人の怒れる男』64年『質屋』)、田中好子、サイババ(超能力者も死ぬんや) 5月 上原美優、児玉清(名司会、書籍案内は実に参考にさせていただきました)、長門裕之、清水旭、 6月 ピーター・フォーク、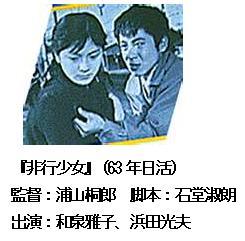 7月 宮尾すすむ、原田芳雄(『竜馬暗殺』『寝取られ宗介』)、小松左京、伊良部秀輝、 8月 前田武彦、日吉ミミ、二葉あき子、竹脇無我 9月 杉浦直樹、五十嵐喜芳、 10月 スティーブ・ジョブス、柳ジョージ、カダフィ大佐、北杜夫、 11月 石堂淑朗(60年『太陽の墓場』、63年『非行少女』)、ジョー・フレージャー、立川談志、 ダニエル・ミッテラン、西本幸雄(江夏の21球と言うが、あれは西本幸雄と21球やね)、 12月 市川森市、金正日、森田芳光(やはり『家族ゲーム』ですね)、
7月 宮尾すすむ、原田芳雄(『竜馬暗殺』『寝取られ宗介』)、小松左京、伊良部秀輝、 8月 前田武彦、日吉ミミ、二葉あき子、竹脇無我 9月 杉浦直樹、五十嵐喜芳、 10月 スティーブ・ジョブス、柳ジョージ、カダフィ大佐、北杜夫、 11月 石堂淑朗(60年『太陽の墓場』、63年『非行少女』)、ジョー・フレージャー、立川談志、 ダニエル・ミッテラン、西本幸雄(江夏の21球と言うが、あれは西本幸雄と21球やね)、 12月 市川森市、金正日、森田芳光(やはり『家族ゲーム』ですね)、
連載 83: 『じねん 傘寿の祭り』 エピローグ (4) 終
エピローグ④終
赤嶺(旧姓:喜屋武)千恵、一九〇五年・明治三八年生まれ。一九二二年・大正一一年、十七歳のとき父を喪う。長女だった彼女は、成績優秀で女子師範学校生だったが、辞めて長崎に住む親戚の紹介で長崎の造船所の事務職となる。親戚は部品作りの下請工場を営んでおり、造船所へ沖縄の青年男女を何人も送り込んで来た実績がある。千恵は寮に入った。三歳下に弟、十歳違いの幼い妹がいた。大正期の若い女性の単身長崎。言葉の障壁を含め、外国へ行くほどの苦難だったろう。千恵は、沖縄の家族への送金を律儀に果たしたという。 長崎や福岡に住むこの親戚の遺族が各種証言をしてくれたが、内容は曖昧。 千恵は長崎の料理旅館の主黒川松栄と出会い、一九二七年・昭和二年二十二歳で黒川自然を産んだ。造船所は前年に退職している。黒川松栄との出会いのいきさつ、出産後の生活などの詳細は不明。弟は、すでになく、十歳違いの妹が、ひと度は姉の長崎での出産を認めていたが、本年はじめ、否定に転じて死去している。 一九三七年・昭和一二年、三十二歳の時沖縄へ帰り、翌三八年・昭和一三年赤嶺盛昌氏と結婚。一九三九年・昭和一四年、三十四歳で女児を出産。百合子と名付けた。 一九五六年・昭和三一年九月八日、五十一歳で肺癌で亡くなった。一人娘、百合子は奇しくも、千恵が沖縄を発ち長崎へ向かった年齢と同じ十七歳だった。明日九月八日は、千恵の命日である。千恵の夫、赤嶺盛昌氏は後を追うように二年後死去している。夫妻が眠る墓地は米軍K基地内に在る。 この千恵なる女性が、黒川自然の生母であると当社は考えるが、断言するだけの資料を得ていない。千恵の夫、赤嶺盛昌の親族は「今さら」「そっとしておいてくれ」と、事実を認めるとも認めないとも言わない。赤嶺百合子と黒川自然の「DNA兄弟姉妹鑑定」という方法があり、両親又は片親が同一という可能性を、両親の場合の「兄弟指数」片親の場合の「半兄弟指数」として提示するが、肯定否定の決定的なものではない。この鑑定の勧めを赤嶺百合子に申し出てはいない。報告書はここで終っている。
 比嘉が、その後を語ってくれた。 つい最近、百合子は、父親の遺品に混じる母親の遺品の中に、見たことのない一葉の写真を見つけた。若き日の母親千恵が、男の子と写っている色褪せた古い写真だ。親戚筋の子供だろうと思っていたが、何人かの親戚筋に写真を見せて訊ねたところ、誰もが顔を顰めるのだった。半信半疑は確信に近付いている。 昨日、黒川は亜希だけでなく謝花晴海にも同じ「脅し」の電話をしていた。晴海は百合子に伝え「何か決定的なものはないか?」と電話していた。百合子は、関係者を傷つけるまいと配慮して行なわれた謝花晴海の調査に心打たれてもいたし、事実なら兄に当たる人物に会いたいとも想っていたので、昨日その写真を晴海に見せた。写真を見た晴海は確信した。写真の子は、七十年の歳月を経てなお、自然そのものだった。今日、百合子はDNA鑑定受諾を言うのではないか・・・。
比嘉が、その後を語ってくれた。 つい最近、百合子は、父親の遺品に混じる母親の遺品の中に、見たことのない一葉の写真を見つけた。若き日の母親千恵が、男の子と写っている色褪せた古い写真だ。親戚筋の子供だろうと思っていたが、何人かの親戚筋に写真を見せて訊ねたところ、誰もが顔を顰めるのだった。半信半疑は確信に近付いている。 昨日、黒川は亜希だけでなく謝花晴海にも同じ「脅し」の電話をしていた。晴海は百合子に伝え「何か決定的なものはないか?」と電話していた。百合子は、関係者を傷つけるまいと配慮して行なわれた謝花晴海の調査に心打たれてもいたし、事実なら兄に当たる人物に会いたいとも想っていたので、昨日その写真を晴海に見せた。写真を見た晴海は確信した。写真の子は、七十年の歳月を経てなお、自然そのものだった。今日、百合子はDNA鑑定受諾を言うのではないか・・・。
あゝ、この報告書には、沖縄と日本の関係が、軍国が、昭和が、黒川の生母の悲哀の歴史が、二十世紀日本の女性が、封建が、日沖の「家」というものが、黒川の「総決算」しなければならない歳月が、・・・詰まっている。比嘉が時間を割いてこの席を用意した血肉から湧き出る「思想」が詰まっている。裕一郎は、命の終わりを間近にしてこだわる黒川の執念の言動を全面的に受容れようと想い、思い詰めた老人の狂言かもしれない事態に時間を割いて惜しまない比嘉という人物との歴史を噛み締めていた。 比嘉が、黒川はその妄想を実行して果て、ユウくんとギャラリーは妻に託す積りではないだろうか、と言う。無計画に見えて、その辺りのことも配慮していたんじゃないか? お前さんのギャラリー作りが、そういうジイさんの全体プランに組み込まれていたとしたら、どうじゃ? 黒川の日常を知る者としては考えられないが、一笑に付そうとも思わない。
同世代と思しき女性と、やや年長の女性が席にやって来た。謝花晴海と赤嶺百合子だ。 赤嶺百合子だろう女性は、黒川が言っていた女優を老いさせればこうだろうと思わす顔立ちだった。母親・千恵似なのだろう。 挨拶を済ませると、百合子は早速、件の写真を取り出して見せた。 間違いなく、黒川だ。黒川自然だ。 詳しく語り合おうとした矢先、黒川がやって来た。比嘉が立って迎えた。 硬い表情の黒川が、全員を睨んで言う。 「沢山集まってぼくを説得か? 言っておくがぼくの決意は変わらないぞ。明日、誰が何と言おうと突入するんだ。ゲートで殺されてもいいんだ。そうなれば、殺したのは米日沖のある連合ということになる。裕一郎君、そこをしっかり後世に伝えてくれ」 裕一郎がその迫力に怯みながらも、「黒川さん、沖縄は母じゃなかったんですか?母を敵に回すのか?」と言葉を返そうとすると、その前に比嘉が言う。 「黒川さん、ぶっそうなこと言うなよ。沖縄の心を信頼しなさいや。明日は母上の命日なんだってね。今年は無理でも、来年墓参できるようにする。ワシは出来ることの全てをするよ。約束する」 百合子が写真を手にして立った。 「お兄さん・・・・・・・なんですよね。これ、あなたですよね」・・・」と写真を黒川に手渡した。 君は誰?といった表情でやや顔を斜めにして、黒川が受け取った写真を凝視している。 「ぼくだ、これはぼくだ。憶えている、これは運動会の日、ウメさんが写した写真だ。尋常小学校の校門前だ。運動会の日、何故かウメさんが写真写真と強く言ったのだ」 そう言ったきり黒川の言葉が続かない。見る見る、黒川の高潮した顔の目と鼻と口から、液というべきか汁と呼ぶべきか、液体がとめどなく流れ出している。百合子の手を握って発する、黒川のオオゥ、ウーという声にならない音が響いた。 比嘉がもらい泣いている。百合子は嗚咽し、謝花晴海は堪えるようにハンカチを目に当てていた。裕一郎は溢れるものに困惑して、目の前の光景に身動きできずに居た。 比嘉が「これからどう進めるか相談しよう。な、黒川さん」と言うと、黒川は黙って頷いた。 比嘉が裕一郎に顔を向けて言う。 「裕一郎よ。沖縄、日本。ワシらが残された時間にすることは五万とあるぞ。それぞれの場所でそれをしよう」 裕一郎はどのようにも答えられない己を認め戸惑いつつ、ただ立ち尽くしていた。 ようやく、全員が腰掛けた。姉のように黒川の手を握り泣きながらも微笑んでいる妹を見て、百合子という名から、又しらゆりの花言葉を思い浮かべていた。無垢と威厳。 裕一郎の中では、機内で見た夢と、目の前の事態とは区別なく一つだった。この上は、黒川が美枝子とユウくんの自由往来を認めるだろうと想うと、ふと、敬愛する女性歌人のある歌が浮かんで来るのだった。
鳶に吊られ野鼠が始めて見たるもの己が棲む野の全景なりし /斉藤 史
(『じねん 傘寿の祭り』 完 )
連載 82: 『じねん 傘寿の祭り』 エピローグ (3)
エピローグ③
明日九月八日と聞いたが、一日前倒ししたのか。 四十Mほど先を、国道に面して延々と続くフェンスに沿って歩く黒川が見えた。ここは何処の米軍何基地だろう。黒川が往く前方二百五十Mには基地の正面ゲートがある。黒川は何故か白衣を着ていた。両ポケットが膨らんでいる。![e[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/12/e1.jpg) 黒川の生母の親戚筋、生母の友人知人の遺族、あらゆる情報源を探り生母を特定した探偵社の、調査の女性:謝花晴海が言った。 「視て、あのポケット。手榴弾だと思う。黒川さんが入手したと電話で言っていた手榴弾じゃないかな。真偽の程は怪しいのですが、本人は、集団自決=強制集団死の地の遺族から手に入れたと言ってたんです。事実だとしてももう発火しないとは思われますが・・・」 比嘉が「いかん走り出したぞ」と追い始めた。比嘉に続いて、晴海と、晴海が連れてきた女性、裕一郎、計四名が一斉に走り始めた。 気付いた黒川は速度を上げようといているのだが、時々咳き込んで立ち止まり、速度はかえって鈍る始末。距離にして六~七十M、時間にして二十数秒だろうか、四人は黒川に追い付いた。 「止めてくれるな。突入する。突入して墓まで行くんだ。そして母に会うんだ」 比嘉が分厚い手で黒川の手を掴んで言う。 「何を言うとるのか!ジイさん。突入なんて出きゃせんぞ。しかもポケットの怪しげなものを振りかざしたりしようものなら、たちまち殺されるぞ!」 「もうこの歳だ。命の閉じ方は承知しておる」 黒川が身体を揺らして地団駄を踏んでいる。
黒川の生母の親戚筋、生母の友人知人の遺族、あらゆる情報源を探り生母を特定した探偵社の、調査の女性:謝花晴海が言った。 「視て、あのポケット。手榴弾だと思う。黒川さんが入手したと電話で言っていた手榴弾じゃないかな。真偽の程は怪しいのですが、本人は、集団自決=強制集団死の地の遺族から手に入れたと言ってたんです。事実だとしてももう発火しないとは思われますが・・・」 比嘉が「いかん走り出したぞ」と追い始めた。比嘉に続いて、晴海と、晴海が連れてきた女性、裕一郎、計四名が一斉に走り始めた。 気付いた黒川は速度を上げようといているのだが、時々咳き込んで立ち止まり、速度はかえって鈍る始末。距離にして六~七十M、時間にして二十数秒だろうか、四人は黒川に追い付いた。 「止めてくれるな。突入する。突入して墓まで行くんだ。そして母に会うんだ」 比嘉が分厚い手で黒川の手を掴んで言う。 「何を言うとるのか!ジイさん。突入なんて出きゃせんぞ。しかもポケットの怪しげなものを振りかざしたりしようものなら、たちまち殺されるぞ!」 「もうこの歳だ。命の閉じ方は承知しておる」 黒川が身体を揺らして地団駄を踏んでいる。
一人の老人を初老の男女が四人がかりで、まるで取り押さえているような光景は確かに異常だ。通りかかった県警のパトカーが、窓を開け速度を落として様子を伺っている。晴海が「父です。何でもありません」と言い、黒川も笑顔で顔の前で手を左右に振った。パトカーは行き過ぎた。 黒川はゼイゼイと呼吸している。患っている心臓は大丈夫だろうか。裕一郎がその心配と「ユウくんのことはどうする気なんです?」とを言おうとしたとき、突然黒川が五人の目の前にある高い網状のフェンスに向かって突進した。柵を越えフェンスに手をかけた。よじ登るつもりなのか? 上部の線には高圧電流が流れているんだぞ! 黒川の背に向かって、裕一郎と晴海より十ばかり年長の、晴海が連れてきた女性が始めて口を開いた。大きな声で言う。 「黒川さん、黒川自然さん。私は貴方の妹かもしれないのです。」 黒川が振り返った。 金網フェンスの揺れを激しく感じた時、
裕一郎は機体の揺れに目覚め、シートベルト装着を促す機内放送を聞いた。 夕刻那覇空港に着き、到着ロビーを歩いていると比嘉から電話がかかってきた。四階の喫茶レストランに居ると言う。やはり空港まで来てくれたのだ。来るのは比嘉だけではないような気がする。 レストランに行くと、滑走路を見渡せる窓際に比嘉が居た。薄いファイルを読んでいる。謝花晴海の報告書だと推測した。 「おう、裕一郎。朝電話のあと調査の謝花さんに電話して会って来たよ。ジイさん、お前が松下亜希さんから聞いたのと同じ脅しを謝花さんにもしていた。突入とか手榴弾とか言ったらしい。自分には時間が残されていないと思い詰めているんや。脅しのパフォーマンスだとしても捨て置けない。彼女はジイさんを説得する一方、ジイさんの妹に当たる人赤嶺百合子と言うんだが、その妹に伝え、赤嶺家が正式に認めるよう再度説得したらしい。謝花さんも、赤嶺百合子さんも、そしてジイさんもここへ呼んである。間もなく来るだろう。ワシは戦争で父親を失った。年老いた母ももう長くはない。村で軍への志願を率先して説いて回ったという亡き父親との対話が、ワシの原点や。じゃから、ジイさんの言う『決着を付ける』という想いは共有できるんじゃ。」 比嘉から晴海の最終報告書を受け取り目を通した。
連載 81: 『じねん 傘寿の祭り』 エピローグ (2)
エピローグ②
裕一郎は近い私鉄の駅へ向かい、駅横から出ている関西空港直行バス停車場のベンチに腰掛けていた。バス到着まで二十分ある。探偵社の、謝花晴海だったか、同年代のその女性に会いたい。会って、黒川生母探しの経過と結論を聞きたい。晴海を知っているという比嘉に電話した。「九・八黒川決起」のあらましを伝え、謝花晴海に会いたいので連絡とってくれと依頼した。比嘉が飛行機の那覇到着予定時刻を訊ねて来る。空港へ来てくれると言うのだろうか。ただ事ではないと直感する比嘉の対応が嬉しかった。 バスは相変わらず空席が目立った。
戦勝国アメリカは、戦後「ハーグ陸戦条約」を根拠として沖縄を占領していた。サンフランシスコ講和条約締結(五一年九月八日)以降アメリカ軍の駐留は国際的に認知されることとなる。条約発効(五二年四月二八日)前の五〇年初頭から基地建設は本格化し、アメリカ政府の出先機関である琉球諸島米国民政府(USCAR)(比嘉の話に出てきたな)は、布令・布告を連発して民の土地を接収。基地の拡充を進めた。一九六〇年六月、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(「日米地位協定」)(あゝ長ったらしい!)の発効により、治外法権的特権・財政負担・各種便宜を得て、今日まで犯罪の逮捕権・捜査権・裁判権、軍関連諸費用・経費負担などを巡る理不尽が続いている。
去年黒川が移住を決断した沖縄からの一本の電話は、生母に関する情報だったが、その直前の米軍機の沖縄国際大学への墜落事故の際も、現場に米軍が非常線を張り、沖縄警察の捜査を妨害阻止したなぁ。轢き逃げ事件・暴力事件・性犯罪、裕一郎でさえ多くの事件を思い出せる。九五年九月の米兵三人による少女拉致暴行事件の衝撃は国民に届き、誰もが「日米地位協定」の構造を考えたと思う。 米軍基地の拡充は、当然ながら多くの墓地をも呑み込んだ。 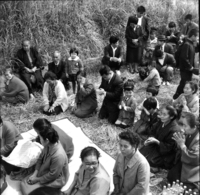 沖縄では清明祭(シーミー)と言って、旧暦三月清明節(四月五日ころ)に先祖の墓前に一族門中が集い重箱のご馳走を持ち寄り先祖を供養する。米軍基地内に墓がある場合、この行事でさえ地元自治体に申請し、米軍の立ち入り許可をもらう必要がある。基地内では米兵が先導、案内されて墓に向かうのだ。基地アピールの行事では寛容で開放的な米軍が、先祖供養には厳格な手続きを要求するのだ。この煩わしく屈辱的な事前手続きに、先祖様を含めたウチナーの今が象徴されている。 小規模な身内だけの命日墓参は、しばしば日程変更を求められ、九・一一以降、イラク戦争開始以降はさらに、基地立ち入り許可は難しくなっている。事態は戦争と直結している。
沖縄では清明祭(シーミー)と言って、旧暦三月清明節(四月五日ころ)に先祖の墓前に一族門中が集い重箱のご馳走を持ち寄り先祖を供養する。米軍基地内に墓がある場合、この行事でさえ地元自治体に申請し、米軍の立ち入り許可をもらう必要がある。基地内では米兵が先導、案内されて墓に向かうのだ。基地アピールの行事では寛容で開放的な米軍が、先祖供養には厳格な手続きを要求するのだ。この煩わしく屈辱的な事前手続きに、先祖様を含めたウチナーの今が象徴されている。 小規模な身内だけの命日墓参は、しばしば日程変更を求められ、九・一一以降、イラク戦争開始以降はさらに、基地立ち入り許可は難しくなっている。事態は戦争と直結している。
黒川は、心ある女性調査員の努力と説得で、生母を特定できたのだろう。生母は結婚相手の一族の墓に眠っていよう。否定に転じた妹さんは亡くなったというから、娘さん、黒川の妹にあたる人物が重い口を開いたのか。そこは、分からない。娘さんが「確かにそうです」と認めているならDNA鑑定など不要だ。互いに記憶を辿り、想い出の品や漏れ伝わる逸話を繋ぎ合わせて行けば照合できよう。墓参が叶わないのなら、特定は出来たが、先方の認知には至らないということだろうか・・・。 黒川が墓を訪ねるには、関係者の同意、自治体への申請、米軍の許可という手続き全てをクリアする必要がある。 もし娘さんが証言したとして、にも拘わらず一族親類縁者の異論で希いが叶わないなら、黒川にとって、それも「妨害者」となるのだろうか・・・。いつだったか、黒川が「ぼくが母に会うことを妨げる要素は、ぼくにとって全て敵なんだ」と言っていたのが気になる。それはちょっと違うと思う。 黒川自身の先妻と子、妻:美枝子との関係に照らせば、家族の事情や制度や「家」という強固なものが絡め織り成す要素は、「敵」などと言い放ちは出来まい。が、そこは黒川様の変則三段論法だ。母は、母たる沖縄は、ぼくを認知すべきなのだ。そこにおいて、ぼくの沖縄帰還は完結するのだ。 その前に立ちはだかる、米日の条約も基地も、フェンスもMPも県警も、紛れもない「敵」なのだ。そしてぼくを容れない沖縄に在る要素は、「敵」ではなくとも、「妨害者」であり内部矛盾なのだ。黒川理論ではそうなる。
裕一郎は関空のゲートをくぐった。 黒川さん、何をしでかす気や! 不安を抱えて那覇行きANA機に搭乗した。
連載 80: 『じねん 傘寿の祭り』 エピローグ (1)
エピローグ①
 裕一郎が退院して向かった妻の転居先は、高度経済成長期に各地に大量に建てられた、狭い一戸建公営住宅風の昭和の香り漂う住居だった。格安家賃だからと妻が選んだのだ。部屋が田の字に配置されていて、狭いキッチンの隣に風呂があり、トイレは後年改装されて水洗になったに違いない造りで玄関の横にある。窓のサッシは全て木造で隙間風が入って来る。それが七〇年代から運ばれて来る風ように感じ、七〇年代の初め住んだ文化住宅を思い出させた。猫の額ほどの庭があって、妻がその狭い裏庭でトマト・パセリ・大葉・キュウリなどを作っていたのを思い出した。その文化住宅で央知も姉も生まれたのだ。 ギブスを外しても、帰ってきた放蕩息子のように、脚の不自由を理由に何をするでもなくダラダラ過ごしていた。実際、松葉杖生活は洗濯物ひとつ干せやしない。妻は怪我人を鞭打つことはせず、仕事を続けた。 裕一郎は連日、リハビリに通院し、帰っては有線放送でかつて見逃した映画を観て過ごし、合間に「黒川との沖縄」を書き始めていた。黒川から二度、ユウくんから三度電話があった。最低限の生活は確保しているようだ。ユウくんは亜希と海へ行ったと報告してくれた。 焦る気持ちが無いではないが、松葉杖を卒業するまでしばらくこのまま居ようと決めていた。どの道、仕事は見つけなければならない。高志の呼び出しには松葉杖をついて二度ばかり呑みに出かけた。大学前駅待ち合わせの一件の真相を言ってやったが、もちろん高志は「それがどうした」とばかりに軽くいなし、話に乗って来ない振りを決め込んでいた。高志はノザキへ戻れと繰り返し言ったが、返事を保留しておいた。 八月末、玲子から朗報がもたらされた。 黒川から現物支給された太陽作の焼物の買い手があったと言うのだ。 大陽会の会報にも載せ、黒川の大阪時代の客の何人かを辿り太陽の焼物の話をするうち、その一人が「美枝子さんなら買い手を探すかも」となり、美枝子の所在を知る人が彼女に連絡した。 美枝子は熱烈な太陽ファンを憶えていて教えてくれた。連絡すると、その人物が買うという。太陽会の筋からも引き合いがあった。 その価格は、何と三点で百万以上だという。三点とも揃っているのが味噌らしい。陶芸界も不思議な世界だ。 二つのルートを天秤にかけるのも美枝子さんに失礼、美枝子さん紹介の人にしなよ、とのことだった。 裕一郎は考えた。その価格は想定外だ。黒川もここまでの値が付こうとは思わなかっただろう。いや、予想していたのなら黒川も大したものだ。最後にカッコ付けやがったか。見直してやってもいい。いずれにせよ、売ったら半額だけいただいて、残りを黒川と美枝子に半分ずつ送金するか。 妻に話すと「そうして上げて」と言う。何故この女性と暮して来たのか・・・、その理由を噛み締めていた。 九月になった。最後のリハビリでOKを貰い、松葉杖を放し、帰宅すると赤飯が待っていた。謝辞を述べておくべきだと思って「全快祝いか、ありがとう」と言うと、「アホ、花器が百二十万で売れた祝いや」と妻は照れ隠した。今日、買い手が玲子を訪ね花器と現金を交換、無事売買が成ったという。
裕一郎が退院して向かった妻の転居先は、高度経済成長期に各地に大量に建てられた、狭い一戸建公営住宅風の昭和の香り漂う住居だった。格安家賃だからと妻が選んだのだ。部屋が田の字に配置されていて、狭いキッチンの隣に風呂があり、トイレは後年改装されて水洗になったに違いない造りで玄関の横にある。窓のサッシは全て木造で隙間風が入って来る。それが七〇年代から運ばれて来る風ように感じ、七〇年代の初め住んだ文化住宅を思い出させた。猫の額ほどの庭があって、妻がその狭い裏庭でトマト・パセリ・大葉・キュウリなどを作っていたのを思い出した。その文化住宅で央知も姉も生まれたのだ。 ギブスを外しても、帰ってきた放蕩息子のように、脚の不自由を理由に何をするでもなくダラダラ過ごしていた。実際、松葉杖生活は洗濯物ひとつ干せやしない。妻は怪我人を鞭打つことはせず、仕事を続けた。 裕一郎は連日、リハビリに通院し、帰っては有線放送でかつて見逃した映画を観て過ごし、合間に「黒川との沖縄」を書き始めていた。黒川から二度、ユウくんから三度電話があった。最低限の生活は確保しているようだ。ユウくんは亜希と海へ行ったと報告してくれた。 焦る気持ちが無いではないが、松葉杖を卒業するまでしばらくこのまま居ようと決めていた。どの道、仕事は見つけなければならない。高志の呼び出しには松葉杖をついて二度ばかり呑みに出かけた。大学前駅待ち合わせの一件の真相を言ってやったが、もちろん高志は「それがどうした」とばかりに軽くいなし、話に乗って来ない振りを決め込んでいた。高志はノザキへ戻れと繰り返し言ったが、返事を保留しておいた。 八月末、玲子から朗報がもたらされた。 黒川から現物支給された太陽作の焼物の買い手があったと言うのだ。 大陽会の会報にも載せ、黒川の大阪時代の客の何人かを辿り太陽の焼物の話をするうち、その一人が「美枝子さんなら買い手を探すかも」となり、美枝子の所在を知る人が彼女に連絡した。 美枝子は熱烈な太陽ファンを憶えていて教えてくれた。連絡すると、その人物が買うという。太陽会の筋からも引き合いがあった。 その価格は、何と三点で百万以上だという。三点とも揃っているのが味噌らしい。陶芸界も不思議な世界だ。 二つのルートを天秤にかけるのも美枝子さんに失礼、美枝子さん紹介の人にしなよ、とのことだった。 裕一郎は考えた。その価格は想定外だ。黒川もここまでの値が付こうとは思わなかっただろう。いや、予想していたのなら黒川も大したものだ。最後にカッコ付けやがったか。見直してやってもいい。いずれにせよ、売ったら半額だけいただいて、残りを黒川と美枝子に半分ずつ送金するか。 妻に話すと「そうして上げて」と言う。何故この女性と暮して来たのか・・・、その理由を噛み締めていた。 九月になった。最後のリハビリでOKを貰い、松葉杖を放し、帰宅すると赤飯が待っていた。謝辞を述べておくべきだと思って「全快祝いか、ありがとう」と言うと、「アホ、花器が百二十万で売れた祝いや」と妻は照れ隠した。今日、買い手が玲子を訪ね花器と現金を交換、無事売買が成ったという。
翌朝早く亜希から電話があった。 今、那覇空港。東京の団体の本部へ行き、明後日かの国へ発つと言う。ギャラリーじねんでオープン直後に会って以来だ。沖縄を離れることの、あるいは仕事のスタートの、挨拶だと思いゆっくりした口調で「がんばれよ」などと言ったと思う。 亜希は急かされているような口調だった。 「北嶋さん、大変なんです。黒川さんを止めて!」 「何? 何のこっちゃ」 「最後の闘いをするって、何やらぶっそうな物も持ってるらしいの。私、昨日最後の配達の帰りギャラリーに立ち寄って、黒川さんにお別れの挨拶したんです。そのとき『君は、明日沖縄を去るから漏れることは無い。誰にも言うんじゃないぞ』って念を押されて、計画を聞きました。明後日、つまり明日九月八日に決行するって」 「黒川さん、何をするって?」 ![030da3898f7d884962b153cc2ebd3d57[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/12/030da3898f7d884962b153cc2ebd3d571-150x150.jpg) 「それは言ってくれませんでした。決着をつける、母に会うんだと思いつめた表情で真っ青なお顔でした」 「明日するって、九月八日・・・? うーん何の日やったかな」 「島に帰ってからネットで調べました。一九五一年九月八日、サンフランシスコ講和条約の締結です。北緯二十九度以南、奄美・沖縄を含む南西諸島を日本の行政権から切り離すという同条約第三号です」 「想像やけど、生母のお墓を特定出来たんじゃないか。で、たぶん、お墓は米軍基地内にあるんやないか。その関係の手続上からも関係者の同意を得られないことからも、お墓に行けない・・・それで・・・。で、ぶっそうな物って?」 「分かりません。本人が道具は用意した、って言うんです」 「よし、今から行く。黒川さんも、何を言うてるんじゃ全くぅ。ユウくんのこともあるのに」 「でしょ。止めて下さい。ことが終ったら北嶋君に話してくれ、彼は解かってくれる、って仰るんです」 「遺族説得が最終的に不調に終ったんやろ。調査員の制止を振り切っての行動やろうなな・・・。分かった行く。松下さん、君は東京に向かいなさい」
「それは言ってくれませんでした。決着をつける、母に会うんだと思いつめた表情で真っ青なお顔でした」 「明日するって、九月八日・・・? うーん何の日やったかな」 「島に帰ってからネットで調べました。一九五一年九月八日、サンフランシスコ講和条約の締結です。北緯二十九度以南、奄美・沖縄を含む南西諸島を日本の行政権から切り離すという同条約第三号です」 「想像やけど、生母のお墓を特定出来たんじゃないか。で、たぶん、お墓は米軍基地内にあるんやないか。その関係の手続上からも関係者の同意を得られないことからも、お墓に行けない・・・それで・・・。で、ぶっそうな物って?」 「分かりません。本人が道具は用意した、って言うんです」 「よし、今から行く。黒川さんも、何を言うてるんじゃ全くぅ。ユウくんのこともあるのに」 「でしょ。止めて下さい。ことが終ったら北嶋君に話してくれ、彼は解かってくれる、って仰るんです」 「遺族説得が最終的に不調に終ったんやろ。調査員の制止を振り切っての行動やろうなな・・・。分かった行く。松下さん、君は東京に向かいなさい」
息子の結婚式は明後日だ。後日詳しく話せば妻も息子も、そして新婦:友華も式欠席を納得してくれるだろう。この話が通じるだけの関係を築いて来たとは言い難いが、人が生きて行く上で避けられない岐路、遭遇する選択場面での優先順位の決定基準を変更する気はさらさら無い。 妻に概要を伝えた。止める妻ではない。ただ、出かけるとき、妻が最後に玄関先でこう言ったのだ。 「気を付けてな!脚まだ完全やないんやから・・・。その歳で逮捕なんかもう絶対アカンで! 帰ったら、こうして急遽沖縄へ行かなきゃならなかった理由、それをあんたなりに書いたらええよ。読ませてもらうよ」
連載 79: 『じねん 傘寿の祭り』 八、 しらゆりⅡ <6>
八、 しらゆりⅡ⑥
———————————————————————————————————————————————
ドアをノックする音の強度で訪問者が男だと分かった。 病室は空調が効いていて程よい温度なのだが、窓のカーテンは閉じられている。強い西陽を避けるためだ。 左右から引かれたカーテンが中央の重なる部分で十センチほど隙いている。その隙間から外が見える。病院のすぐ側を走る私鉄の線路が見えた。 裕一郎は、ギャッチ機能で背を立て半座位になって、高架ではなく土を盛り上げた路盤に敷設された線路を何と言うのだったかな・・・とボンヤリ考えながら外を見ていた。ちょうど、電車が走り抜けるところだった。防音が行き届いているのか気になるほどの音量ではない。入院して一週間、電車の音が気になって眠れないということはなかった。 ドアの方へ首を捻ると若い二人の男女が入って来た。 「戻って来たと思うたら早速これかいな。どこまでオカンに迷惑かけたら気が済むねん?」 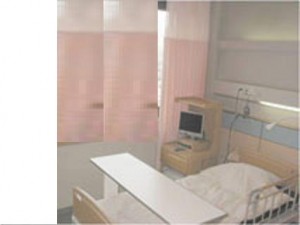 「ちょっと、央知さん」。女性がたしなめる様に男の袖口を引いている。男は怯まず続ける。 「オカンはお人好しにも自分が引越しに呼び戻したばっかりに・・・と悔んどるんや。そんなことにも気付けん人なんやこの人は・・・」 女性は、息子:央知の詰問を遮ろうと半歩前に出て言う。 「始めまして・・・。上杉友華と申します」 「この人と来月結婚するんや。」 「始めまして。父親の裕一郎です。そうなんですか、おめでとう」 息子は三十二歳だったと思う。裕一郎が些細なことから単身生活を開始した頃、すでに会社員で広島を皮切りに転勤を繰り返していた。今は本社勤務となり京都に居る。姉がいるが彼女は結婚して横浜に住んでいる。その頃家はすでに裕一郎と妻の二人だった。 「独りでやって行けると証明できたんか、独りでは無理やったと思い知ったんか?」 「証明しようとなんか思うてないよ」 「出て行った理由をオカンに説明できたのか?」 「いや、解からんやろう」 「自分に対しては出来てるのか?」 「それはもっと解からん」 「何やねんそれ、独り旅ってか、贅沢な・・・。何の責任もないガキが、カッコ付けて北へ行くみたいな自己愛だけの放浪かい?」 「俺は南へ行ってたんや」 「茶化すなよ。まあええわ、罰当たって脚折ったんやな。姉ちゃんもそう言うとるぞ」 「央知さん・・・」上杉という女性が、又央知の袖口を引いている。
「ちょっと、央知さん」。女性がたしなめる様に男の袖口を引いている。男は怯まず続ける。 「オカンはお人好しにも自分が引越しに呼び戻したばっかりに・・・と悔んどるんや。そんなことにも気付けん人なんやこの人は・・・」 女性は、息子:央知の詰問を遮ろうと半歩前に出て言う。 「始めまして・・・。上杉友華と申します」 「この人と来月結婚するんや。」 「始めまして。父親の裕一郎です。そうなんですか、おめでとう」 息子は三十二歳だったと思う。裕一郎が些細なことから単身生活を開始した頃、すでに会社員で広島を皮切りに転勤を繰り返していた。今は本社勤務となり京都に居る。姉がいるが彼女は結婚して横浜に住んでいる。その頃家はすでに裕一郎と妻の二人だった。 「独りでやって行けると証明できたんか、独りでは無理やったと思い知ったんか?」 「証明しようとなんか思うてないよ」 「出て行った理由をオカンに説明できたのか?」 「いや、解からんやろう」 「自分に対しては出来てるのか?」 「それはもっと解からん」 「何やねんそれ、独り旅ってか、贅沢な・・・。何の責任もないガキが、カッコ付けて北へ行くみたいな自己愛だけの放浪かい?」 「俺は南へ行ってたんや」 「茶化すなよ。まあええわ、罰当たって脚折ったんやな。姉ちゃんもそう言うとるぞ」 「央知さん・・・」上杉という女性が、又央知の袖口を引いている。
石垣島の民宿のベランダで電話で話したとき、妻は「引越しするから手伝いに来る?」と乗りやすい依頼を振ってくれた。引越しを手伝うという大義名分を得て、求めに応じて帰阪したのだ。その引越しを終え、小物を運ぶ為に借りていたレンタカーを返しに行く際、事故に巻き込まれた。 坂道を下った処に在る大きな交差点、赤信号で停車していた。裕一郎の車は前から四台目。すぐ後ろにもう一台乗用車が停まった。 右折車用に右折車線があり、直進車は左車線に並んで停まっている。バックミラーに大型のトラックが写った。そのまま進行すれば、右折車線に進むことになり、交差点まで進んでは車線変更出来ない。直進したいのだろうそのトラックが左車線に割り込もうとした。加速しているのではないか、強引だなぁと思った瞬間、ガチャーン・グチャっという音がして、前後から挟まれた車は大破。後ろの車を含めた計五台は押し出され最前列の車は交差点の中にいる。裕一郎はどこでどうなったのか判らぬまま、激痛走る左脚を引きずり車外に出た。後ろの乗用車の運転者はまだ出て来ない。最前列の軽トラックはワインを満載していて、道路に瓶が散乱して、割れた瓶からワインが流れ出ている。ほどなく、全運転者が車外に出てきた。奇跡的に全員命に別状は無いようだ。ガソリンの臭いが漂って来た。引火の恐れありと誰かが指摘して、車との距離をとった。信じられないことに、裕一郎の車は、大げさに言えば運転席と後部座席が引っ付いていた。 衝突して以降のことは何が何だか分からないが、直前のトラック割り込みに至る映像だけは、スローモーションで再現できた。 救急車が来て、全員が病院に搬送された。激痛の脚は骨折していた。挟まった足首がカエルの足が捻れたような状態でのことのようだ。くるぶし=腓骨の下部の骨折ということだった。左足膝下から指の付け根までギブスを固定した時には、内出血で爪先に血が溜まり腫れて濃紫色を帯びていた。二週間で退院。ギブスを外すのに四十日前後、松葉杖なく自立歩行できるようになるには二ヶ月強を要すらしい。 央知に言われるまでもなく「罰が当たった」と思った。 当然、まだ引越し先では一度も寝起きしていない。退院すれば、そこへ帰ることになる。 裕一郎は、受容れてもらうための当然のペナルティを支払ったのだと納得していた。そのペナルティの支払いにも妻の介助介護を必要とするのだが・・・。しかし、怪我は痛く不自由なのだが、たぶんそのお陰で妻が積もる言い分の発言を手控えたと思う。いや、ほとんど言わなかった。代わりにこう言ったのだ。 「退院したら、家を空けてまで過ごした『お値打ち』の日々を、書いてみたら? せめて沖縄三ヶ月だけでも・・・。読んでやるよ」 値打ちなどありはしないのだ、困った。『お値打ち』か・・・。
「あと一週間初期リハビリをして退院や。しばらく松葉杖やな」 「しっかり噛み締めたらええよ」 「そのつもりや」 「結婚式には、松葉杖で無理して出席せんでもええんやで」 「・・・・・・」 「いえ、是非出て下さい。私は父が亡くなってますので有り難いです」 「ありがとう。体調が許せば出席させてもらうよ」。上杉友華が裕一郎をしっかり見てニッコリ頷いた。 央知がそれまでの口調の角をやや削って言う。 「入院費・治療費は大丈夫なんか?」 「その点は大丈夫や。事故は百%相手方に非があって、運転手も認めてる。全部保険で出る」 「収入の補償は?」 「俺、収入証明なんか無いんで、主婦扱い、主夫やな。実際、沖縄で主婦してたんやが・・・。主婦は日額七千五百円やそうな。友華さん、七千五百円ですよどう思います?」 「収入証明できる仕事を続けます」友華が笑って返した。亜希と変わらぬ年齢だろう彼女の毅然とした返しを聞きその笑顔を見て、央知がこの女性を選んだことに頷き、「息子をよろしく」と念じていた。
二人が帰った後、不覚にも涙がこぼれた。 ユウくんと二人の生活をして見せると宣言し、曲りなりに、実際相当曲がっているが、曲りなりに続けている黒川、松山の温泉旅館従業員寮に居る美枝子、沖縄から再びかの地へ発つだろう亜希、黙して若い女性と別れたのだろう高志、やはり放蕩には違いない数年の果てのうらぶれ男を受容れた妻、彼らの人生・・・それが押し寄せてくるのだった。 それは、怪我・入院という苦境ゆえの弱気だけが思わせた心情ではないのだ、そう自覚していた。
(八章、しらゆりⅡ 終 次回より エピローグ)
歌「100語検索」 34、 <散>
散
桜は嫌いだ!
別・離・忘・去・逃・棄・折・流・ちぎれ・倒 (http://www.yasumaroh.com/?cat=26 )それでも納得しない「お国」は「砕けよ」「散れ」と言っている。 「散る」はそれこそ修復不可能、命の終わりだ。
花と言えば「桜」だと、一体誰が決めたのだ。 古来、花は「梅」だったと思う。花が命を終える場面を表す日本語は実に見事にその瞬間を捉えていて感じ入る。桜は「散る」、椿は花びら全てが一気に落ちるので「落ちる」と表し、罪人の斬首を連想させて喜ばれない。 牡丹は大きすぎて自らの重みに耐えかねるように朽ち行くので「崩れる」と表す。 梅の花は独り密かに命を終えるが、その様を「こぼれる」と表し奥ゆかしい。 桜のあの散り際は、どうも騒々しい。辺り一面にこれでもかと花びらを撒き散らし、前夜までのバカ騒ぎ酒宴を呪うように人間どもに反撃している。 桜をネタに呑み騒ぐ人間(もちろん私を含む)どもも、これ見よがしに咲いた挙句過剰な反撃に出る桜も、どうも好きになれない。 桜に責任はないが、好きになれないのにはもうひとつ理由がある。 仏教用語「散華(さんげ)」を拝借僭称して、「お国」の為に命を失った人々の最期を表すに使った詐術のことだ。 「散華」:仏や菩薩が来迎した際に、讃嘆するために華を撒き散らし降らしたという故事にちなんで行なわれる。 法要などに散華が行なわれ蓮などの生花が使われていたが、蓮華を模った色紙で代用する。 ここから、「散る」に最も相応しく儚さを象徴する花を求め、日本人(?)の死生観・無常観・「もののあはれ」など儚さを美しく感じる風土感性(?)にマッチするとして、見事に散る桜の花を散華のシンボルに誰かが祀り上げた。 日本軍兵士の戦死を美化するに際して、「玉砕」とともにそれを美化する表現として「散華」が採用されたのだ。もちろん、事故・病死・空襲・非戦闘員・他国の兵士のそれは「散華」とは言わない。【ウィキペディアより要約】(靖国の合祀基準そっくりだな) そして軍国用語とされちまった「散華」のその華は下記歌謡にもある通り「桜」なのだ。 ところで、先日偶然、万葉集に登場する植物ベスト・テンを知った。(数字は登場回数)
 1.はぎ(萩)141 2.うめ(梅)116 3.たちばな・はなたちばな(橘・花橘)107 4.すげ・すが・やますげ(菅・山菅)74 4.まつ(松)74 6.あし(葦)55 7.ち・あさぢ(茅・浅茅)50 8.やなぎ・あをやぎ(柳・青柳)49 9.ふぢ・ふぢなみ(藤・藤波)44 10.さくら(桜)41 「桜」は何と第10位と下位だ。
1.はぎ(萩)141 2.うめ(梅)116 3.たちばな・はなたちばな(橘・花橘)107 4.すげ・すが・やますげ(菅・山菅)74 4.まつ(松)74 6.あし(葦)55 7.ち・あさぢ(茅・浅茅)50 8.やなぎ・あをやぎ(柳・青柳)49 9.ふぢ・ふぢなみ(藤・藤波)44 10.さくら(桜)41 「桜」は何と第10位と下位だ。
ひとはいさ心もしらずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける(紀貫之:古今集) これは、前段に、『初瀬に詣づるごとに宿りける人の家に、久しく宿らで、程経て後に至れりければ、かの家の主、かく定かになむ宿りはあると、言ひ出だして侍ければ、そこに立てりける梅の花を折りて、よめる』とあり間違いなく梅。 東風吹かばにほひおこせよ梅の花主なしとて春を忘るな(菅原道真:901年、京を追われるに際しての作歌とされる。拾遺和歌集) これらは梅だが、この前後から梅から桜への変遷があり、それは古今集編纂前(905年奉上)の時代だと言う。 ヤマトが全国制覇(701年。唐、列島を代表する王権として大和を認知。呼称を「倭」から「日本」に改める。旧唐書:『倭伝』のあとに『日本伝』あり。『或いは云う、日本は旧(もと)小国、倭国の地を併(あわ)せたり』と記載されている )、を成し遂げて以降、 つまり品川宿「たそがれ自由塾」が主張する「倭」(九州王権)から「ヤマト」(近畿天皇家王権)への覇者移行の後二世紀の間に、梅~桜の主役交代があり、根深い事柄だと思う(勉強不足で直感でしかありません)。 *品川塾塾頭は、紀貫之も菅原道真もよく知る古の九州王権の存在を匂わせているのではないか、と考えています。 梅は中国出自の植物で、万葉では大宰府での歌や貴族の庭に咲いているのを詠んでいて、東国の歌には登場しないそうだ。やがて桜が花の主役となった。 「桜」が、軍国日本が差し向けたサクラ(啖呵売の仕込み偽客)役の呪縛から解放され本来の桜に戻るなら、その美しさ・「あはれ」を認めもしたい。このままでは、桜の側も迷惑だろう。
『同期の桜』 http://www.youtube.com/watch?v=yY6WraxaTZk&feature=related 作詞:西条八十 『名月赤城山』 http://www.youtube.com/watch?v=rEF4UGJhHZs 東海林太郎 『この世の花』 http://www.youtube.com/watch?v=6_rSk4-EOlk 島倉千代子 『緋牡丹博徒』 http://www.youtube.com/watch?v=1r-K-FSyiBA 藤純子 『終着駅』 http://www.youtube.com/watch?v=DxRV_Txt3bw 奥村チヨ 『恋人よ』 http://www.youtube.com/watch?v=HM_2yAW_vZg 五輪真弓 『エリカの花散るとき』 http://www.youtube.com/watch?v=dParcpK1DAM 西田佐知子 『昴』 http://www.youtube.com/watch?v=I0oq0k2GfIc 谷村新司 『ひとり咲き』 http://www.youtube.com/watch?v=_cmcjSmBlXY チャゲ&飛鳥 『さくら(独唱)』 http://www.youtube.com/watch?v=KnjxtkgrFh4 森山直太郎 『島唄』 http://www.youtube.com/watch?v=DKB41krUnVU 宮沢和史
他に沢山ある。日本人は「散る」が好きなのか? 何せ、かつて人々は内に抱えた心情の行く先を「散る」へと収斂させる力学下に生きざるを得なかったのだ。戦後そこから出たはずなのだが、何やら雲行きは怪しい。そこへ行くと、女性の「散る」は「お国」の要請ではなく、己一人の決断で桜本来の「散る」を奪い返しているように聞こえるのだが、それはぼくだけか? ともあれ「散華」(パクリ、僭称の)はまっぴらだ。
『ジョニーの子守唄』アリス、 『東京流れ者』渡哲也、 『夢は夜ひらく』藤圭子、 『学生時代』ペギー・葉山、 『網走番外地』高倉健、 『湯の町エレジー』近江俊郎、 『東京ラプソディー』藤山一郎、 『伊勢佐木町ブルース』青江美奈、 『からたち日記』島倉千代子、 『花咲く乙女たちよ』舟木一夫、 『空に星があるように』荒木一郎、 『花と蝶』森進一、 『大利根無情』三波春夫。