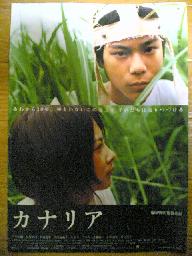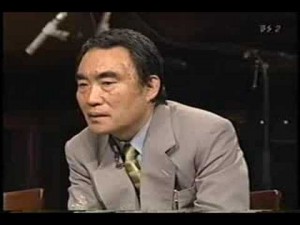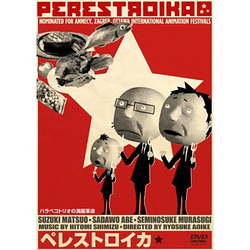歌遊泳:いとしのエリー
20数年の昔。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
たそがれ映画談義: 『カナリア』
そう、これはオーム真理教をモデルにした映画だ。
「人間の共同性と全き個人性の相克」といふ永遠の課題が迫り、
物神崇拝へと至る呪縛から主体的に免れることの隘路と困難、
「個人の復権」への苦闘が痛かった。
「皇国少年の自己解体」と、彼らの戦後の自己再生や、
座標軸喪失症候群、あるいは総撤退・総封印(一切放棄)の「病」を想った。
実は、そこが「共闘」や「連帯」が始まる契機であり原圏なのだ。
若い元信者:伊沢(西島秀俊)の、少年:コウイチ(石田法嗣)への問いかけ
『教団もまた我々が生きているこの醜悪な世界の現実そっくりの、もうひとつの現実だった』
『お前は、お前が何者であるのかを、お前自身で決めなくてはならない』は、13歳コウイチにはあまりにも酷で、難しい。・・・痛々しい限りだ。 社会性を抜きには生きられない存在たるぼくら大人が抱える課題なのだから・・・。
この少女(の母性)にして初めて可能だったと思えるのだった。
谷村美月。 2007年『檸檬のころ』では、素晴らしい若手女優さんに成長していた。
書評: 脇田憲一著『朝鮮戦争と吹田・枚方事件-戦後史の空白を埋める-』(明石書店)
|
【イントロ部】
三浦雅士はその評論集『青春の終焉』(2001年 講談社)の前書きをこう始める。
――「『さらば東京! おおわが青春!』 続けて、青春や青年という語の起源と、発展し世に定着する過程、下って60年代後半に急速に萎んでしまった背景などを語っている。例えば「伊豆の踊子」では、青春がエリート層の旧制高校・帝国大学という制度による囲いこみによって維持された、つまりは階級による特権者の独占物であったと語り、主人公はまさにその青春に在り、登場する人々、踊子も栄吉やその女房も青春とは無縁だったと述べる。60年代後半の学生反乱こそは、そうした永く続いたエリート層・特権者の独占構造の大衆化を通じた解体過程、青春の終焉であったと言う。青年という語にはあらかじめ女性を排除する思想性が間違いなく付着しているし、それは保護者の会を父兄会と呼び、労組などでも若い男性と女性全部を一緒にした部会を作り、青年婦人部と呼んでいたことにも正直に表れているとつなぐ。 事実、70年を前にしたぼくの学生期には、所得倍増の「成果」が創り出したその特権の大衆化の中で、青春や青年といった語は、臨終直前であり、やがて青春・青年はダサい気恥ずかしい言葉として姿を消した。三浦氏が言うとおり、青春文化・青年文化とは呼ばず、代わって若者文化と称したのだ。 (以下、カルチャー・レヴュー37号、http://homepage3.nifty.com/luna-sy/re37.html#37-2) |
たそがれ映画談義:『サイドカーに犬』
たそがれ映画談義:『百万円と苦虫女』
我ら二人、偶然同じ映画を取り上げましたね。ええ歳したオッサンが二人、
ネット社会の片隅(?)で、蒼井優的若者への共感・声援の、
キーボードを密かに叩いていたのか・・・、あの苦虫女に届けたいね!
「なんとか出会って苦虫女を抱きしめてほしいと祈りながら観ていた」のは、
ぼくも同様なんです、もう泣きそうになって・・・。
学生が控えめに発した言葉「自分探し・・・みたいなことですか?」に蒼井優が返す、
「いえ・・・。むしろ探したくないんです。探さなくたってイヤでもここに居るんですから」 と。
続いて苦虫女は弟への手紙で、こう独白する。
「姉ちゃんは、自分のことをもっと強い人間だと思っていました。でもそうじゃありませんでした。」
ナチュラルであるのに、そのナチュラルこそがむしろ
生きにくい理由の根本を構成している。
という転倒状況が若者たちを覆う今どき。
ラストのすれ違いは、その「今どき」の若者が強いられる「社会」からの「要請」を、
容れて・学んで・こなして行くのではなく、ナチュラルの側に身を置き続け
その立ち姿に「アッパレ」と拍手したのでした。
この二人、苦虫女と学生は必ず再び出逢います(現実場面でなくとも)。
ナチュラルということそのものに棲む「無知・過信・無謀」を、痛手を負って思い知り、
あのラストシーンには学生君の「必死さ」に対して、「あんたには頼らないわよ」
という「見かけによらない、芯の強い女」のメッセージ性と爽快感がある
とアンケートの初稿ではそのことを書いたのですが、「見かけによらない、芯
の強い女」というのは監督の狙いではないだろうし、現在のフェミニズムの達成点は
> 「いえ・・・。むしろ探したくないんです。
> 探さなくたってイヤでもここに居るんですから」
>「姉ちゃんは、自分のことをもっと強い人間だと思っていました。
> でもそうじゃありませんでした。」
と、苦虫女に言わせる境地じゃないでしょうか?
交遊通信録:K大校友連絡会御中

 http://www1.kcn.ne.jp/~ritsu/dai3kaisiminnkouza.doc を受けて。
http://www1.kcn.ne.jp/~ritsu/dai3kaisiminnkouza.doc を受けて。歌遊泳:【緒形拳 阿久悠を語る】
歌遊泳:民子さんオホーツクを唄う
交遊通信録:趙博+織江 VS 勲章森繁
趙博の「人生幸朗的パギやん日記」11月11日分(下記転載)を読んで、大いに共鳴・・・。彼のホーム・ページ「黄土(ファント)通信」(http://fanto.org/index.html)のパギやん似顔絵が共通の友人の作だという“えにし”もあって、森繁的「胸に勲章」文化に抗おうとする彼の芸の心と志を、そして激しい言葉を吐いた気持ちを、考えた。
(人生幸朗的パギやん日記、11月11日)
So, what?
森繁が死んだ。大衆芸能の分野で文化勲章を初めて貰った大俳優…あははは、大阪を裏切ってのし上がっただけやんけ。藤山寛美の森繁批判を鮮明に覚えている。「大阪の人情をよう演じん人間が、虐げられたユダヤ人を演じられるか。東京は大根役者ほどウケまんねんなぁ…」
市橋が逮捕された…またぞろ馬鹿マスコミが大騒ぎ--ぬるいのぅ。11・8沖縄県民大会は報道しなかったよねぇ…、ねぇ、マスコミ諸君。
趙博+織江 VS 勲章森繁
森繁の「社長シリーズ」は、中小企業社長を面白おかしく相対化していて、
観客に「君もやがて社長かも」と、社長業などは手が届く世界なのだよと示し、
サラリーマンと呼ばれた層に「安心」を提供し、支持されたのだと思う。
サラリーマンの悲哀を抱える観客は、加えてもうひとつの「安心」も手に出来たのだ。
20世紀後半、先進国の「都会に出て職に就く」亜インテリ層、企業社会の悲哀(例えば映画なら、『セールスマンの死』『アパートの鍵貸します』『アレンジメント』、日活『私が棄てた女』に見える)・・・
つまり故郷を離れ、貧しくも苦労して高学歴を得、管理的職責に在り、
心ならずもか望んでか、
企業内的上昇志向に染まって成し遂げたささやかな成果と、
否定しようも無くその成果を得んが為に、踏み放ち・打ち棄て・断ち切った「大切なことども」・・・・。
たぶん「社長シリーズ」は、その「事実」を忘れさせてくれたのだ。
自分は、あくせくサラリーマンの処世街道を生きている。けれど、
上り詰めたところで、所詮ほらこの通りのバカ騒ぎの社長様だ・・・。
だから、それは、大東京の、
「大切なことども」を完全には「裏切れなかった」人々、
「のし上がれ(ら)なかった」人々、
そうした勤労サラリーマンにとって絶妙の「カタルシス」なのであった。
そうした観客に媚びた森繁流儀など、
そんなもん認めないぞという趙・寛美の側からの
総てを解った上での「異論」だ。
森繁が「強い」のは、そうした「地べた」からの批判をよく承知していて、
「裏切って」「のし上がった」ワシと、さあどっちが、都会の現代勤労者の心に響く?
と云わば開き直っている点だ。
が、森繁への広範な支持にはやはり、勲章だけではない理由があると思う。
観客は、『完全には「裏切れ(ら)なかった」「のし上がれ(ら)なかった」層』、
『森繁社長の言動に「カタルシス」を見出していたサラリーマン層』なのだ。
己の企業社会人生を振り返り、森繁に赦してもらう「あちら側」
に座る心地悪さといかがわしさを知らぬわけではない。
先般の両国シアター・カイでの声体文藝館『青春の門・筑豊篇』会場に、
「あちらとこちら」の境界からやって来た観客が居たのなら、
タエさんと織江、そして「織江の歌」には、
その観客を「こちら側」に踏み留ませる、あるいは呼び込む力が備わっていた。
その力の蓄積こそが、やがて大御所森繁への「異論」の体系となって行くだろう・・・。
(ダラダラとくどい当コメントは、もちろん趙さんに送信し、真摯な内容の返信をいただきました)
12月16日(水)には、品川宿での初公演。我が庵から徒歩圏内ではないか!
出張を取り止めて行こうと思う。