通信: 尖閣・竹島の現実的解決案 に遭遇
「9月14日朝、尖閣諸島付近の日本の領海に中国艦船が六隻も侵入」とのニュースが流れた。メディアはいささか興奮気味に領海・侵犯・主権などの言葉を(意識的に?)繰り返し連発していた。 某知事の購入計画ブチ上げ以来、香港の活動家の上陸、日本の国会・地方議員などの上陸、中日各界が互いに声高にナショナリズム・国家・民族・主権を叫び、街頭行動や有名人挙げての発言、反日デモと来ての、中国艦船侵入だ。事態はエスカレートしており、15日には中国全土各市でかなりの規模の反日デモがあった。 同じ15日に、たまたまTVで自民党総裁候補の記者クラブでの共同インタヴュー番組を観た。一様に「毅然とした態度」「海保の強化」「しっかりと対応」などと、民主党の対応を責める割には抽象的でよく解からない。前日だったか、朝日報道ステーションでも、古館氏の尖閣問題に関する質問「直ちに何をしますか?」にも「断固として」「海保の能力充実」などが繰り返された。中国がそれでも領海侵犯や上陸を強行すればどうするのです?と古舘氏は食い下がっていたが、具体案など誰にも無いのだ。 たぶん古舘氏は、「単身中国に乗り込んで」とか「相手のトップとの会談」などの返答を期待したのだろうが、そうした大見得は相手の強(したた)かさからして可能性低いと見ての発言自重だろう。が、「しっかり」「断固」の繰り返しでは・・・。それは、民主党も同じで、実は誰にも妙案は無い。「民主党の軟弱が・・・」論も、「某知事が火に油・・・」論も、事態の構造を考えれば、それが根本の問題なのではない。枝葉末節だ。 「いや、日本に正当性があるのだから」と言っても、そこは相手も「正当性」を持っていると主張している。歴代日本政府の言い分が歴史に照らして、国際法に照らして妥当だと言われても、互いに国家の最高機関・最高責任者の名において「我が領土である」と内外に宣言してしまっているのだ。前言撤回は構造上からも無理だ。 某知事やTV頻出の論客は、いずれも勇ましいのだが、中国がそれでも領海侵犯や上陸を強行すれば?の問いに「物理力・軍事力を行使する!」とでも答えるのか? 勝てないし、人命の殺傷を伴うぞ。国是に反する。 ぼくは、2010年11月のブログ( http://www.yasumaroh.com/?p=8800 )で、明の琉球行「冊封使」がしばしば寄港していたと知っても、 日本が、日清戦争(1894~95)の戦勝に乗じて(下関条約には記載なく)実効支配したのだと知っても、 海人のものだ以上の線引きに与することは保留したい、と書いた。 そして、中国のものでもヤマトのものでも明治政府のものでもありはしない、と書いた。
今、具体的で根本的で、無効に見えて実は一番有効な解決策(だと思われる)案を準備している人が居ると聞き、その案を入手した。日本だけが引き下がるんじゃないのだ。互いに「我が領土」と言っているのだから、そこは互いになのだ。その一線を超えられるか、という課題は、為せば「東アジア」総体が世界から尊敬を得るばかりでなく、「北東アジア共同の家」構想への一里塚にもなる。案をここに転載する。 当ブログ読者諸氏、どう思われます? ネット・ツイッター等で波を広げる動きを作ろうと考えているらしい。賛同する? 現在、この案に添える「アピール文」(仮題:戦争無き互恵の為に、歴史的妥協を)を検討中だそうだ。
【案】 文案第一号 Ø戦争なき互恵の未来のために誇らしき歴史的妥協を! Ø荒れ狂う領有権主義への歯止めシンボルとして、非武装共同管理緩衝地帯の創設を! Ø所有者なき海の尊厳を海に返還しよう! Ø国家に見放されてきた離島の矜持を国家から独立していることの矜持として花咲かせよう! Ø両地域を民族的敵愾心の発生装置から和解の発生装置へと変換しよう!
竹島(独島)・尖閣(魚釣)諸島領有問題に対する解決策の提案 竹島および尖閣諸島の領有権をめぐる日韓-日中の国家紛争を永久的に解決する方策として以下の提案をおこなう。
1.竹島(独島)は日韓両国の共同管理区域とし、両国はその領有権を永遠に放棄し、その旨を国際社会に通告する。 2.竹島(独島)は一切の軍事施設をおいてはならない非武装の無人地帯として共同管理される。 3.竹島(独島)ならびに協議のうえ決定された範囲の周辺海域に対する漁業権を両国は放棄し、その海域を漁を禁止された漁業資源保護区として共同管理する。 4.同海域に漁業資源以外の天然資源(石油、天然ガス、レアアース、等)が発見された場合は、その採掘を凍結するか、採掘する場合は完全に均等の出資に基づく共同管理採掘会社を設置し、その採掘資源を均等に両国に配分する。
同様の条約が尖閣(魚釣)諸島に関して日中両国によって結ばれる。すなわち、 1.尖閣諸島(魚釣)は日中両国の共同管理区域とし、両国はその領有権を永遠に放棄し、その旨を国際社会に通告する。 2.尖閣(魚釣)諸島は一切の軍事施設をおいてはならない非武装の無人地帯として共同管理される。 3.尖閣(魚釣)諸島ならびに協議のうえ決定された範囲の周辺海域に対する漁業権を両国は放棄し、その海域を漁を禁止された漁業資源保護区として共同管理する。 4.同海域に漁業資源以外の天然資源(石油、天然ガス、レアアース、等)が見つかった場合は、その採掘を凍結するか、採掘する場合は完全に均等の出資に基づく共同管理採掘会社を設置し、その採掘資源を均等に両国に配分する。
通信録: **さん、セイキョウ・リジ やめるって? やめたらアカンで!
半「公」的存在の社会的使命 と 社会的アドヴァンテージ
**運動? **の闘い? **組合? **生協? **NGO? 【生協のはじまり】 世界で初めて生協が誕生したのは、1844 年、イギリスのロッチデールという小さな町の職工28 人が「ロッチデール公正開拓者組合」の店を作ったことにはじまる。当時イギリスの労働者は、産業革命のあおりを受け、低い賃金と高い物価、悪質な商品に悩まされていた。
何とか苦しい生活から逃れようと考えた末、週2 ペンスの積み立てを続け、1 年かけて1人1 ポンドずつのお金を出し合って、安心して利用できる自分たちの店を持った。この店が生協のはじまりで、その時に決めた運営原則は「ロッチデールの原則」として世界中の生協の中で今も受け継がれている。( http://202.252.170.6/research/staff/kado/06ch2.pdf#search=’ 生協の理念と歴史 より) 営利目的ではない社会的営みが経済活動を伴う時、中枢メンバーは初期運営理念のよほどの反芻確認と運営を支える人々への各種配慮に努めないと、その営みは持続しないし変質すると思う。そのことには無頓着なのに維持出来ているという不可思議が続いているなら、それはその営みが経済活動に純化し、中枢メンバーの経済基盤が安泰だからに過ぎない。そしてそこには、間違いなく一般企業のような風土が育っているはずだ。 恣意的な人事・奇妙な労務政策・業務の外注・専従職員のモチベーションの溶解・初期理念に基づいた活動の形骸化・意思決定作法の不可解・参加者の発意の減少・パワハラ・不当労働行為・専横・私利・・・・・・などが目立ち始めれば、その組織は経済的領域以外では「死に体」だということだ。そして、しがみ付いている虎の子の「経済的領域」自体が、やがて大崩壊するか、モーレツ企業顔負けの「儲け主義」として存続するか、のいずれかを選ぶことになるのだ。かく言うぼくはその轍を踏んだ身だ。天罰も食らっている。だから、他者のことはいっそうよく見える。 分かりにくい文でしょう? そう、具体を書けば何処の何を言っているのか関係者には分かるので控えているのだ。いや、言わせてもらおう。
営利目的ではない社会的営みが経済活動を伴う時、中枢メンバーは初期運営理念のよほどの反芻確認と運営を支える人々への各種配慮に努めないと、その営みは持続しないし変質すると思う。そのことには無頓着なのに維持出来ているという不可思議が続いているなら、それはその営みが経済活動に純化し、中枢メンバーの経済基盤が安泰だからに過ぎない。そしてそこには、間違いなく一般企業のような風土が育っているはずだ。 恣意的な人事・奇妙な労務政策・業務の外注・専従職員のモチベーションの溶解・初期理念に基づいた活動の形骸化・意思決定作法の不可解・参加者の発意の減少・パワハラ・不当労働行為・専横・私利・・・・・・などが目立ち始めれば、その組織は経済的領域以外では「死に体」だということだ。そして、しがみ付いている虎の子の「経済的領域」自体が、やがて大崩壊するか、モーレツ企業顔負けの「儲け主義」として存続するか、のいずれかを選ぶことになるのだ。かく言うぼくはその轍を踏んだ身だ。天罰も食らっている。だから、他者のことはいっそうよく見える。 分かりにくい文でしょう? そう、具体を書けば何処の何を言っているのか関係者には分かるので控えているのだ。いや、言わせてもらおう。
品川宿『たそがれ自由塾』:塾頭として、ハッキリ言っておく。(団体戦、個人戦とも いつでもOKやで。応酬しますか?) 実質賃金減少+消費税アップ攻撃の世、扱い額が巨大化したからと言って、活動費基準と職員や理事の報酬を上げることなく、すでに十分な報酬を得ている中枢メンバーの報酬をたとえ数万円でも上げるなら、今すぐ「生協」の看板を降ろして営利企業だと公言しなさい。 政治課題を取上げるに、選挙での特定候補応援はOK、反原発は政治的に過ぎるなどという恣意的な線引きを再び行なうつもりなら、 直ちに政党支部にでも名称変更しなさい。 パワハラ、恣意的な人事異動、職員への退職勧告を繰り返すなら、「生活」「協同」「組合」の、その、いずれの言葉も返上しなさい。 友人の会社は、自己破産したが、手形の裏判も借入の個人保証も当然彼が担い彼個人も自己破産した(債務、ン憶円)。これは特別なことではなく、世の中小零細企業・一人親方の個人事業主は、誰も皆そうしたリスクを抱えて経営している。 そちらではどうだ? 専務か常務か知らんが、ナンボのリスクを負ってるンや?まるで、「親方日の丸」やないのか! 税法上も、固定資産税や法人税における非課税特例(優遇税制)を受けている。 それは有り余る資金で御殿(?)等々を建て続ける巨大宗教団体への優遇税制のように不当なのか? 決してそうではないのだ。 なぜか?・・・ 戦後の農地改革・婦人参政権などを始めとする戦後改革の一環で1948年に成立した『消費生活協同組合法』にも明記されている理念によっている。公開の原則・民主的管理・教育促進などが謳われ、『生じた利益は全組合員に帰属する』とその協同性が高らかに宣言されている。それは、まるで9条のように輝いて尊いのだ。 つまり、一般企業以上の規模の商いをしても、経営陣(と言って悪ければ執行部)は世の企業主に比して限定的なリスクで、「親方日の丸」のようで済まされるのは、生協が「社会的存在」だからである。つまり「公」を抱えて存在しており、「私」企業ではないのだ。 「消費生活協同組合法」施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03404001001.html 薄給で勤めろ、ボランティアしろ、極貧に耐えろなどとは言ってない。 われらと我等の事業は「公」でもある、そのことに恥じない対応、襟を正した佇まいに戻りなさい。そう申し上げている。すでに一般企業水準と同等かそれ以上の報酬を得ているではないか。 各種取組・教育の活動費・必要資金はいつも不足し、ときに「やる気のある者」の自腹じゃないですか! 雨の日も嵐の日もやって来てくれる、配送部門のお兄さんの労働条件はどうですか? 兄さんと話し合ったことありますが、いろいろ聞いてますよ。 組合員理事さんは、幼い子を抱え自分の仕事を持ち、残った僅かな時間で時に深夜に企画書を書き・情宣チラシを作り・通信を発信している。 これら、活動費や配送職員・組合員理事さんの待遇考慮(保育体制など)に優先して、一握りの者の報酬を上げなければならないとは、とうてい思えないのです、消費税アップを前にして・・・。 現在の活動領域を越え、 地域の子育て「力」の復権(若いお母さんへの子育て教室、学童料理教室など)、福祉や高齢者の自立・共生(ケアハウス、グループホーム、特養など)、生活総体を対象に新たな挑戦(男性高齢者予備軍への家事炊事教室など)も構想していると聞けばこそ、 生協活動に集って来る有意の人々の「やる気」を挫くような対応には、あえて厳しく申し上げた次第。 ワシを怒らせるな! 以上。 「生活」「協同」「組合」、その原点に立って下さい。生協を取巻く消費経済状況の困難さは承知しております。 お心当たりの団体からの返答を待ちます。当方、もちろん公開での討論でもOKです。
たそがれ映画談義: 『桐島、部活やめるってよ』
http://www.youtube.com/watch?v=KjjG0WTQ6C4
YouTubeへの投稿より一篇転載: 痛いです。ものすごく痛々しい。 最初は「あ~こういう奴いたな」「自分はこっちグループだったな
『桐島、部活やめるってよ』(12年、現在公開中) http://eiga.com/movie/57626/ 監督:吉田大八、 聞いた名だと思ったら、 『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』(07年。佐藤江梨子、永作博美) http://www.phantom-film.jp/library/site/funuke/ 『クヒオ大佐』(09年。堺雅人、松雪泰子、満島ひかり) http://www.youtube.com/watch?v=6NCvrZpazWE 『パーマネント野ばら』(10年。菅野美穂、池脇千鶴、小池栄子) http://www.youtube.com/watch?v=GEN8BKixi74 (http://www.yasumaroh.com/?p=6286)と その全作品を観ていて、しかも結構お気に入りの作品たちだったのだ。今回、四作目を拝見。
素晴らしい映画でした。バレーボール部のエース:桐島が部活をやめるらしい。桐島は所在不明。 たぶん作者の分身だろう帰宅部の菊池と映画部の前田を始め、中学時代大学生と付き合っていたと噂される桐島の彼女梨紗、ちょっと大人でクールで冷静という名の処世術を手放さないカスミ、桐島の代役を押し付けられた技量不足の風助に感情移入するバトミントン部の実果(個人的には女子の中で一番気になりましたが、ラスト近くバレーボール部の練習時に風助へのシンパシーを口にする。あれはいけません、黙っていなさい)、帰宅部菊池への不器用な片恋に悩む吹奏楽部部長の亜矢・・・・・・ 不在の桐島(最後まで桐島は登場させない)への距離、今居ないことへの感慨、事態からそれぞれが「自身の部活・非部活・高校生活」を問い始める。二年生。彼らの中を順に視点を移動させながら事態を立体的に描く手法も、実に上手く行っていた。 ぼくの高校時代とは違う生徒達の表現の「直截性」や「可視性」に違和を感じながら、時代を経て変わらない彼らの「俗情」「邪心」「シャイ」「秘めた真剣」「ついそうしてしまう茶化し」などなどに安堵したりで、現代高校生の生態と状況を見事に切り取っていると、知りもせず思うのだった。 現在(いま)を切り取っているとして、しかし、ここに登場する準エリート(地方の二流以内の公立進学校生)ではない、いわば四流五流校とされる高校・落ちコボレ・引きこもり・逆にアウトローとして街に出る・・・などの貧困(経済的、状況的、精神的に)高校生を描く映画を撮らねばならない義務を、監督:吉田大八は負ってしまった、と思う。そうしてこそ、両側から時代に迫れるのだろう。 作者は『桐島・・・』に教師や親を登場させないのだが(そこがまた素晴らしい)、そしてまた政治や社会への回路もあえて描きはしない。説教調で浅はかな取って付けた社会性ほど不快なものはない。生徒たちは、狭いムラで「自分たちだけ」の「自己責任(?)」において事態に対処し解決してゆくのだとでも言うように、幼い「大人」なのだ。その「大人」観察眼の自制的な目線は、あるリアルを捕らえる吉田流の作法でもあるようだ。 その先に当然現在(いま)が在り、社会が在る。 吉田大八はここで描いたリアルをバネに、前述した底辺(?)校やドロップアウト生の掴み難いリアル、それをたぶん違う方法で掴み描くだろうと思う。だから吉田大八には、自身の地域活動を「世田谷方式」などと高く自己評価(大塚英志から「ファシズムを下支えするモノへの転化」の可能性を皮肉っぽく指摘されてはいるが)して悦に入る(?)宮台真司に感じたような、ハイソエリート主義(?。失礼)への遠疎感は抱きはしなかった。 続編、期待したい。
それにしても、優れた作品(だとぼくが思っている)を含めて、強圧にも誘導にも譲ることのない固有性と 出来事の背景を抉り出す鋭い社会性と 人々を仮当事者へと叩き込まずにはおかない迫真性と 現在(いま)を射抜く全体性を湛えた「堂々たる」日本映画に久しく出会えていないような気がする。 例えば、ヴィスコンティの『山猫』、ベルトルッチ 『1900年』、内田吐夢『飢餓海峡』、小栗康平『泥の河』なんてね・・・。 何が、微細化し「私」化し俗欲化しているのか? そこは、「美しい」ものたちがいくらでも浸透できる液状化した砂地だというのに。
、
ぼやき: シンゾウ君とトヲル君が、 「美しい(?)」国柄の「価値観」を共有。
「維新の会」と安倍元首相。
「維新の会」が安倍元首相との連携を進めるべく動いたとの新聞報道。維新の代表になってくれと言われたという情報まである。ご指名に預かった安倍氏の側も妙にはしゃいでいるそうだ。数年前の出来事(政権投げ出し)が恥ずかしくはないのかと言われながら、秋の自民党総裁選挙に立つそうで、維新との連携に進むのだそうだ。 さっそく「あの政権プッツン投げ出しの{お坊っちゃま極右}はかえって好都合、日本の有権者はあの辞め方を簡単には忘れないよ。{美しく}共倒れしてくれるのではないか?」と楽観論が出ている。  そうだろうか? 日本の有権者は、簡単に忘れることにかけてはプロだよ。 元首相は、辞任(投げ出し)後半年ほどの段階で「ぼくの登場のタイミングが少し早かたようだ。美しい国の真意が理解される時が必ず来る。そのタイミングで再び起つために云々・・・」と周囲に捲土重来を誓って見せていたそうだ。地方行脚(?)を繰り返し、軟弱・お坊ちゃまを返上、パワーアップを図って「来るべき時」に備えて来たそうだ。尖閣・竹島・「従軍慰安婦問題」が浮上する「今」がそのタイミングだという訳か。 「維新の会」となら「価値観を共有できる」「戦いにおける同志だ」そうだが、安倍元首相の再登場が、尖閣・竹島・「慰安婦問題」を巡る「国家主義的」世論(?)を背景にして「維新の会」の人気に乗って力を得るなら「楽観論」は通らない。手ごわいと思うし、その先への流れをつくるキッカケにしたい自民党右派の伝統的DNAが前面に登場だ。
そうだろうか? 日本の有権者は、簡単に忘れることにかけてはプロだよ。 元首相は、辞任(投げ出し)後半年ほどの段階で「ぼくの登場のタイミングが少し早かたようだ。美しい国の真意が理解される時が必ず来る。そのタイミングで再び起つために云々・・・」と周囲に捲土重来を誓って見せていたそうだ。地方行脚(?)を繰り返し、軟弱・お坊ちゃまを返上、パワーアップを図って「来るべき時」に備えて来たそうだ。尖閣・竹島・「従軍慰安婦問題」が浮上する「今」がそのタイミングだという訳か。 「維新の会」となら「価値観を共有できる」「戦いにおける同志だ」そうだが、安倍元首相の再登場が、尖閣・竹島・「慰安婦問題」を巡る「国家主義的」世論(?)を背景にして「維新の会」の人気に乗って力を得るなら「楽観論」は通らない。手ごわいと思うし、その先への流れをつくるキッカケにしたい自民党右派の伝統的DNAが前面に登場だ。
「維新の会」は次期総選挙において、「みんなの党」「小沢新党」との連携は採らない一方、公明候補者が居る選挙区への立候補は見送るという。 最早明らかだろう、「維新の会」とは、議席を獲得するに最も有効なバーターを選択して公明には恩を売り、新自由主義的な経済・労働政策と、国家主義的な教育などの政策への公明の追随を担保し(すでに府政・市政で実行済)、自民右派との連立、さらには連合を考えていよう。安倍元首相が自民党総裁となるならば「維新の会」との連立ということだと思う。別の者が総裁となっても、自民内「価値観」共有派との共同歩調が始まるだろう。 「維新の会」の目指すものとは結局、 行政改革という名の 公務員叩き、職員基本条例、教育基本条例、福祉切捨て、労働者関連施設廃止、男女共生施策嫌いの施設と予算の縮減などが本音で、大阪都構想・道州制等見栄えする表向きの衣装に過ぎない政治と、 「君が代条例」、従軍慰安婦問題などでの発言、集団的自衛権行使への見解、改憲論、近現代史学習館(扶桑社・育鵬社の教科書製作者を迎えて)の創設構想に明らかな国家主義に貫かれた思想なのだ。 歴史に照らせば、ン十年前ヨーロッパに登場したあの政党の亡霊のような動きではないか。 あの時も、既成保守政党の没主体的擦り寄りがその政党の権力奪取を助けたのだが、「維新の会」旋風は、橋下という絶好のタレントを得て、戦後自民党が果たそうとして果たせなかった、国家主義・民族主義・排外主義・反民主主義・改憲政権を、本格的に登場させようとする装置として尊重されるだろう。そこに「大阪ハシズム」の根深さと根本問題がある。
国家が過剰に語られ、民族が声高に叫ばれ、近隣国への憎悪が組織され、人々が勝利(取敢えずスポーツだが)に熱狂し、外交姿勢を弱腰と糾弾する昨今(実に日露戦争直後1905年の世情に似ているではないか!)・・・、この国の国柄は、宮台真司・大塚英志の対談集『愚民社会』(太田出版、12年1月、¥1600)が言う通り「近代への努力を怠って来た」結果だろうとは思う。ヨーロッパの近現代は果てにナチス登場を許しホロコーストを生んだではないかと語って、近代の意味を否定する論にはぼくは与しない。 ところで、国柄はこんなところに表れる。お茶の間経済ジャーナリストと自称してTVに登場する、萩原博子という一見「主婦の味方」「生活から政府を撃つ」風スタンスのオバチャンまで、悪乗りして「民主党の弱腰外交が、竹島・尖閣問題を悪化させた。知識があって弁が立つ人がやった方がいい」(9/2夕刊フジ)と語るのだ。ナショナリズム称揚とそれに基づく外交選択のお茶の間説得に一役買っても、当然それに動員されたとは自覚しはしない。 大同小異はあれ、現在マスメディアが垂れ流している情報に大差はない。竹島・尖閣に怒らないのは「非国民」だと言い始めかねない論調に溢れている。石原慎太郎は「野田政権は日本人の政府ではない」と吠えている。お隣韓国では、竹島(孤島)への見解を問われ言葉を濁したKARAが、猛烈なバッシングに晒されている。
![a81693bca62d1d083e63c04fa877a1873[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/09/a81693bca62d1d083e63c04fa877a18731.jpg) 近代への努力を怠る、近代そのものの否認、近代の胎動を経ずして経済大国化、等等・・・・そのいずれであれ、ヨーロッパ的近代体験からは隔たって在って、21世紀に至ってしまっている中露日韓。 中・露・日・韓による領土問題は、どちらに正当性が有ろうが無かろうが、いずれかのナショナリズムに立脚した論からは、決して答えに行き着きはしない。 領土問題という超難問の中で、東アジア総体の「近代への努力」を、試す・行なう・挑む、その構えをまず確立したいものだ。 それができない限り、国内的には80年前のヨーロッパのあの政権の類似政権を許すことになる。 東アジアへの顔、国内の民度、それはワンセットだ。
近代への努力を怠る、近代そのものの否認、近代の胎動を経ずして経済大国化、等等・・・・そのいずれであれ、ヨーロッパ的近代体験からは隔たって在って、21世紀に至ってしまっている中露日韓。 中・露・日・韓による領土問題は、どちらに正当性が有ろうが無かろうが、いずれかのナショナリズムに立脚した論からは、決して答えに行き着きはしない。 領土問題という超難問の中で、東アジア総体の「近代への努力」を、試す・行なう・挑む、その構えをまず確立したいものだ。 それができない限り、国内的には80年前のヨーロッパのあの政権の類似政権を許すことになる。 東アジアへの顔、国内の民度、それはワンセットだ。
【蛇足】 言いたくはないのですが、某市市長選に際してのぼくの言い分( http://www.yasumaroh.com/?p=14358 )を撤回する気はありません。むしろ、ますます危惧した状況へと事態は動いているようです。あそこで「維新」の勢いを削ぐことは有効だったと思う。 いずれにせよ、「自民党の伝統的右派DNA+維新」との総力戦が始まるのだと思う。 孫にハシズム社会を遺したくはない!
、
つぶやき: 空気読み 涙見せたり 威嚇をしたり (某市長)
![G20120705003613260_view[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/08/G20120705003613260_view1.jpg) 去る7月5日某市長は、記者から大津市立中学生の自殺に関して、感想を問われ、 「イジメが自殺の原因だとする明確な証拠は無い」などとは決して言わず、 『あの事件は本当に痛ましい。子どものことを考えたら悔しいだろうし』 『ああいう問題は難しいところもあるが、もうちょっと早く気付いてあげられなかったのかと思う』と答え、声を詰まらせ 落涙してみせた。(各紙報道)
去る7月5日某市長は、記者から大津市立中学生の自殺に関して、感想を問われ、 「イジメが自殺の原因だとする明確な証拠は無い」などとは決して言わず、 『あの事件は本当に痛ましい。子どものことを考えたら悔しいだろうし』 『ああいう問題は難しいところもあるが、もうちょっと早く気付いてあげられなかったのかと思う』と答え、声を詰まらせ 落涙してみせた。(各紙報道)
直接的証拠や、加害者の関与の具体性を列挙したり保存したりは出来なかった事柄に、被害者の立場に立って構想する「知性」や、歴史性に照らした「理性」を発揮したのではなく、涙は「空気」を読むに敏なタレントとしての彼のパフォーマンスだったとすぐに分かる。
昨日、従軍慰安婦問題には次のように発言した。
橋下氏、慰安婦強制連行「証拠あるなら出して」
 【読売新聞 8月21日(火)19時55分配信】 大阪市の橋下徹市長は21日、いわゆる従軍慰安婦問題について、「慰安婦という人たちが軍に暴行、脅迫を受けて連れてこられたという証拠はない。もしそういうものがあったというなら、韓国の皆さんにも出してもらいたい」と述べ、旧日本軍や官憲による「強制連行」はなかったとの認識を示した。
【読売新聞 8月21日(火)19時55分配信】 大阪市の橋下徹市長は21日、いわゆる従軍慰安婦問題について、「慰安婦という人たちが軍に暴行、脅迫を受けて連れてこられたという証拠はない。もしそういうものがあったというなら、韓国の皆さんにも出してもらいたい」と述べ、旧日本軍や官憲による「強制連行」はなかったとの認識を示した。
大阪市役所で記者団の質問に答えた。 橋下氏の発言は、「資料の中に、強制連行を直接示す記述は見当たらない」とする政府の見解を踏まえたものだ。ただ、慰安婦問題への対応を求める韓国政府に対し、論争を提起する姿勢を示したことは、韓国側の反発を招く可能性もある。 橋下氏は、李明博韓国大統領の竹島訪問の強行について、「従軍慰安婦という課題が根っこにある。領土問題の前提として、従軍慰安婦について強制の事実があったかどうかを、韓国ときちんと議論すべきだ」と強調した。
橋下君、極東軍事裁判を始めとして、証拠や証言は数多くありますよ。 軍側の書類を証拠とし、「無い」「無い」と叫んでいるのか。 そりゃ無いわな。 例えば大前研一のような、左翼ではない人からもこんな発言がある。 http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/a/78/index2.html
「子どもの家」を廃止する一方で「近現代史の学習施設」の開設計画(「展示内容の助言を扶桑社や育鵬社の教科書編集に携わった人にも求めたい」)、集団的自衛権の行使、九条改憲・・・・橋下氏の本音がますます明らかになっている。
つぶやき: あさって20日の 銀座・五輪祝勝パレードに想う
![502932ad8a285o0640048012132983692[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/08/502932ad8a285o064004801213298369211.jpg) 前ブログに書いたように、ロンドンでの選手たちの活躍に拍手したいとは思うのだが、20日に予定されている銀座パレードの沿道に何やらいかがわしいプラカードなどが登場しそうに思う。 近隣国との摩擦に国家主義的に対処し、自分たちの政権の数年前の同じ対応を棚上げして、国民統合の好機到来とばかりに政権に対して声高に「弱腰」「軟弱」と罵る御仁が多数登場している。彼らには、「竹島は云々」「尖閣諸島はどうこう」などと叫ぶプラカードの登場は我が意を得たりというところか。
前ブログに書いたように、ロンドンでの選手たちの活躍に拍手したいとは思うのだが、20日に予定されている銀座パレードの沿道に何やらいかがわしいプラカードなどが登場しそうに思う。 近隣国との摩擦に国家主義的に対処し、自分たちの政権の数年前の同じ対応を棚上げして、国民統合の好機到来とばかりに政権に対して声高に「弱腰」「軟弱」と罵る御仁が多数登場している。彼らには、「竹島は云々」「尖閣諸島はどうこう」などと叫ぶプラカードの登場は我が意を得たりというところか。
![img_242975_62018610_0[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/08/img_242975_62018610_01-200x300.jpg) プロ野球優勝チームのパレードのように五輪での健闘を称えるのはよいことだと思うし、今後のスポーツ振興に繋がるかと思えるので否定したくはない。 けれども、野球チームという「私」をファン心理から称えるパレードと、本来選手を称えるはずなのだが、「国家」を称えたい者どもに占拠されている「(擬)公」=国家が主宰するパレードとは自ずと性格を異にしている。 震災・円高・デフレ不況・消費税政局・・・。 五輪での選手活躍の威光を拝借したい政権の思惑や、ここ幾日かの、近隣国との摩擦を巡る各種の発言を見聞きするにつけ、かつて明治~昭和の戦勝を謳った提灯行列や、戦時の壮行会行進や某国の軍事パレードを想起してしまう。 1905年の、対ロシア戦争祝勝の提灯行列+ポーツマス講和に「軟弱だ」とする抗議の市民行進、それが今再来するのか? 一体、国と民はこの100年に何を学んだのだろう。宮台真司(好きではありませんが)の言うとおり「近代への努力を怠ってきた」国柄が、今、白日の下に晒されている。
プロ野球優勝チームのパレードのように五輪での健闘を称えるのはよいことだと思うし、今後のスポーツ振興に繋がるかと思えるので否定したくはない。 けれども、野球チームという「私」をファン心理から称えるパレードと、本来選手を称えるはずなのだが、「国家」を称えたい者どもに占拠されている「(擬)公」=国家が主宰するパレードとは自ずと性格を異にしている。 震災・円高・デフレ不況・消費税政局・・・。 五輪での選手活躍の威光を拝借したい政権の思惑や、ここ幾日かの、近隣国との摩擦を巡る各種の発言を見聞きするにつけ、かつて明治~昭和の戦勝を謳った提灯行列や、戦時の壮行会行進や某国の軍事パレードを想起してしまう。 1905年の、対ロシア戦争祝勝の提灯行列+ポーツマス講和に「軟弱だ」とする抗議の市民行進、それが今再来するのか? 一体、国と民はこの100年に何を学んだのだろう。宮台真司(好きではありませんが)の言うとおり「近代への努力を怠ってきた」国柄が、今、白日の下に晒されている。
2011年3月16日天皇がマスメディアを通じて「おことば」を発した。もちろん、たぶん、東日本大震災+福島原発事故という未曾有の事態ゆえのことなのだから・・・と言うが、実に迅速で震災五日目のことだった。天皇が自ら全国民を対象にメッセージを発し伝えたのは何と1945年8月15日以来66年ぶりのことだったという。 「平成の玉音放送」と論じ、1945年と2011年に、天皇崩御に拠らない「改元」が行なわれたのだと説く論者も居る。 国柄のベイシックな「相貌」や人々のポピュラーな「心性」が、機関車の重い車輪が動き出す時のようにゴットンと動き始めようとしているのなら、今、止めなければと思うのだ。 上の画像は、2010年ロッテ球団の優勝パレード。 (ちなみに、ロッテ創業者:辛格浩氏は在日韓国人一世。女子サッカー、ナショナルチーム《なでしこジャパン》にメンバーを多数輩出しているINAC神戸のオーナー:文弘宣氏は、金時鐘さんが学園長を務めるコリア国際学園の常務理事を務め、財政支援を束ねる在日二世実業家。海峡を跨いで立つアイデンティティに学びたい。)
ぼやき: ジュードウ・競泳と 国際ルール
ジュードウへの異論も、競泳メドレー・リレー銀への賛辞も 別にナショナリズムの発露なんかじゃないよ! あえて言うなら『アンチ・偏欧米スタンダード』論なんじゃよ。
ロンドン・オリムピックはあと一日で終わる。 競泳男子メドレーリレー・男女各競泳・女子バレーボール・男女サッカー・体操・女子レスリング・・・など、驚きの活躍が続いた。 8月初旬から帰阪しての盆休暇。連日の「ニッポン」組の頑張りについつい深夜の実況を見てしまうのは事実だ。![o0378050012117159603[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/08/o03780500121171596031.jpg)
オリムピック半ばの先日、さる席で競泳陣の頑張りなどを称えたところ、 予想通り、「隠し切れないナショナリズムが顔を出したか?」と「左翼(?)」独特の聞き飽きた皮肉が返って来た。 どう思われようが構わないが、「反欧米気分」や「Pan-アジアニズム」が身の何処かに潜んでいることを自覚しているので、そこは黙っていた。 ナショナリズムじゃないんだよ。ちゃんと言うから聞いてくれ! 世界を覆う「インチキ公平、偏欧米偽フェア」に基づくルール作りへの異論なんです。
球技が苦手なぼくは、高校時代のごく短期間柔道部に居たのだが、「国際化」と引換えに点取り競技と化したとも言いたいジュードウは、柔道ではないのだとの想いを強くして来た。無理にでも数値化することが「公平」「フェア」だとする、他の競技にも見られる原型変容は、実はスポーツに限られた現象ではない。文化のみならず思想や哲学にさえ及ぶ、固有の地域が培って来たオリジナルな「文化文明」総体の価値観・価値論が「国際化」の過程で辿る変容は、つまりある種の転向でもあるのだ。 問題は、一見「公平」「フェア」に見えもする評価点数を競い合う為に取って付けた数値化が、そのスポーツならスポーツの本来持っていた価値や美学を損わないかどうか、そこだと思う。 元々、数値化には馴染まない事柄や出来事や方法(スポーツなら技など)、つまりは価値が、強引に数値化・評価点数の競い合いへと変質させられているとしたら、やはりそれは元始の原形とは「違うもの」、国際化・公平・フェアという衣装をまとった加工品=「虚構」だと言えるのではないか? しかも、公平・フェアを標榜する者たちは、その公平・フェアの基準や運用ルールを、しばしば「国際化」の推進を言い出した側の私的な都合で自在に変更さえして来た。
1956年メルボルンオリムピックで、競泳平泳ぎで潜水泳法の古川が金メダルを取ると『常に水上に頭が出ていなければならない』と新ルールが作られた。日本泳法が30年に亘り苦しんで来たのは有名だ。ルール策定者は上半身を水上に大きく出すウェーヴ泳法の確立の見通しを得た87年、1ストロークごとに1回水上に出れば良いと改正。1988年ソウル背泳で鈴木大地が金メダルを取るとバサロスタート(潜水泳法、サブマリン泳法とも呼ばれる)を10M以内に規制した(現在は15M以内)。公平に潜り、フェアにスタート後長く潜水することのどこがアンフェアなのだ? 1964年東京オリムピック・女子バレーでアジア人:日本が金を取ると、「ネットの高さを上げる」というアジア人に不利なルール変更を行なった。「公平」に、共通の高過ぎない(?)ネットで競技することの何処が不都合なのか? あまり知られていないかもしれないが、冬季スポーツにも奇妙なルール変更がある。ジャンプでは、ノルディック複合で荻原潰しを目的とした「ジャンプ得点比率の低減」を強行した。さらに長野オリムピック・ジャンプで、ノーマルヒル銀(船木)、ラージヒル金・銅(船木・原田)、ラージヒル団体金(原田・岡部・斎藤・船木)とアジア人が活躍すると「スキー板の長さは身長に比例とする」とルール変更。背の低いアジア人は、小さなスキー板で勝負せよ!という訳だ。何が「公平」なのか? そんな公平・フェアが通るのなら、「砲丸投げの鉄球重量は体重に比例」とか、「ラグビーのチーム員の体重合計は***kg以内とする」(ラグビーはオリムピックに無いが)とかになる訳かい? ![ym120801-02[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/08/ym120801-021-213x300.jpg) そもそもジュードウの体重別制も、身長も体重も小さなアジア人に投げ飛ばされる「耐え難い絵柄」を衆人に見られたくないという邪心に拠っていたと、柔道部の先輩が言っていた。同じ体重クラスなら衆人に見せも出来るという訳だ。 そうした柔道ではないジュードウに何とか合わせて努力して来た日本ジュードウが、煮え湯を飲まされたのがシドニー・『世紀の誤審』だ。 2000年シドニーオリムピックの100㎏超級の篠原・ドイエ戦の『世紀の誤審』については、今さら解説も不要だろう。動かぬ証拠(YouTube画像 http://video.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B7%E3%83%89%E3%83%8B%E3%83%BC%E7%AF%A0%E5%8E%9F%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%A4%E3%82%A8%E6%88%A6+%E4%B8%96%E7%B4%80%E3%81%AE%E8%AA%A4%E5%AF%A9&tid=6c4429eb067a9be79b9d663dd4630bdf&ei=UTF-8&rkf=2 )を添付して、ぼくの断じてナショナリズムではない「アンチ・偏欧米スタンダード」の根拠の一端としておく。 ちなみに、ドイエ自身は篠原の技の直後、呆然として「一本取られた」という表情で事実を認めていた。
そもそもジュードウの体重別制も、身長も体重も小さなアジア人に投げ飛ばされる「耐え難い絵柄」を衆人に見られたくないという邪心に拠っていたと、柔道部の先輩が言っていた。同じ体重クラスなら衆人に見せも出来るという訳だ。 そうした柔道ではないジュードウに何とか合わせて努力して来た日本ジュードウが、煮え湯を飲まされたのがシドニー・『世紀の誤審』だ。 2000年シドニーオリムピックの100㎏超級の篠原・ドイエ戦の『世紀の誤審』については、今さら解説も不要だろう。動かぬ証拠(YouTube画像 http://video.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B7%E3%83%89%E3%83%8B%E3%83%BC%E7%AF%A0%E5%8E%9F%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%A4%E3%82%A8%E6%88%A6+%E4%B8%96%E7%B4%80%E3%81%AE%E8%AA%A4%E5%AF%A9&tid=6c4429eb067a9be79b9d663dd4630bdf&ei=UTF-8&rkf=2 )を添付して、ぼくの断じてナショナリズムではない「アンチ・偏欧米スタンダード」の根拠の一端としておく。 ちなみに、ドイエ自身は篠原の技の直後、呆然として「一本取られた」という表情で事実を認めていた。
選手たちの頑張りに、勝手に生来の「アンチ*****」を仮託してのオリムピック観戦だった。まぁ、いかがわしいルールやその背景でも、それを乗り越える者が出てきたりするし、スポーツはスポーツだ。影響は限られていよう。しかし、社会的営みに関するルールは人間の生存の全領域に及ぶのだ。言えることは、中小零細企業も、狭い農地で生産する農家も、市井の民も、北島康介たちのようには「恣意的なフェア」による「スタンダード」を跳ね返す、度外れた能力など持たないということだ。スポーツに於いてさえこのようなアンフェア「フェア」を押し進める者たちは、経済・貿易・製造・農業・医療・保険・他で、例えばTPPにどんな「公平」を準備しているのか・・・?
翻って想うに、この国の・この社会の「当たり前」「与件(の一部)」とされているルールの多くは、理不尽で恣意的で身勝手な人員構成や手順で決定され、かつ日々ご都合主義的な変更を繰り返してはいまいか。そして、ぼくならぼくは、そのルールを作る側に居るのではないか? そうでなくとも、「ネットを上げる」「スキー板を身長比例とする」などに、かつては即座に「それはおかしい!」と思えた思惟力・感性・嗅覚を喪っていはしまいか? 例えば、
*条約により米軍に基地を提供し、その過半(3/4)を沖縄に置く。返還されるはずの、世界一危険な市街地の基地に欠陥機オスプレイを配備する。 *原発は過疎県海岸地域に建設し、使用済み核燃料の処理方法や廃炉方法はこれから考える。 *今後のエネルギー政策の如何によらず、「日米原子力協定」に基づき、日米の原子力共同研究・協力は続け原発輸出は続ける。 *福島原発事故に関して、民主党政権を問い東電を責めるが、米の設計・メーカーに欠陥や不備を問わない。 *年金のダブル・スタンダードいやトリプル・スタンダードは、勤労者各個人の職場選択の結果であり自己責任である。 *企業たるもの、任意の数の正社員で運営し、他は有期雇用・派遣社員・下請など非正規雇用者で賄うべきである。競争に勝ち抜く為に、法や制度を最大限活用して、その非正規雇用者への企業責任から免れる研究・努力に励まねばならない。 *労働組合の使命は、正規雇用労働者が所属企業の発展や賃金の上昇などを実現することであって、下請・臨時・パート・季節・派遣労働者の雇用形態や権利問題などに関わる言動を行うことではない。 *公務員は、所属機関の政策批判をしてはならないし、政治的言動をしてはならない。
ともあれ、残された時間を、構造的「アンフェア」を推進したりそれに手を貸すことに使いたくはない。 出来れば、どんなに微力でもその構造に抗う「生」を立てたいと思ってはいるのだが・・・。
たそがれ映画談義: 小百合さん撮影中作品 『北のカナリアたち』 秋公開

前作『おとうと』にやや失望( http://www.yasumaroh.com/?p=3233 )しただけに、撮影中の本作には期待してます。 生徒たちの20年後を演じる6人の若手についてもいずれも好きな役者さんなんで、それも楽しみです。 「告白」の湊かなえの著書「往復書簡」を原案に、吉永小百合主演、阪本順治監督で描くヒューマンサスペンス。日本最北の島・礼文島と利尻島で小学校教師をしていた川島はるは、ある事件で夫を失う。それをきっかけに島を出てから20年後、教え子のひとりを事件の重要参考人として追う刑事の訪問がきっかけとなり、はるはかつての生徒たちに会う旅へ出る。再会を果たした恩師を前に生徒たちはそれぞれの思いを口にし、現在と過去が交錯しながら事件の謎が明らかになっていく。
単純な敵・味方二元論、ゲーム世代的文化観 それはそれで勝手だが
真っ当な人々に刃を向ける以上、捨て置けない。 橋下市長の実像。 ズバリ それは幼児の残虐性だ!
産経新聞によれば、26日再度文楽を視察した橋下氏の言い分は以下の通り。 『財団法人・文楽協会への補助金凍結を示唆している大阪市の橋下徹市長は27日、国立文楽劇場(大阪市中央区)で前夜鑑賞した文楽について「人形劇なのに(人形使いの)人間の顔が見えると、中に入っていけない」と批評。「クライマックスのときに、顔がポコッとみえるのは、どうも腑に落ちない」と率直な感想を述べた。 橋下市長は26日の文楽鑑賞後、「大阪発祥の古典芸能が守るべきものであることはよく分かった」と理解を示す一方、「演出など、見せ方をもっと工夫すべき」と注文をつけていた。』 -7月27日13時50分配信-
(何故、君の貧弱で稚拙な感性の腑に落ちなければならないのか!恥を知れ!)
(歌舞伎の、大見得とか六方とか誇張された所作の様式美なんかも「あり得な~い」と却下するのか。歌舞伎はメジャーで芸能ニュースネタも含めてマスコミにも再三登場するから、「行列のできる***」と同じく、ボクちゃんは認めるのかい?)
例えば、近未来SF映画とアメフトの大ファンでもあり天下の正義漢を自認する、カウボウイ・スタイルのアメリカ大統領が、円形野外劇場のギリシャ悲劇を鑑賞して「難解なセリフの応酬より、舞台にもっと大道具など『見える化』を工夫しないと・・・。あの服装で直立して語るのには入っていけない」と言い、日本の大相撲に「体重制」がないのは「アンフェア」で「腑に落ちない」と論評したら、どうか? 体重制なきある種の「非合理」を含めて「大相撲」とする体系なんですから米大統領といえども「放っといてくれ!」です。
例えば、アメリカの成金石油王が、イタリアのヴィスコンティの映画『山猫』を観て、「何やら重厚な装飾は立派だか、ラストにググッとくるものがなかった。台本が古い、現代に合う様に工夫してもいいのではないか?」と言えば、ヨーロッパの映画ファンは怒りを越えて、成金の無教養とガサツさに言葉を失うだろう。シチリヤの市街地、石畳の舗道に跪(ひざまづ)き、滅び行く者の悲哀と覚悟を胸に矜持と受容を抱え、静かに祈るサリーナ公爵(バート・ランカスター)(この人、これと『エルマー・ガントリー』『家族の肖像』があるから歴史に名を残した役者なのだ)。 イタリア統一運動、赤シャツ隊、時代の節目、旧体制の終焉、理想どもの裏切り、新興勢力の現実主義・・・多くの終わりと始まりを目撃しながら生を閉じて行く公爵。うらぶれた小径へ曲がってゆく公爵の後ろ姿・・・。 あのラストシーン・・・、ぼくは好きですが。
これらの、ゲーム熱中世代の中学生のような軽薄で幼い文化観と、下記に示す間違っていて単純な正義感と言うか幼児性丸出しの独善・攻撃性は、同じ根っこのものだと思いませんか?
大阪市環境局の現業職員の労働組合がごみ収集事業の民営化方針に反対するチラシを戸別配布していた 問題で、橋下徹市長は11日の市議会本会議で、「組織の方針について反対を促すような行動は、組織の信頼を失墜させる行為として厳しく処分したい」と述べ、 関与した職員の懲戒処分を検討する意向を示した。 ( 何を言うとるんじゃ!! だから独裁者と言われるのよ) あんた、弁護士やろ! それ、何に基づいて言うとるの? 何人も「組織の方針について反対」を表明する自由と権利を有してるの!
公立学校の先生が、子どもの家事業廃止を批判したことが我慢できないらしく、執拗な攻撃を繰り返しています。「現場を知らない」のはどちらでしょう?twitterする暇があるなら、高校生が話していたように現場に来て、見て、感じることから始めるべきです。
そして彼は言い放っています。「公立高校教員が教員の身分で決定された市政改革に口を挟むのは断じて許されない」と。 (納得できない市の施策に已むに止まれず意見を吐く教師は許されない。と言うような行政トップは「許されない」)
子育ての 「私」性と「公」性-後編
若い母親よ、苦境を越えてくれ
当事務所まで来てくれたのは、区の***部**係のA氏、提携の外部団体****のB氏。 なるほど、子ども・子育て・家庭と冠が付くここでも民間委託・外注なのか? 区職員が云わば管理職・デスクワーク、外部団体が現場というか直接案件に接する配置か? ならば、いわゆる丸投げ・下請けではないのか? 人減らし・効率化(という名の営利企業的運営)ではなく、逆に官的対応・官的感性では至らなかった面を補うべく、官民の複合による活性化へと向かう試みなら言うことは無いのだが・・・。 我が事務所で一時間、目撃した状況を説明し、区や学校が出来ることの可能性について話した。これまで、当案件の通報はなかったと言う。 数日内に問題の時間帯に四辻に来てみます。学校を特定し、個人を特定し、まず母親本人・学校と話してみます。おうおう、中々スピード感あるやないか。
 ぼくの顔つきが強面(?)だし「疎か(おろそか)」に扱っては後が大変そうだからか、男性高齢者からこの種の通報は珍しいからか、 官・民の二人は真剣に聞いてくれた。 母子のプライバシーもあり、詳細のご報告は「概略」しか出来ないと思いますが、ご了承下さい。ああ、結構ですよ。あの子への暴力が無くなり、事態が母子が前進する方向へ動くのなら、固有名詞・プライバシー絡む詳細、そんなことはどうでもいいんです。
ぼくの顔つきが強面(?)だし「疎か(おろそか)」に扱っては後が大変そうだからか、男性高齢者からこの種の通報は珍しいからか、 官・民の二人は真剣に聞いてくれた。 母子のプライバシーもあり、詳細のご報告は「概略」しか出来ないと思いますが、ご了承下さい。ああ、結構ですよ。あの子への暴力が無くなり、事態が母子が前進する方向へ動くのなら、固有名詞・プライバシー絡む詳細、そんなことはどうでもいいんです。
学校・本人・夫と話し合えた、と電話で報告があった(夫はいたのだ)。夫は毎日早朝出かけるので事実を知らなかった。夜は大きなトラブルも無く、隣近所とも上手く行っている、と言う。 それが、事実なら朝の通勤前の慌しい時間帯だけに起きているパニックなのか? なら勤務先に、子の登校時グズルことのみ話して出社時間を・・・と言おうとすると、「勤務先と話すように勧めました。」 日を次いで報告を得たいが、気になりながら一現場終了を得て通例通り10日間ほど帰阪した。
6月中旬、「集団登校にはまだ加わらないようです」「2:1の割合で、父親も送るようになりました。父親も勤務工夫を勤め先にお願いしたそうです」と連絡がった。下旬、また帰阪した。
7月中旬、A氏B氏の再訪を受けた。「母親の勤務を30分後ろにずらしてもらえました」と報告があり話し込んだ。通学時だけなのか、日常がどうなのかを密かに調べた苦労など、この「公」務員、中々やるじゃないか、と思わせる話がいっぱい。夫の経済的・仕事内容の苦境・学校との話し合い、夫婦ともの勤務先の件、・・・・・・容易ではないだろう。働くための条件は、子育てに直接大きく絡んでいるのだ。 女子プロレスラーのように大柄なあの母親は「誰かが通報してくれないか」と思っていたそうだ。きっと、止めに入った関西弁の中年男性だと思いますが、もう大丈夫ですとよろしくお伝え下さい、と・・・。夫婦で号泣なさったそうです。
一度離婚して同じ組合せの再婚だそうだ。「昨秋からの復縁で失敗してはならじと肩を怒らせて生きていたかも・・・・・・。夫とも話し合えました。」と言っているそうだ。A氏が言う、「息子が、学校生活に馴染めず毎朝登校を渋る事実は、夫に知られたくなかったんですな」 離婚・再婚に付着している、本人だけが知る「負目」「事情」「愛憎」は知るよしもない。たぶんそこに、人には語れない・人には解からない、夫婦の歴史があるのだろう。だが、子はそんなことからは解き放たれて生きる権利がある。そして、偉そうなことは言えないが、夫婦ちゅうものは、そうした「負目・遠慮・背伸び芝居」を続けていては、再崩壊やで、と思った。 もし、報告の通りなら、いい方向に向かっているのだろう。この母子のようには行くことは稀なんですか? まぁ、いろいろですね、今回ご亭主がマトモな人で助かりました、だそうだ。いつもこうは行かないだろうし、このケースも先がどうなるか不安だ。 もし、母親が言っている通り「誰か通報してくれ」「多くの他人に諭されて立ち直りたい」が事実なら、この母親はギリギリ踏みとどまる理性いや母性を持っていたのだ。 頼むよ、しっかり自分と息子を生かすんやで! 関西弁爺のお希いです。
************************************************************
ともあれ、A氏B氏の動きが無い(または遅い)なら、こうはならなかった。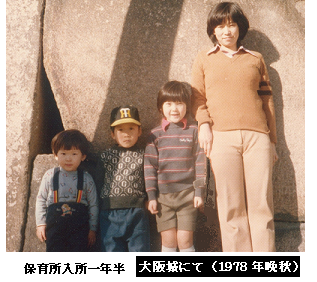
「公」の仕事ぶりに謝意を抱いたのは、昔、労働争議(組合否認の偽装破産VS職場バリケード占拠)のさ中、当方には5歳児・3歳児・1歳児と子が三人おり働けなかった妻が、無収入回避の為に勤めるに当たり、中途入所(しかも仕事が見つかる前から)という弾力的運用で保育所入所を措置した某市の福祉事務所長の英断・・・、あれ以来だなぁ~~
「私」の決意や努力が、「公」の誠意と理ある運用に遭遇する時、「公」「私」の本来あるべき形が見えるのかも。 いや、奇妙な効率主義や「指図務」さえ無ければ、市民と本来の公務員は、そのように響き合って在ることを求め互いに呼び込むのではないか・・・。そう思いたい。

