連載 28: 『じねん 傘寿の祭り』 三、 タルト (6)
三、タルト ⑥
黒川はまず美枝子を博多に住まわせた。敷金はちょっと立て替えてくれと言われ、もちろん美枝子が出した。次いで黒川は、美枝子を店員として店に採用し、店を二人の物にしようと画策した。妻から業務の実権を奪おうという魂胆だ。なにしろ、黒川は子供の小遣帳程度の数字でも「頭痛が起きる」と把握できない幼児で、運営の全ては妻の手にあったのだ。美枝子も手が出ない。一時、妻と美枝子が同時に店に居ると言う修羅場だったが、すぐに妻は出て行き、手を打った。反撃だ。経理・財務の一切を仕切っていた妻は百貨店を含む各得意先と、黒川が切り拓いたあちこちの作家に夫の非道を訴えた。唐津の某作家のように「百貨店の女店員をたらし込むとは何ごとか!」と引上げる者もあって、幾つかの回線は妻の思惑通り切断されしてしまった。 福岡県美術家協会の大物が調停に乗り出し、これといった資産のない黒川が、店の権利と在庫一切を差し出すことを条件に、離婚は成立した。
「店の奥の居間で、私たちを囲んで座っている協会のお歴々を前にして黒川が吐いた決め台詞、カッコよかったのよ。しびれちゃうよ」 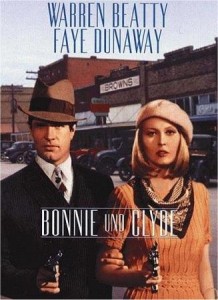 「何て?」 「いくら何でも恥ずかしいなぁ」 「ここまで言うた以上、喋らんとぉ」 「そうね。言っちゃおうかしら・・・」 「はい、言うて下さい」 「言うね。こう言ったのよ。『たとえ世界中を敵に回すことになろうとも、ぼくはこの人を採る』だって、クッフフフッ、あーあヒドイ」 「おっと、そりゃ新派以上や」 「冷や汗が出るわね。いくつになっても昔とおんなじで、歯の浮くようなスローガンに弱かったのね、私」 そうなのだ美枝子が浪速大に来たと言う前後の「あの時代」、周りには魂に届いたと思えるスローガンやキャッチ・コピーが咲き乱れていた。「全世界を獲得する為に」「一人一党派」「感性の無限の解放を」「連帯を求めて孤立を恐れず」・・・・それは、つまり八方塞がりの「公」的状況と、個的な行き詰まりの「私」的迷路の袋小路を、瞬時にそして大きく解き放ってくれたのだ。美枝子だけでなくドンピシャの言葉には誰だって弱い。「いくつになっても」? 今、美枝子の和服姿を見ていると、その当時の「三十になっても」が「五十八になっても」と聞こえなくもない。 博多の妻との二人の子供は成人しており、姉は嫁ぎ弟は大学生だったが、父親には愛想を尽かしていて、彼らは事態を静観していた。店は大衆工芸品や博多の土産物屋に化けて今も在るはずだという。元妻と娘で運営している。その時の大量の在庫は、その理事たちを含む地元の同業者が上手く買い叩こうとしたが、母子はそれを巧みに小出しして捌き、永年食い繋いだという。七七年秋、美枝子と黒川は博多を離れた。 「裸一貫とはあのことね。互いに大きなスーツ・ケースを牽いて、三十と五十一の道行きみたいで、ほんとスリリングで今思い出しても楽しかった」 「金も無かったんでしょ」 「うん。私が父から貰ったお金が百五十万残ってた。それが軍資金」 東へ向かった。東京へ行こうとなっていた。東京には、話半分だと思うけど、同業の古い友人がいて部長として迎えてくれる手はずになっているという。考えたらあれが新婚旅行だった。広島に立ち寄ろうってことになって、宮島に泊って、翌朝原爆ドームへ行くと、黒川の様子がおかしい。 父母・叔父叔母、みんな長崎で亡くしたと聞いていて知ってたけど、広島で込み上げたみたいで・・・。 黒川は「広島でその威力・被害規模も充分知っていたのに、再び長崎に落としたのはより罪深い。アメリカを許せん。もっと許せんのは、降伏を延ばし、沖縄地上戦・広島・長崎を招いた奴らだ」と震えていた。
「何て?」 「いくら何でも恥ずかしいなぁ」 「ここまで言うた以上、喋らんとぉ」 「そうね。言っちゃおうかしら・・・」 「はい、言うて下さい」 「言うね。こう言ったのよ。『たとえ世界中を敵に回すことになろうとも、ぼくはこの人を採る』だって、クッフフフッ、あーあヒドイ」 「おっと、そりゃ新派以上や」 「冷や汗が出るわね。いくつになっても昔とおんなじで、歯の浮くようなスローガンに弱かったのね、私」 そうなのだ美枝子が浪速大に来たと言う前後の「あの時代」、周りには魂に届いたと思えるスローガンやキャッチ・コピーが咲き乱れていた。「全世界を獲得する為に」「一人一党派」「感性の無限の解放を」「連帯を求めて孤立を恐れず」・・・・それは、つまり八方塞がりの「公」的状況と、個的な行き詰まりの「私」的迷路の袋小路を、瞬時にそして大きく解き放ってくれたのだ。美枝子だけでなくドンピシャの言葉には誰だって弱い。「いくつになっても」? 今、美枝子の和服姿を見ていると、その当時の「三十になっても」が「五十八になっても」と聞こえなくもない。 博多の妻との二人の子供は成人しており、姉は嫁ぎ弟は大学生だったが、父親には愛想を尽かしていて、彼らは事態を静観していた。店は大衆工芸品や博多の土産物屋に化けて今も在るはずだという。元妻と娘で運営している。その時の大量の在庫は、その理事たちを含む地元の同業者が上手く買い叩こうとしたが、母子はそれを巧みに小出しして捌き、永年食い繋いだという。七七年秋、美枝子と黒川は博多を離れた。 「裸一貫とはあのことね。互いに大きなスーツ・ケースを牽いて、三十と五十一の道行きみたいで、ほんとスリリングで今思い出しても楽しかった」 「金も無かったんでしょ」 「うん。私が父から貰ったお金が百五十万残ってた。それが軍資金」 東へ向かった。東京へ行こうとなっていた。東京には、話半分だと思うけど、同業の古い友人がいて部長として迎えてくれる手はずになっているという。考えたらあれが新婚旅行だった。広島に立ち寄ろうってことになって、宮島に泊って、翌朝原爆ドームへ行くと、黒川の様子がおかしい。 父母・叔父叔母、みんな長崎で亡くしたと聞いていて知ってたけど、広島で込み上げたみたいで・・・。 黒川は「広島でその威力・被害規模も充分知っていたのに、再び長崎に落としたのはより罪深い。アメリカを許せん。もっと許せんのは、降伏を延ばし、沖縄地上戦・広島・長崎を招いた奴らだ」と震えていた。 
 海軍少年航空兵だった黒川は、1945年、昭和二〇年春土浦から小松に転属していた。敗戦後すぐ、小松から苦労して汽車を乗り継いで長崎へ戻り瓦礫の街を歩き、実家に辿り着いた。旅館経営していて羽振りのよかった父、一人っ子の自分にいつも優しかった母、二人に親孝行できなかったことが悔やまれるが、見渡す惨状を見れば諦めるしかなかった、と黒川は言った。ただ、実家横の坂道で、黒川の世話係りだった元女中のウメさんに出会って思い出話も出来たらしい。あれこれ話したが別れ際にした話は、何故か鮮明に覚えているという。黒川は搾り出すように語り始めた。
海軍少年航空兵だった黒川は、1945年、昭和二〇年春土浦から小松に転属していた。敗戦後すぐ、小松から苦労して汽車を乗り継いで長崎へ戻り瓦礫の街を歩き、実家に辿り着いた。旅館経営していて羽振りのよかった父、一人っ子の自分にいつも優しかった母、二人に親孝行できなかったことが悔やまれるが、見渡す惨状を見れば諦めるしかなかった、と黒川は言った。ただ、実家横の坂道で、黒川の世話係りだった元女中のウメさんに出会って思い出話も出来たらしい。あれこれ話したが別れ際にした話は、何故か鮮明に覚えているという。黒川は搾り出すように語り始めた。